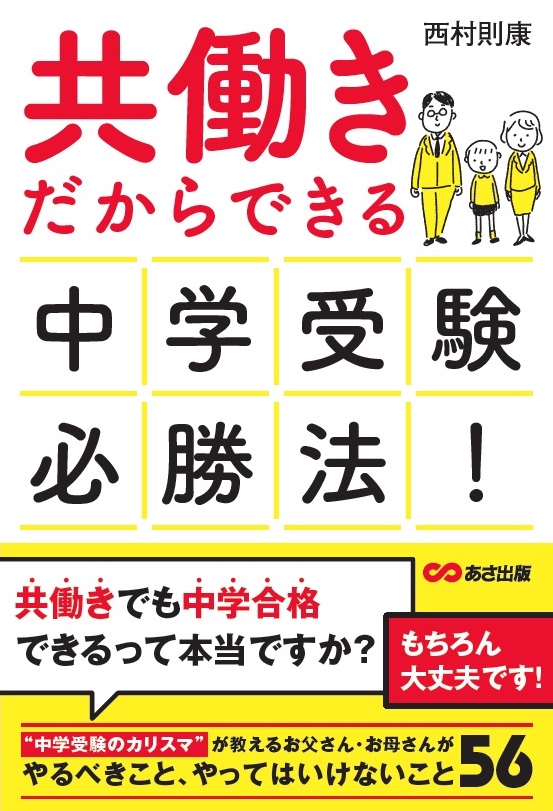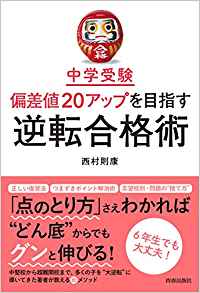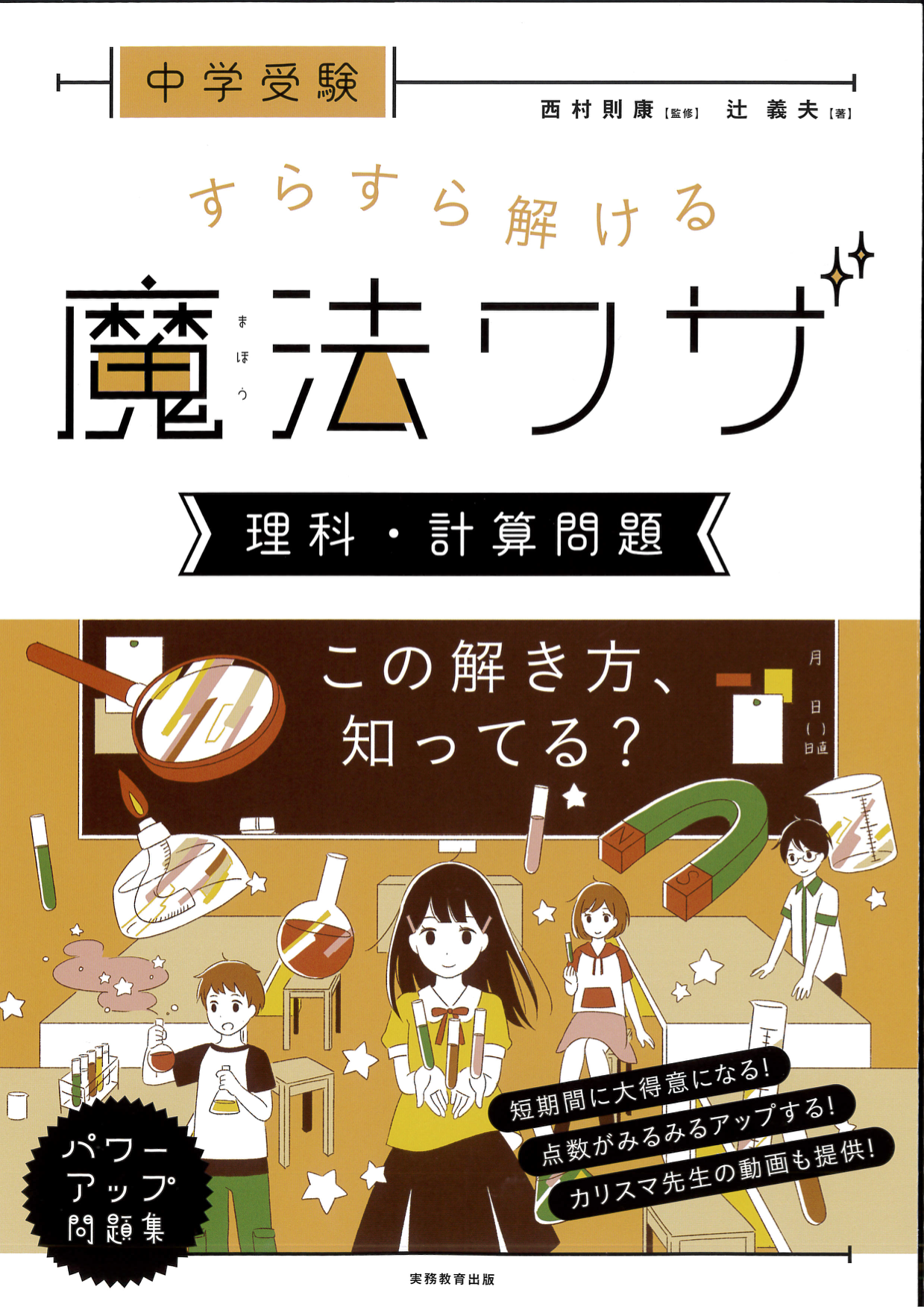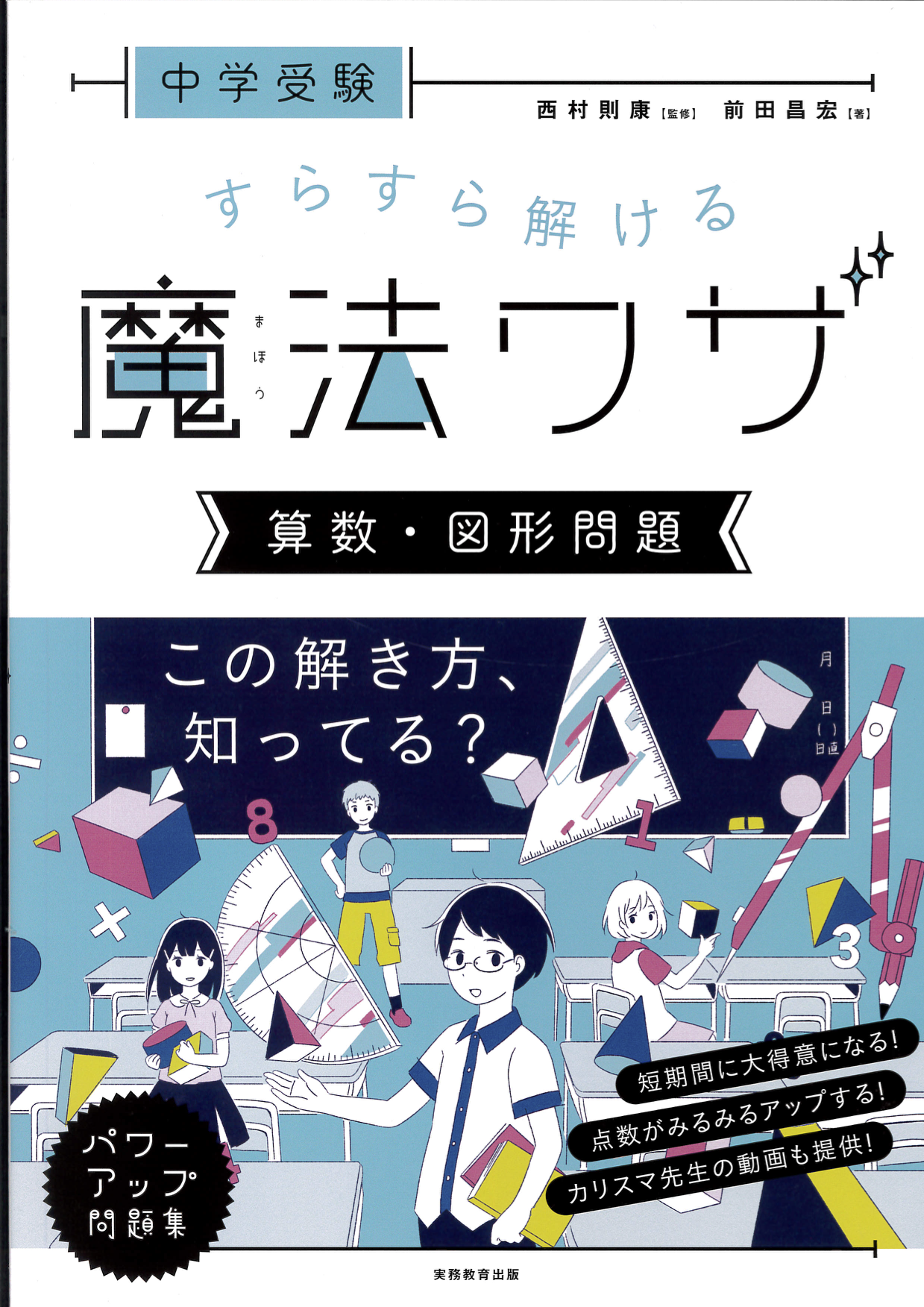Q.
子どもの算数のノートを見ると、算数の授業が、ただの「答え合わせ」になっているようです。
どのようにフォローしていけばよいでしょうか。
(5年生・日能研)
A.
■ 授業の受け方を工夫しましょう
算数はどうしても授業が「答え合わせ」になってしまうことがよくあります。
子どもが問題を解いて、そのあとに先生が正解とその解法を解説するという流れだと受け身になってしまいがちです。
先生もテキストの単元のポイントを読むだけになってしまうこともあるようで、これではもったいないですよね。
そこで、授業の受け方を工夫してみてはどうでしょうか。
授業中に問題に取り組みながら、名門指導会を主宰する西村が停止王する「◯△×方式」で各問題に印をつけていきましょう。
◯…自分で解けた問題
△ …自分で解けはしなかったものの、説明を聞いたら理解できた問題。次に似た問題が出てきても解けそうなもの
×…自分でも解けず、説明をきいてもよく理解できなかった問題
ご家庭で復習するときに、まずは「△」の問題をもう一度子どもにやらせてみてください。
「×」に取りかかると時間がかかってしまうので、まずは「△」を重点的に復習するようにします。
■ ご家庭での「ミニ授業」で理解を深める
子どもが「△」の問題を解くことができたら、その解法を説明してもらう「ミニ授業」をしてみてください。
「どうやって解いたの?お母さん(お父さん)におしえて」ときいてみましょう。
子どもは自分が解いた道筋をほかの人に説明することで、より理解を深めます。
また、お母さん(お父さん)に教えることができた、説明することができたことが大きな自信にもつながるでしょう。
ここでのポイントは、大人が途中で口をはさまないこと。「そうじゃないでしょ、こう解くんじゃないの?」ではなく「なるほどね」「そういうことか。次はどうするの?」などと子どもの説明をきいてあげてください。
大人が「教える」のではなく「教わる」ことに徹底してください。
■ 宿題にも優先順位をつける
さらに、宿題でもそれぞれの問題に「◯△×」の印をつけて、まずは「△」「◯」から先に行うようにします。
「×」は、時間が足りなければ省いてもけっこうです。
全部を完璧にやることが目標ではないので、最優先は「△」だということを前提に宿題をする習慣をつけておきましょう。
テスト直しは「正答率」をひとつの目安とし、まずは正答率が高いものを優先的に復習して、知識を定着させておきましょう。
■ 優先順位を意識しながら学習に取り組む
授業だけでなく、宿題やテスト直しもそうなのですが、すべてをこなそうとせずに、優先順位をつけて効率良く取り組めるように、問題に印をつけたり正答率を見たりする工夫ができるとよいですね。
子どもだけでは判断が難しいこともあるので、大人がうまくフォローしてあげましょう。塾の授業は同じ単元を何度かやるので、「難問まですべてやらなければ」という心配をする必要はありません。
どんなお子さんの成績も最速でアップさせる プロ講師の『分析力』『着眼点』をお知らせする 無料メールマガジンを配信しています。
これまでに5000人以上のお子さんを、開成・麻布・武蔵・筑波大駒場・桜蔭・雙葉・女子学院・灘・甲陽・東大寺・洛南・神戸女学院などの難関校に合格させてきた名門指導会の講師陣。
そんなプロ講師のノウハウがぎっしり詰まったメールマガジンである『うちの子だけの合格マニュアル』を配信しています。
購読者の皆さんには毎週最新の合格マニュアルをお届けします。

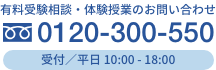


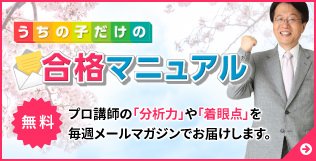



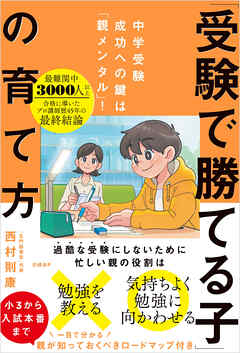
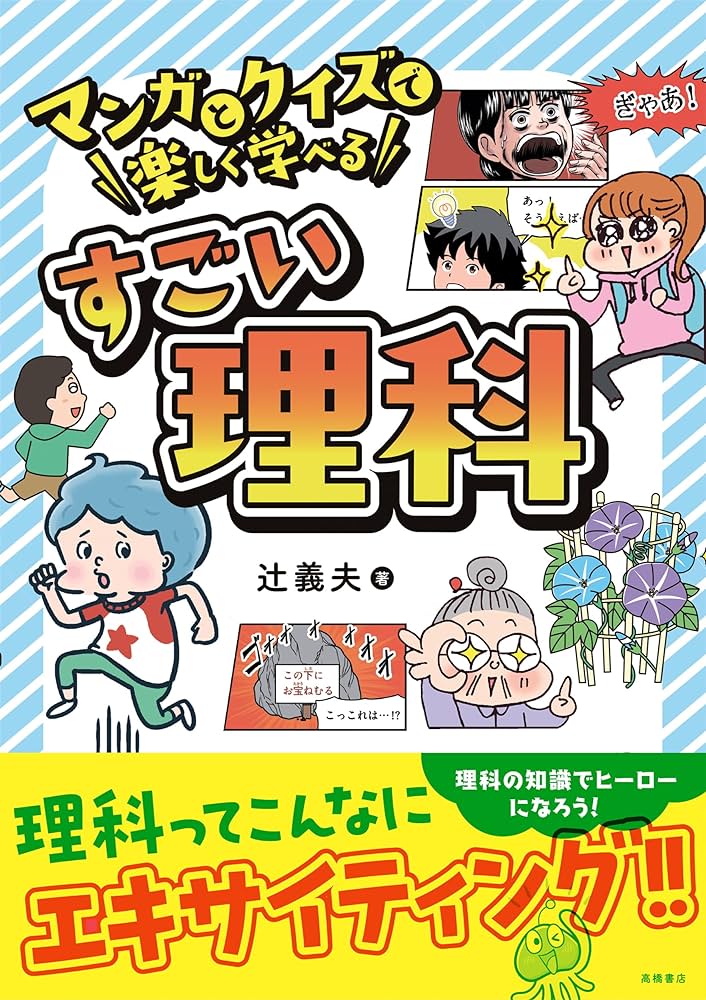
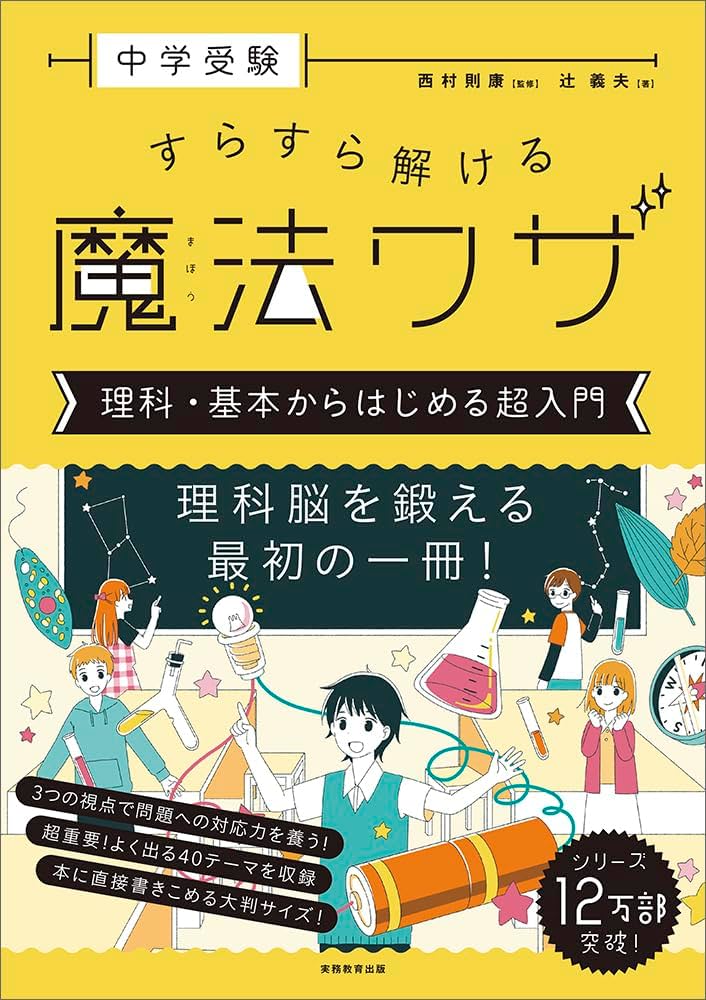
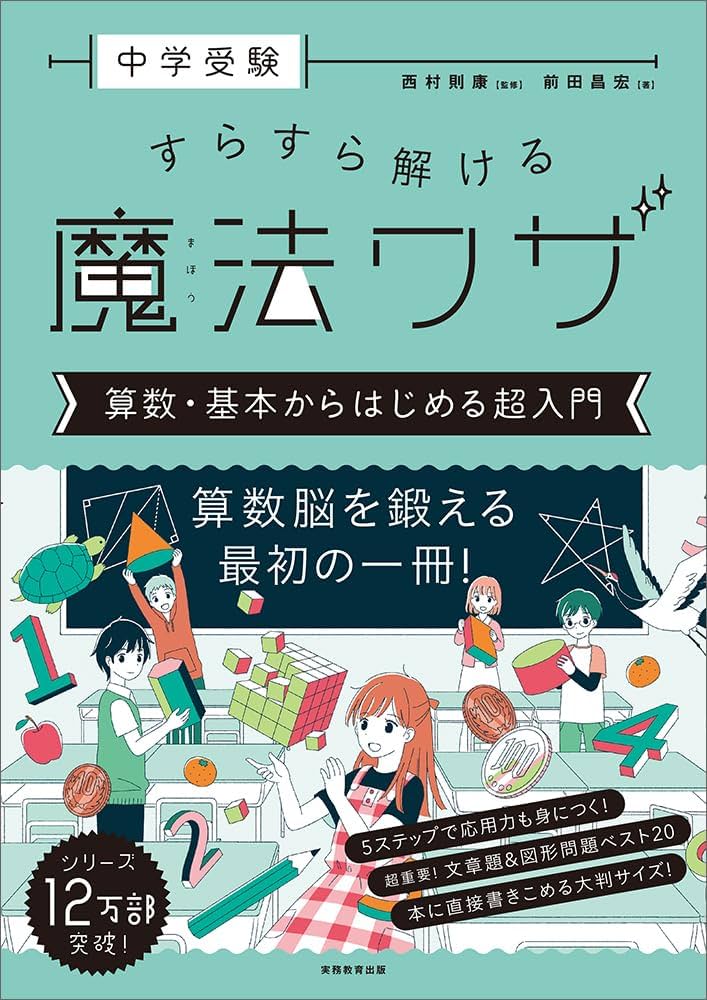
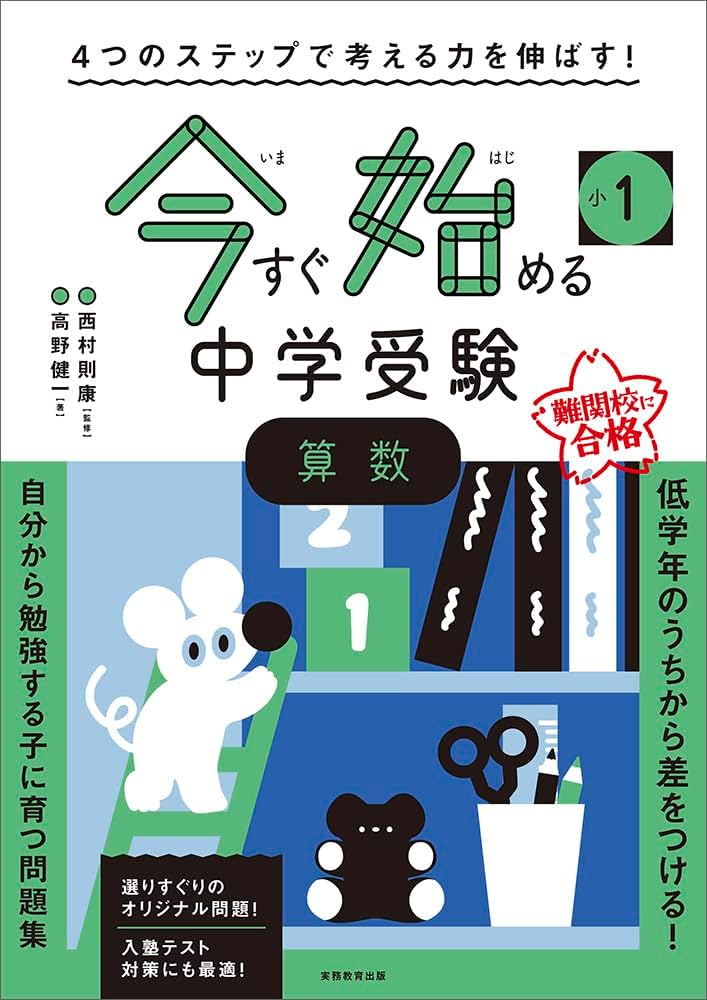
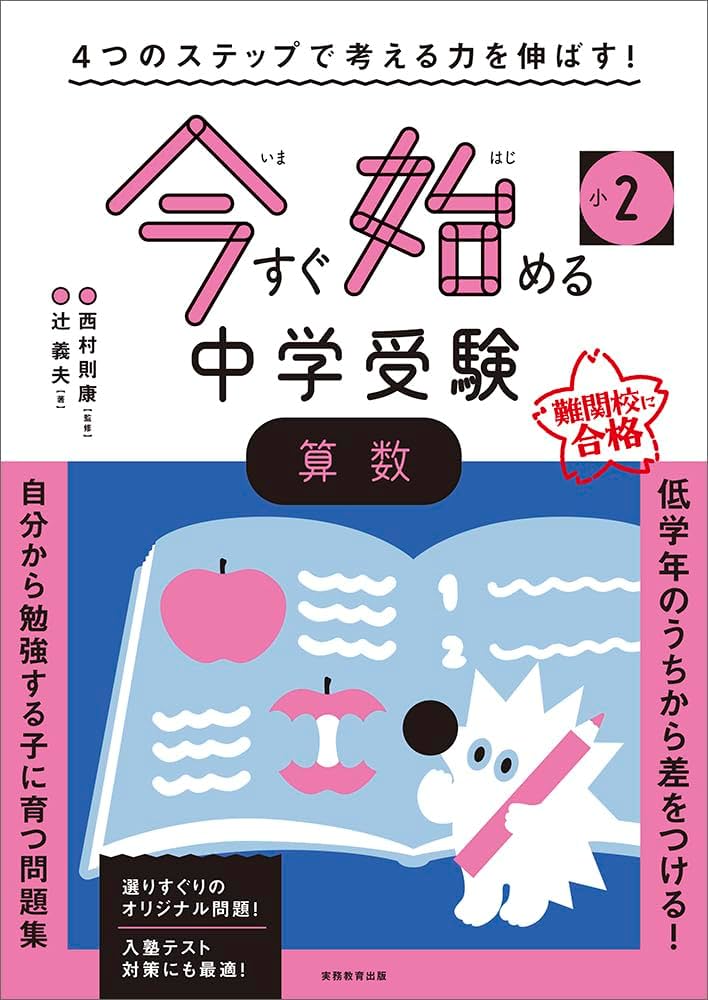
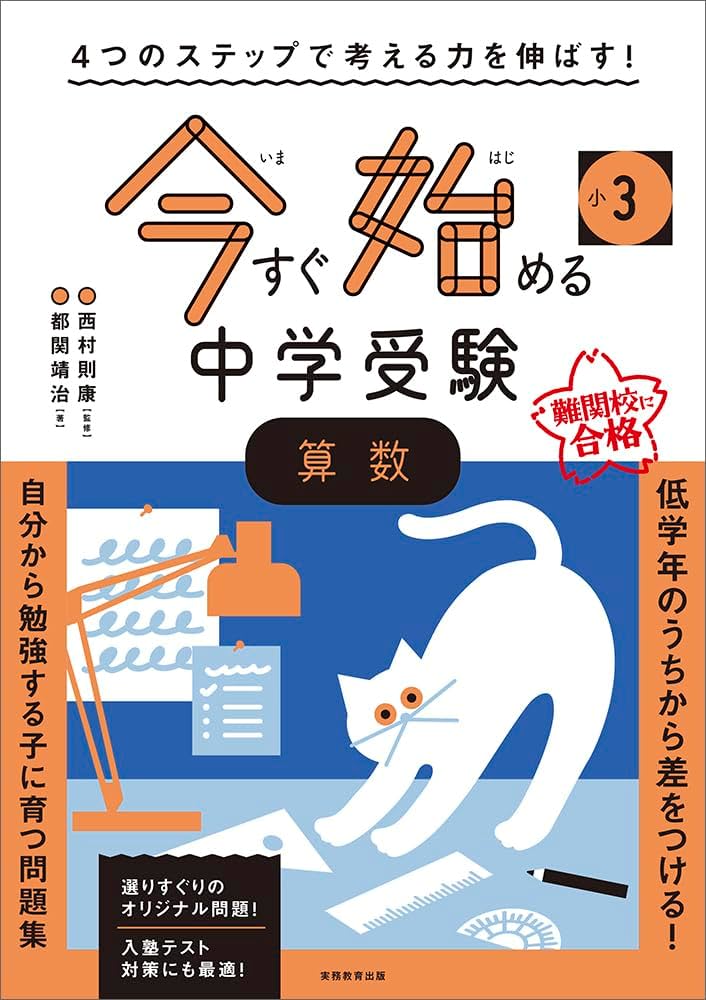
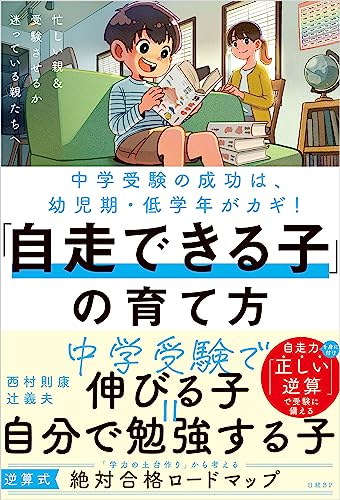
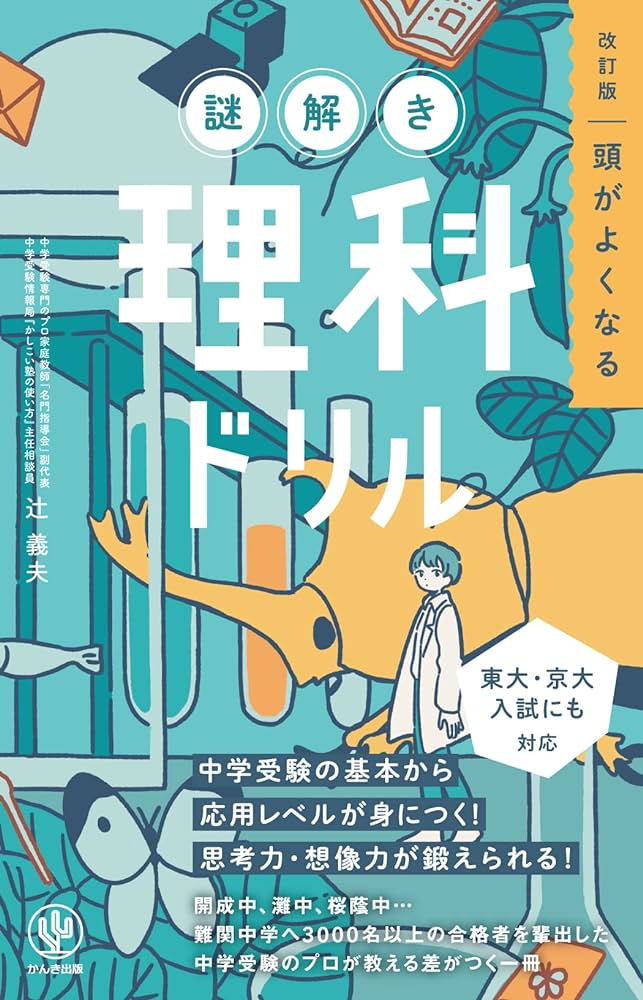
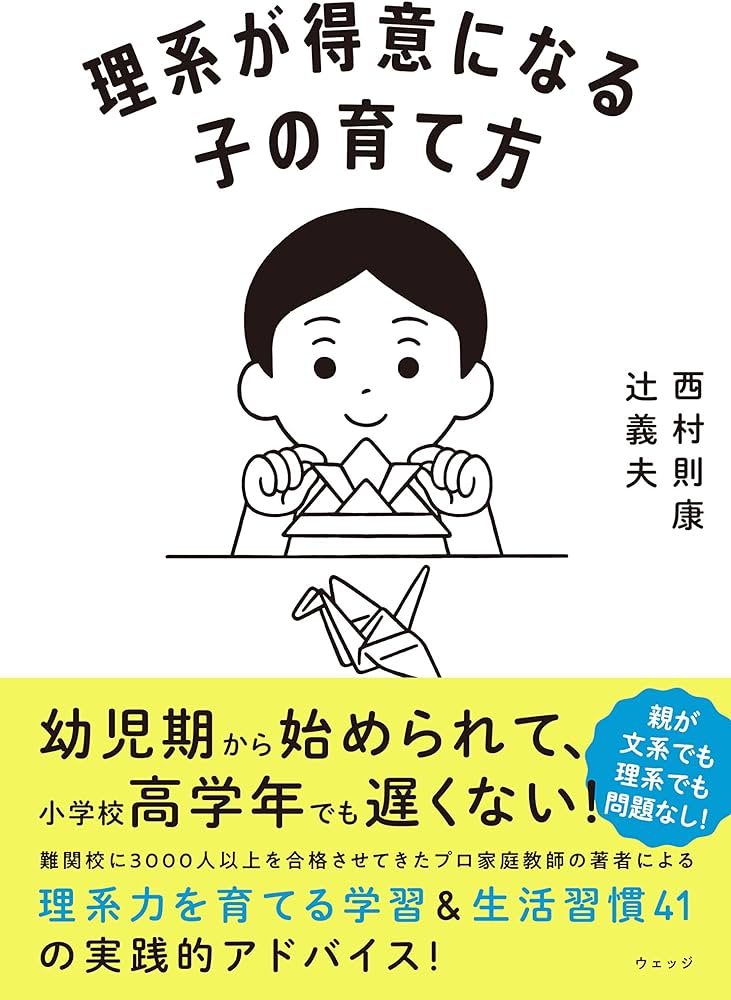

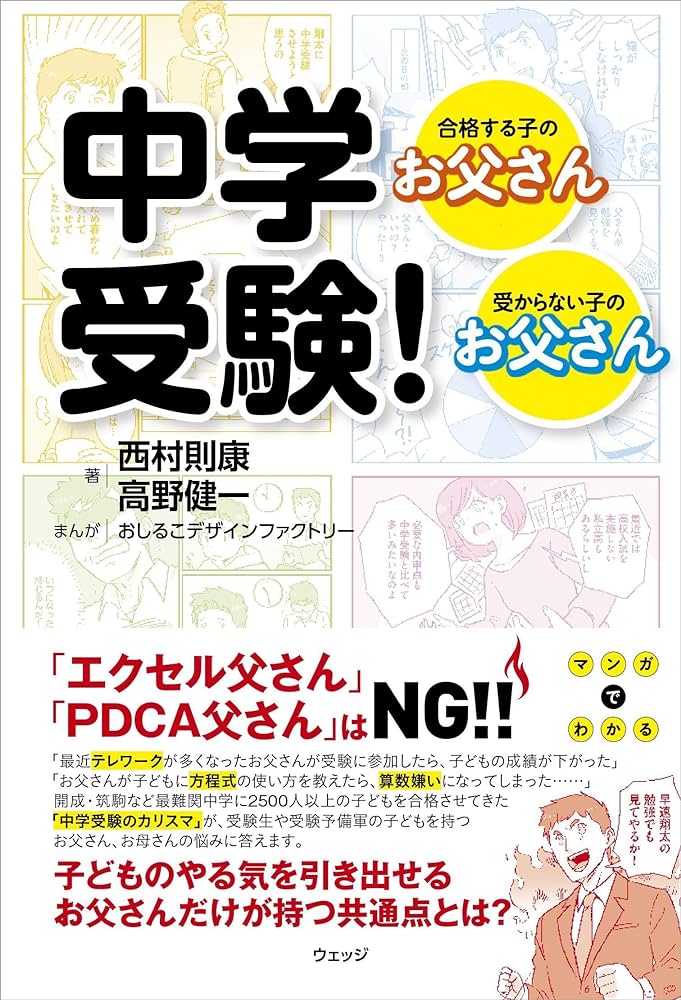
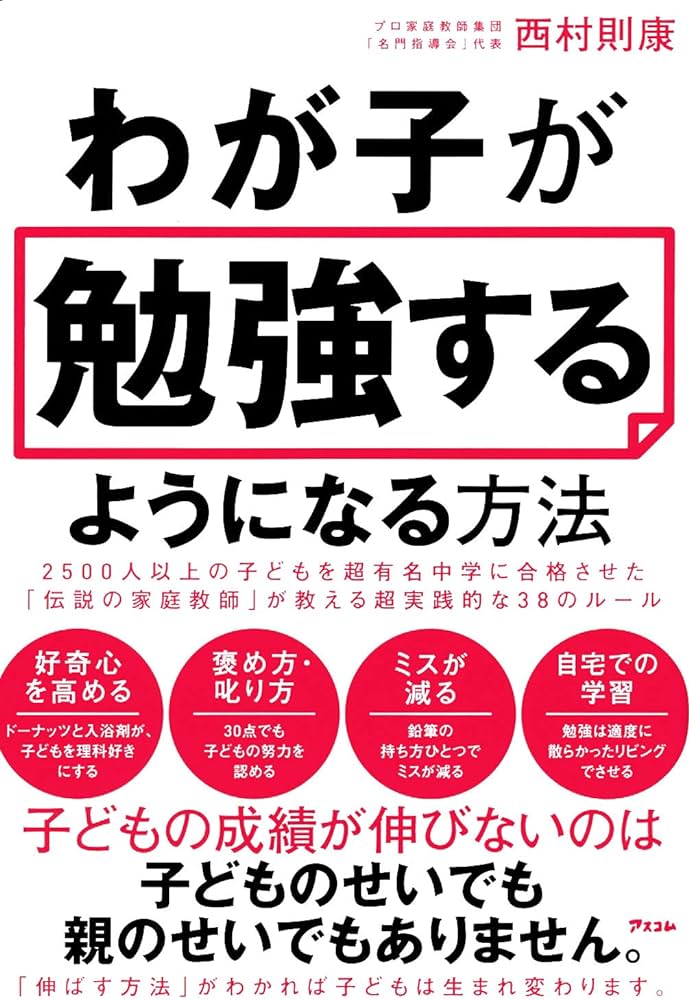
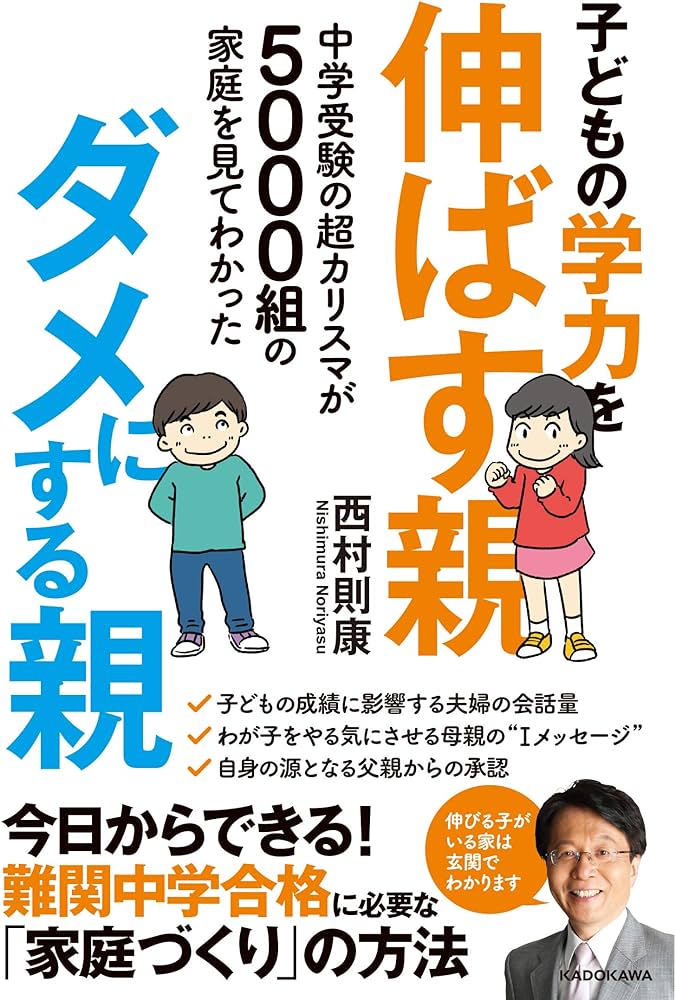
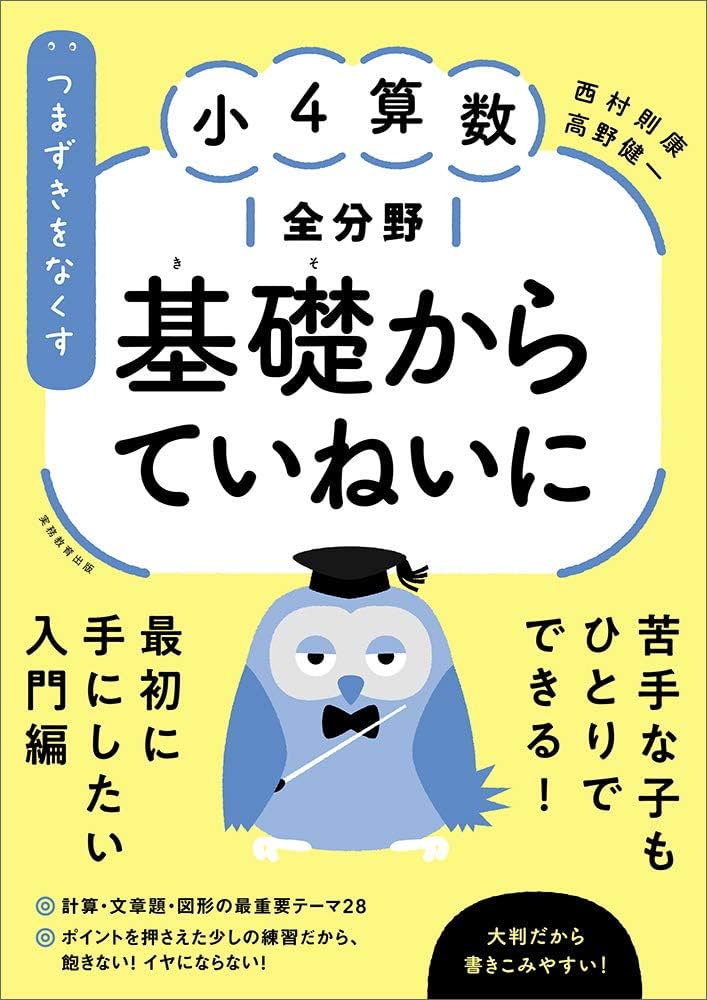
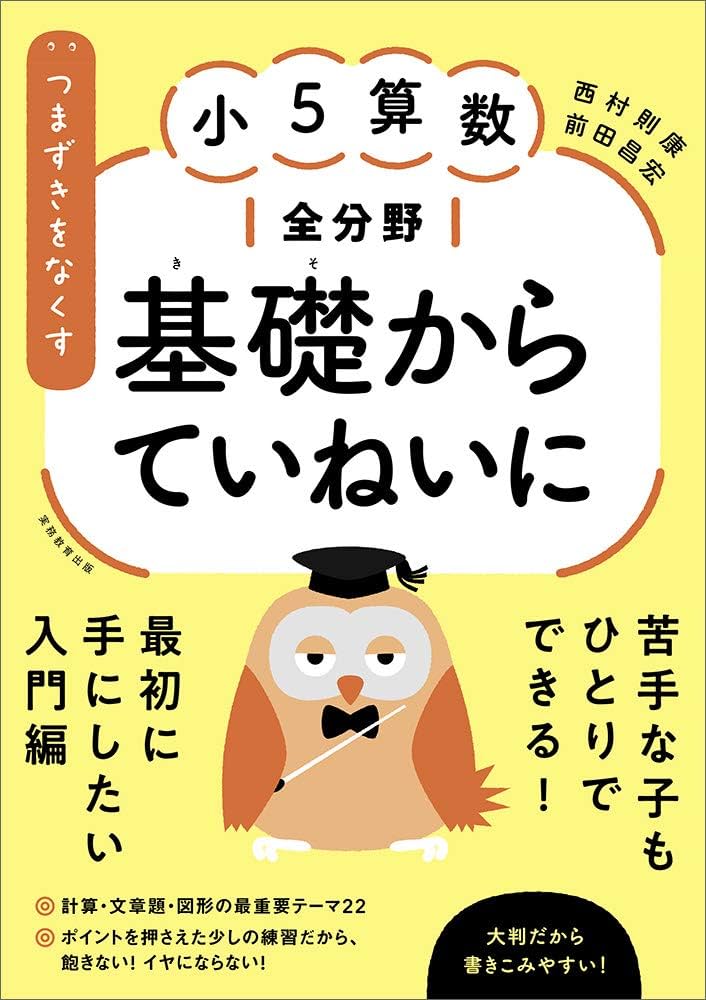
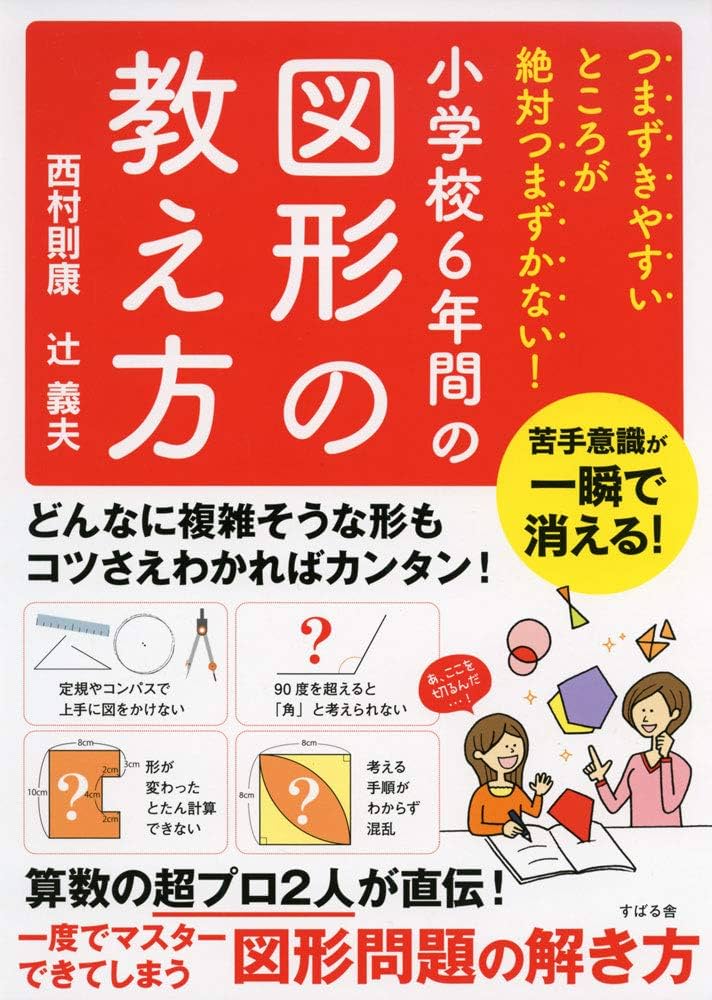
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[算数]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushsansu.jpg)
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[国語]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushkokugo.jpg)