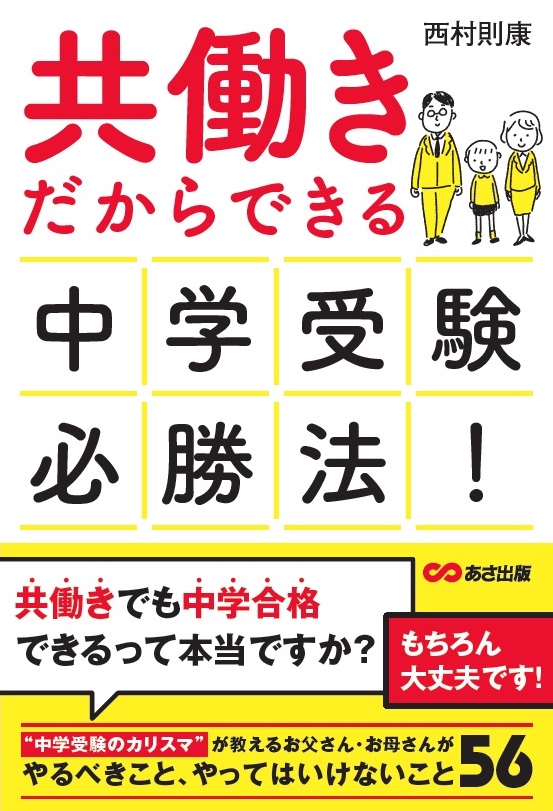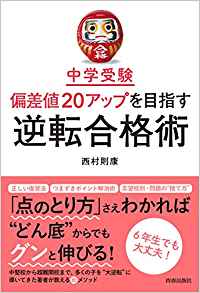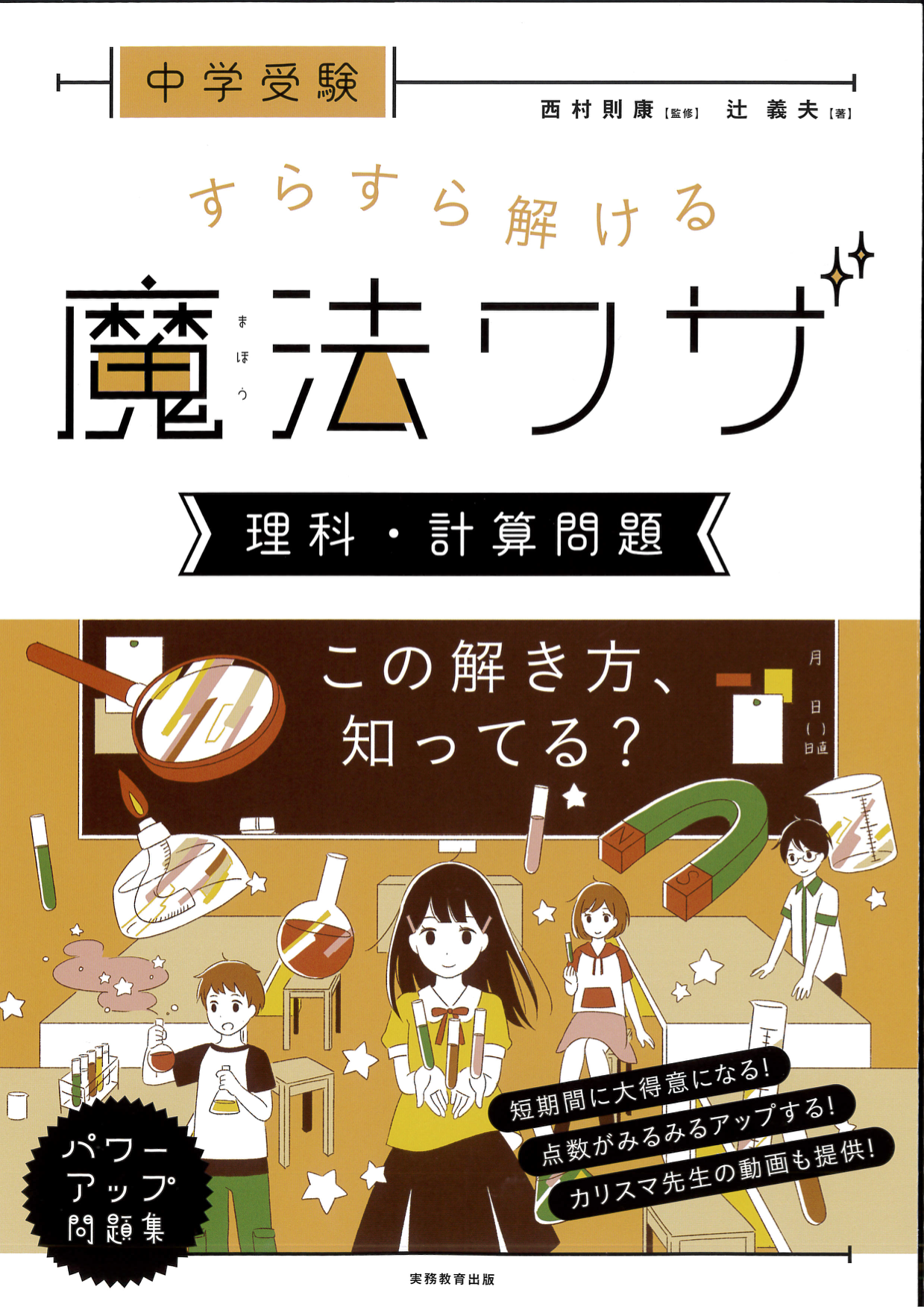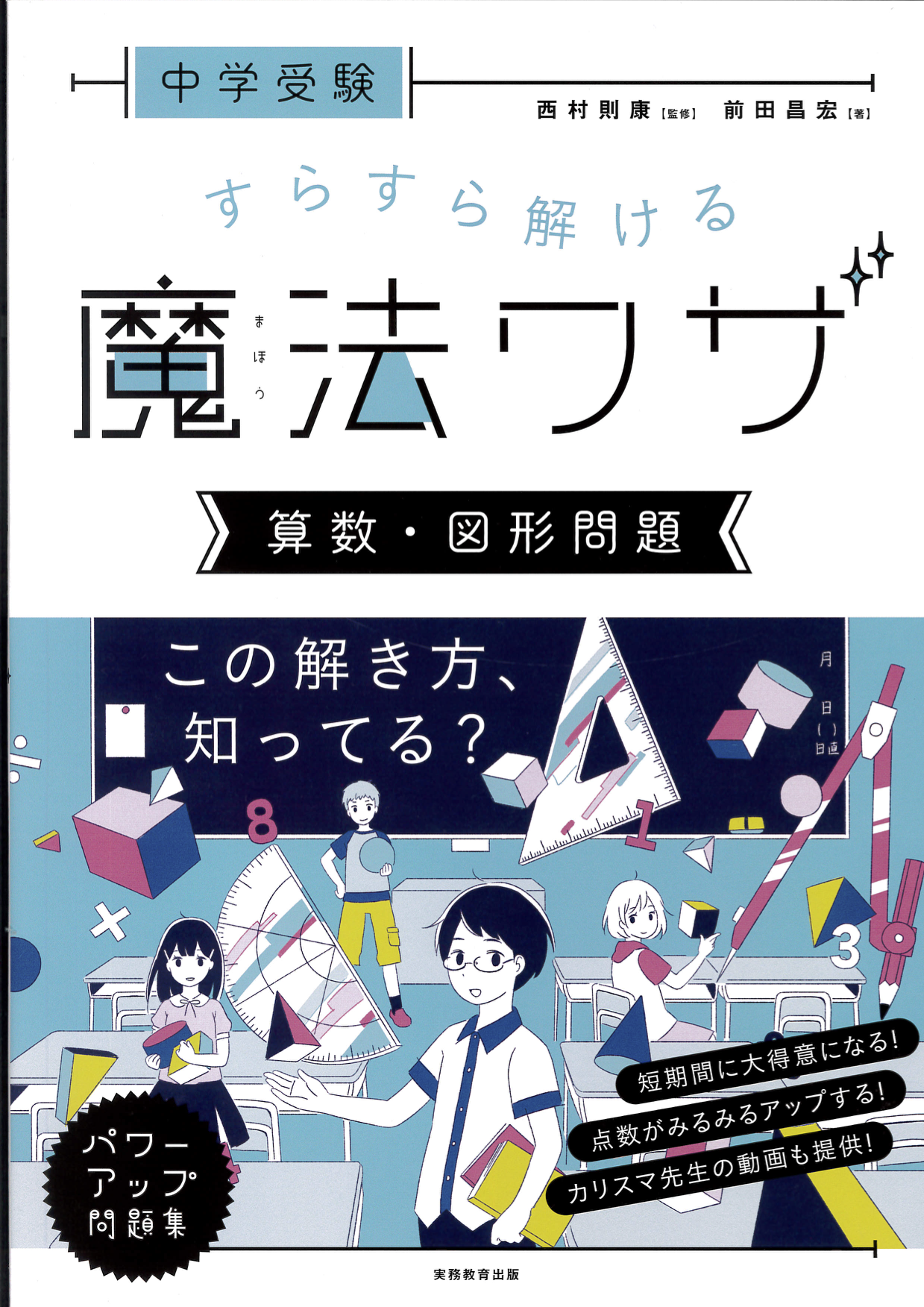目次
不合格だったお子さんへの声かけが「逆効果」になってしまうことも
お子さんに必要なのは「向き合うための静かな時間」
進学する学校こそが「お子さんにとってピッタリの学校」になるように
中学受験で得たいちばんの収穫は「学習習慣」
多くの中学校で、2025年度の入試・合格発表が終わりました。
首都圏の天気は概ね良好でしたが、一部では大雪になった地域もあり、ご本人も保護者の皆さんも大変だったのではないでしょうか。
皆さん本当にお疲れ様でした。
さて、今ご本人・保護者の皆さんは長かった受験生活や日々の課題・サポートから解放され、清々しい気持ちでお過ごしでしょうか。
それとも、何かしら後悔が残っていたり、進学先が未だ確定できずに落ち着かない気持ちでいらっしゃったりするでしょうか。
今日は、見事合格を手にされ受験を終えられたご家庭ではなく、残念ながら主な志望校に不合格であった生徒さんの保護者の皆さんに向けてお話ししたいと思います。
不合格だったお子さんへの声かけが「逆効果」になってしまうことも
お子さんが無事合格であった場合、今ごろは皆でお祝いをして、受験勉強のために返上したクリスマスやお正月に代わるのんびりした日々を満喫されているかと思います。
しかし、望まない結果と向き合うことになった場合はそうもいきませんよね。
落ち込んでいるお子さんをどのようにケアしてあげたら良いのか、この不合格を今後に最大限活かすために何が出来るのかと悩まれているご家庭も多いと思います。
まずお子さんへの声かけ・心のケアですが、大切なことはお子さん自身が現実を受け止めるための静かな時間をきちんと与えてあげることです。
例えば、不合格が発覚したとき、ご自身もショックのあまり、こんな発言をされてはいませんでしたでしょうか。
「頑張ったんだから良いじゃない!結果がすべてじゃないもの」
「落ち込んでいるの?ママはちっとも落ち込んでいないわよ。」
「さあ、切り替えて今日から高校受験に向けてがんばろう!」
「◯◯ちゃんもダメだったんだって。落ちたのはあなただけじゃないわよ」
「お母さんも残念だわ。やはり、夏休みにだらけていたものね。」
「(合格した)◯◯ちゃんに比べて勉強を頑張り始めたのが少し遅かったわね。」
「だから『安全校』も受けた方がいいと言ったじゃない!あなたが選んだ道なのだから仕方ないけれど。」
……などなど。
どれも保護者の方ご自身も気持ちのやり場がなかったり、ご本人を元気付けるために良かれと思ってかけたりした言葉だと思うのですが、これらは不合格という現実に直面した直後であるお子さんを追い込んでしまう発言です。
目の前の厳しい現実を、周りの人間からあらためて諭されたくないことは、ご自身が何か失敗してしまった時のことを想像されれば、大人の皆さんにも容易にご想像がつくと思います。
受験校の検討が甘かったこと、エンジンのかかるのが遅く合格レベルに達せなかったこと、落ちたのは本人だけではないこと、また気持ちを切り替えて頑張らなければならないこと……。
どれもこれも、ご本人も、もう痛いほど思い知っているのです。
お子さんに必要なのは「向き合うための静かな時間」
そこで、今は「お子さん自身が現実を受け止めるための静かな時間」をきちんと与えてあげることに徹しましょう。
必死に励ましの言葉を考えたり、元気づけようとした結果としてお説教のようになってしまったり、保護者の方ご自身が落ち込みを否定して明るく振る舞う必要はありませんし、それは逆効果になることが多いでしょう。
今はそっとお子さんの気持ちを思いやり、お子さん一人の時間を作ってあげてください。
二人三脚、もしくは三人四脚でここまで歩んできた皆さんの今のお気持ちは、何も言わずともお子さんに伝わります。
色々声をかけたいところをグッと我慢してあげる。
余計な声かけをせず静かに見守ってあげる。
このことこそがお子さんへの最大の優しさであり、不合格体験を今後に活かす大切なポイントだと思います。
不合格に直面した生徒さんは自分自身を静かに振り返る時間が出来て初めて、現実を受け止めることが出来ます。
そして、いずれ次の段階として「なぜ志望校に落ちたのか」「これから自分はどうして行くか」についても自分自身で考え始めることでしょう。
実際に、中学受験は合格だけが全てではありません。
この経験をお子さん自身がしっかりと受け止め振り返ることで、不合格体験からも合格体験以上の学びと成長の機会を得ることができ、それが今後の成功の礎となるのです。
進学する学校こそが「お子さんにとってピッタリの学校」になるように
そして、お子さんがある程度現実を受け入れ、自分自身の受験生活について振り返り、今後についても考えることが出来始めたら、ご本人が進学することになった学校について、ぜひ一緒に話してあげてください。
受験校選びを偏差値だけでしていなければ、皆さんの進学することになった学校は「ここは良い学校だな」もしくは「通っても良いな」と思えた学校のはずです。
中学受験で第1志望に合格出来るのはたった3割のお子さんで、殆どの場合は第2志望以下に進学します。
大切なのは、ここからどう伸びていくかです。
ですからお子さんが今回の受験を振り返っている間、保護者の皆さんはぜひお子さんが4月から通うことになった学校について良いところを改めて見直しておき、
「良い学校に決まって良かったね」
「ここはあなたの入りたい◯◯部の活動が盛んだから楽しみだね」
「家から20分で通えるから自由な時間がたくさん出来るね」
「タブレット端末を一人に一台貸与してくれるのよね。ICT教育に力を入れているから、あなたたちの時代にぴったりだね」
など、言葉にしてお子さんに伝えてあげて欲しいのです。
信頼する保護者の方の前向きな発言はお子さんの新生活へのモチベーションとなり、4月からの中学校生活をきっと楽しみにさせてくれることでしょう。
決して、「残念な学校へ通うぼく、わたし」というイメージで春を迎えることがありませんように。
中学受験で得たいちばんの収穫は「学習習慣」
これまでにも何度もお伝えしていますが、”全ての子どもにとって最も良い学校”などというものは存在しません。
“良い学校”とは、そこに通うお子さんにとって居心地が良く、日々前向きに楽しく勉学や部活に励むことができる環境が整っており、友人に恵まれた学校生活を送れる場所ではないでしょうか。
それは自分のモチベーションの持ちようによっても変わってきますし、実際に通ってみなければ分からないものです。
中学受験は合格を目標にやってきたのですから、もちろん第一志望合格こそが最高の結果であり、努力してきた皆さんへのご褒美といえます。
しかし、たとえ不合格となっても、その失敗体験からお子さんが多くを学び、自分自身を変革し、今後の人生に活かせれば、それは大きな「成功」となり得るのです。
もちろん全ての受験校に不合格となり公立中学に進学する人も、その良い点を見つけ、活かして欲しいと思います。
公立小学校に通う場合、家から近い分学習に費やせる時間は多くなりますし、教育費も私立進学よりずっと少なく済みますから、その分を今後の学習を支える塾代や家庭教師代に回すこともできるでしょう。
中学受験にチャレンジした生徒さんはそうでない生徒さんに比べ知識が豊富で学習習慣も身についています。
入学後もしっかり努力を続けていれば、公立中学で3年間トップクラスの成績を取り続け、大きな自信を得ることも出来るでしょうし、学校推薦の道が拓ける場合もありますね。
進学先には小学校の友達も数人いるでしょうから、初めのうちは特に心強いかもしれません。
指定区内から通いたい中学校を選べる「学校選択制」が利用できる地域もありますから、その場合はよくホームページなどを確認し、お子さんにあった中学校を一緒に選んであげてくださいね。
どんな結果であれ、受験生の皆さんが与えられた現実をしっかりと受け止め、この経験を人生の財産として活かし、いっそう輝いていけることを、心から願っています。

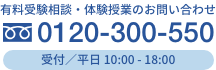


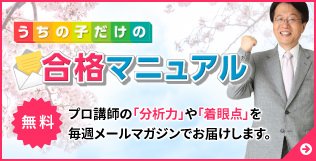



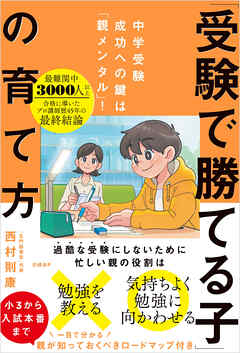
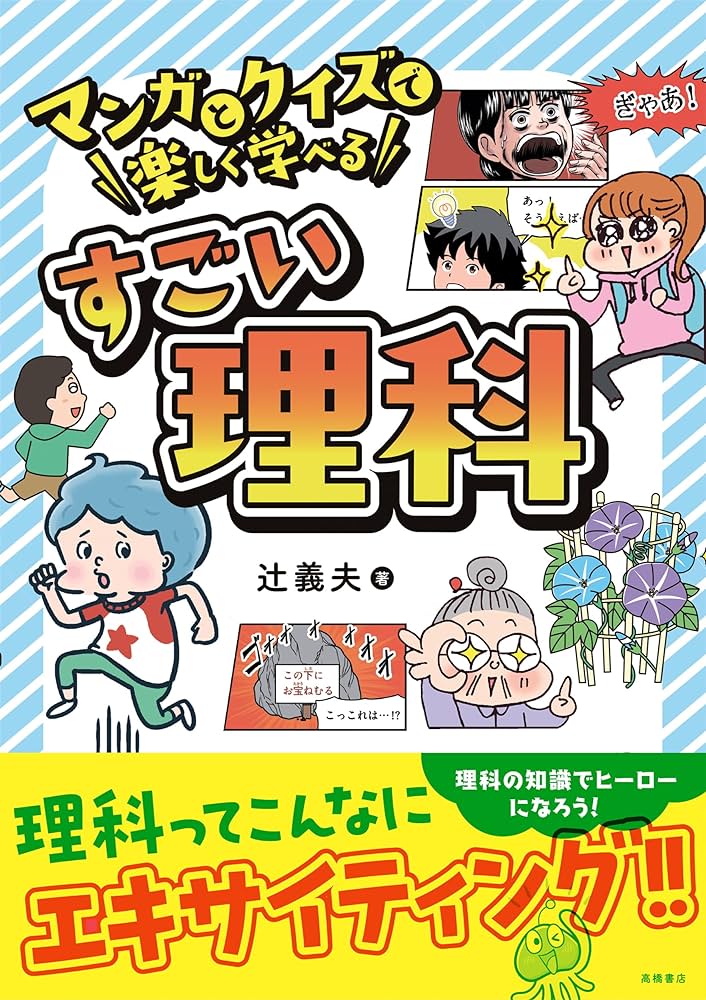
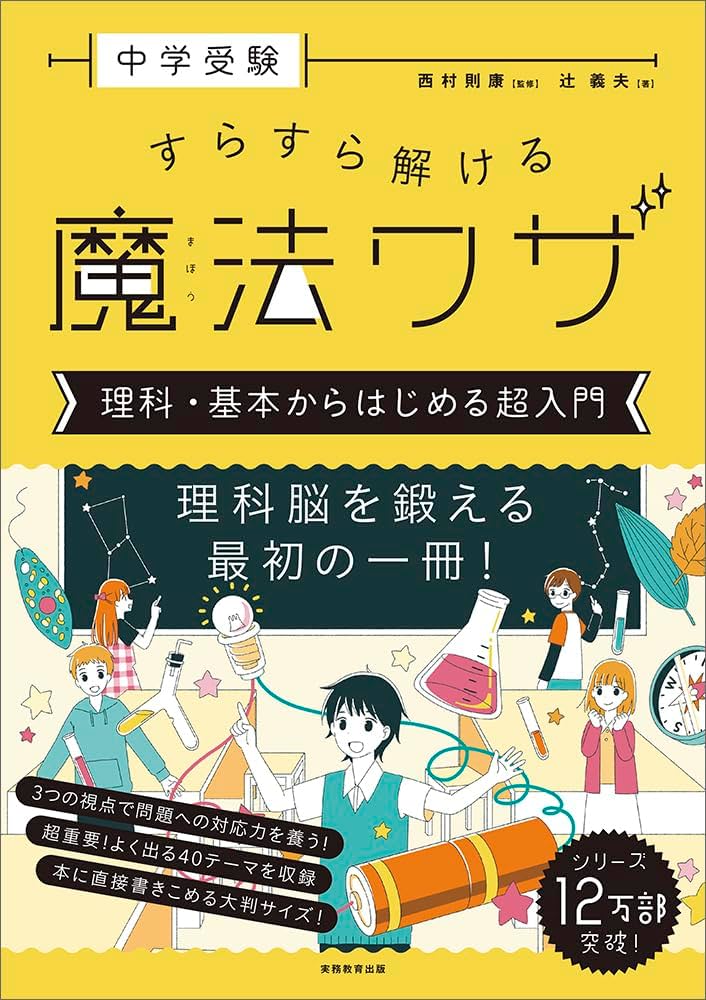
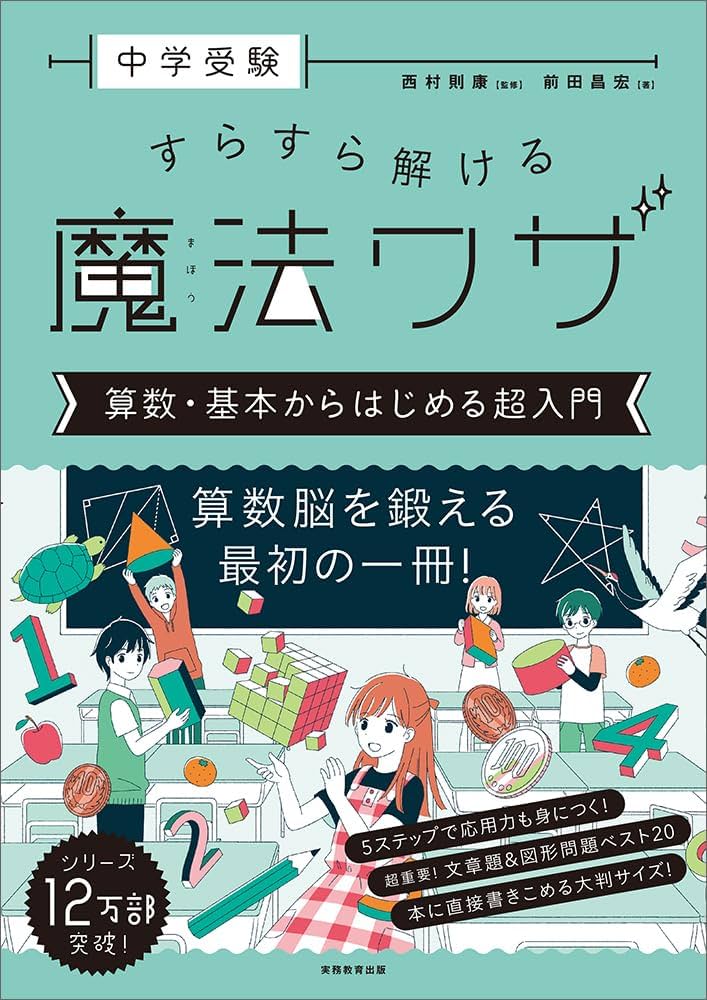
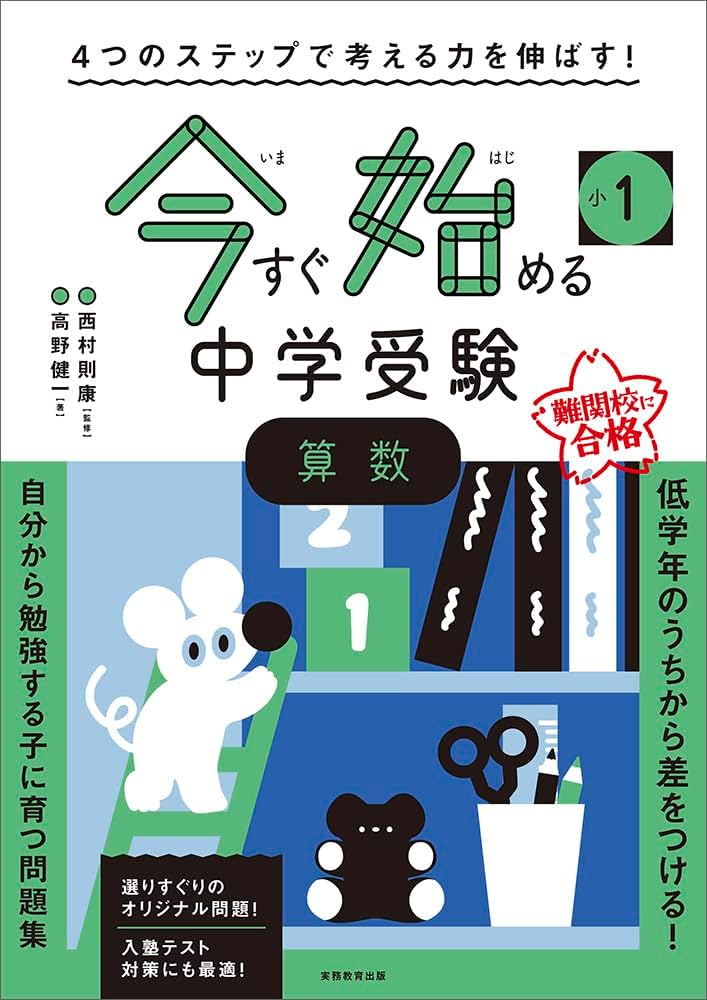
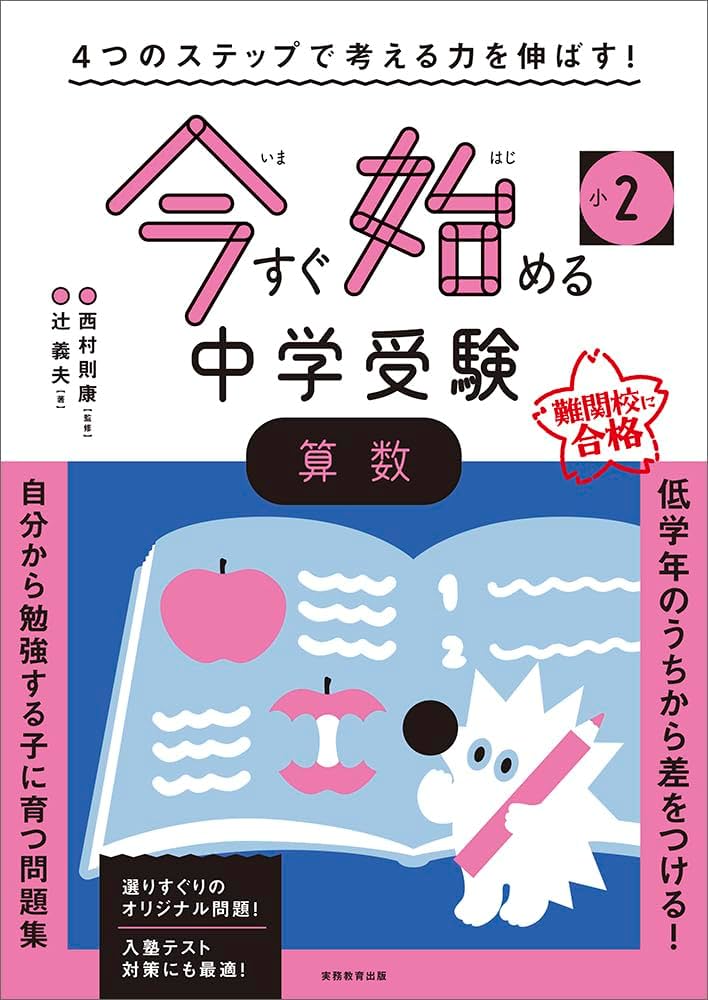
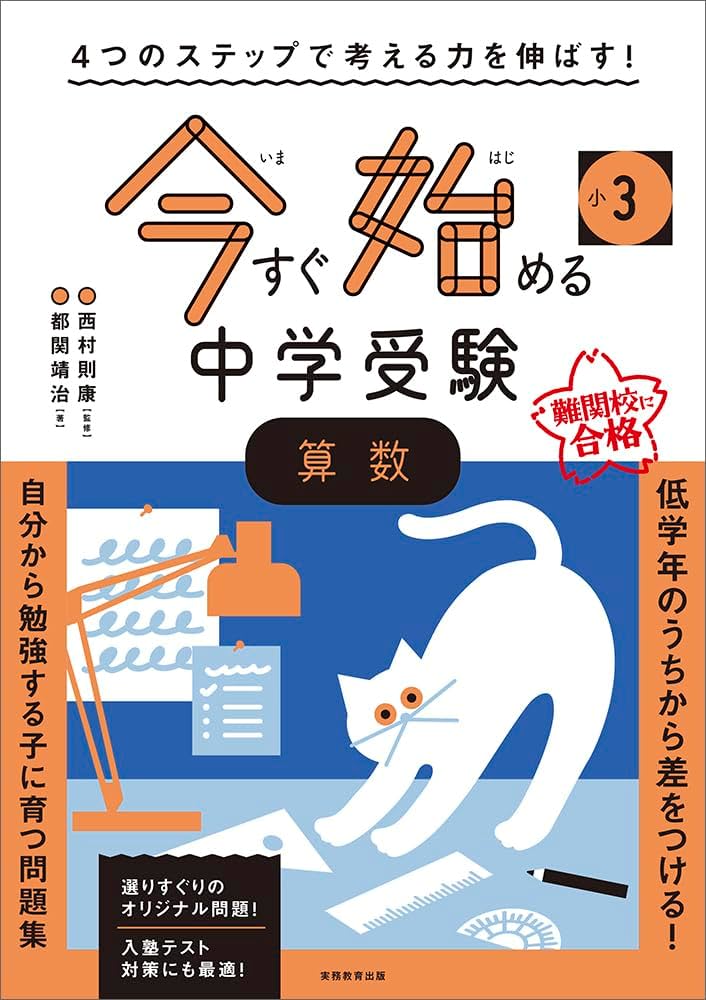
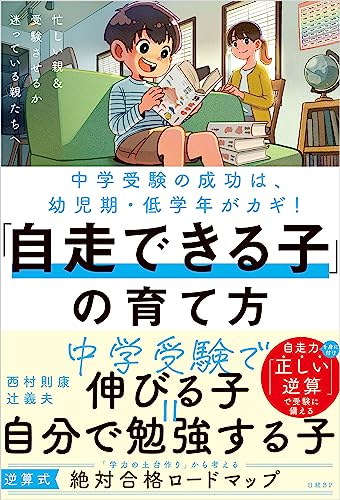
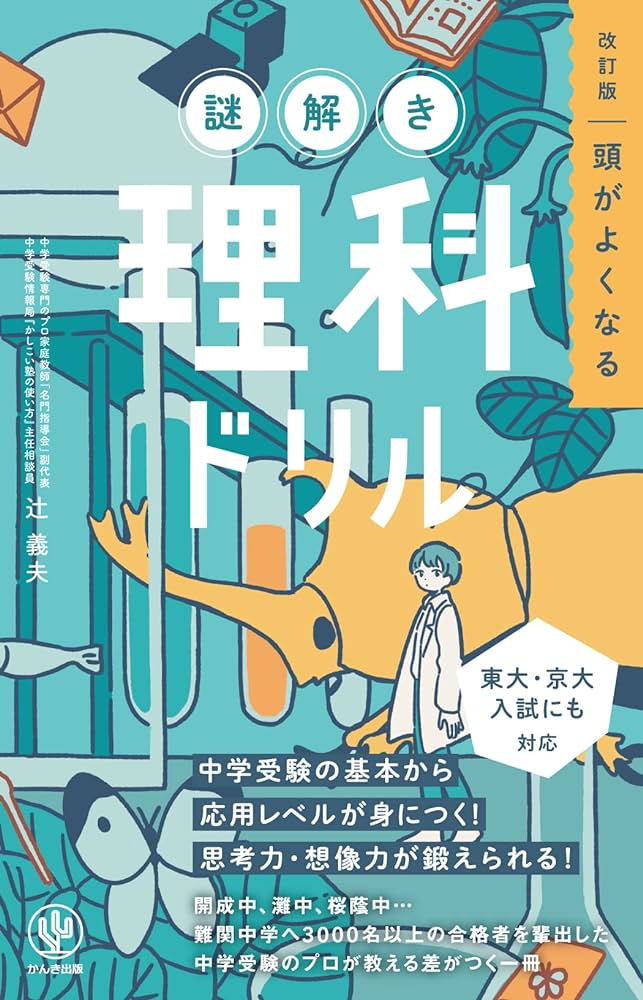
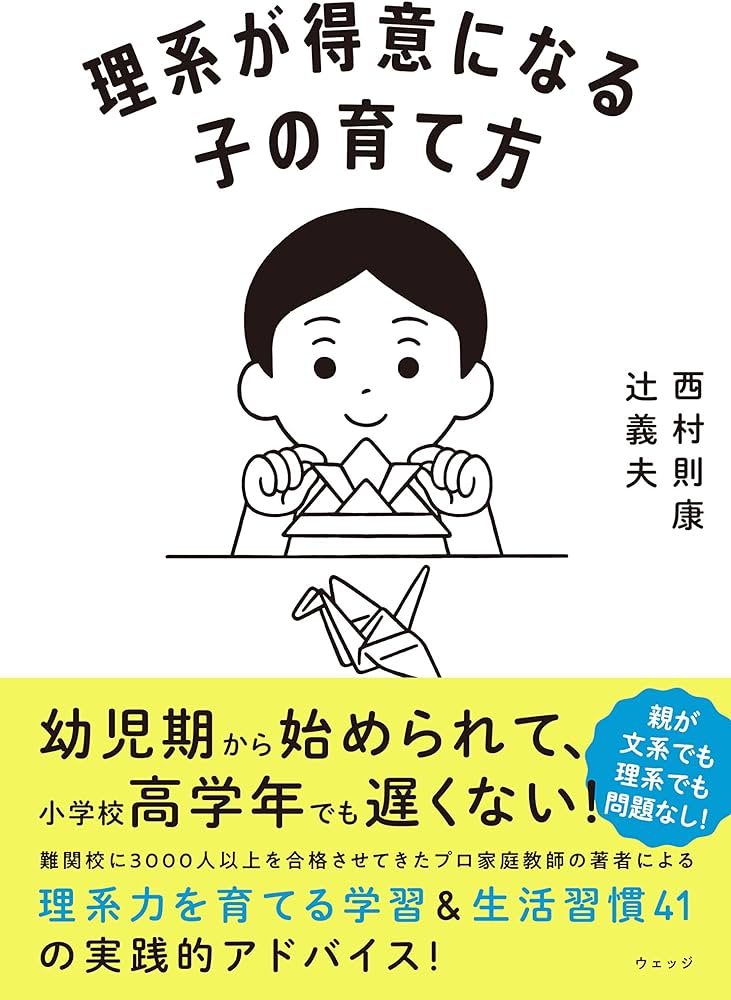

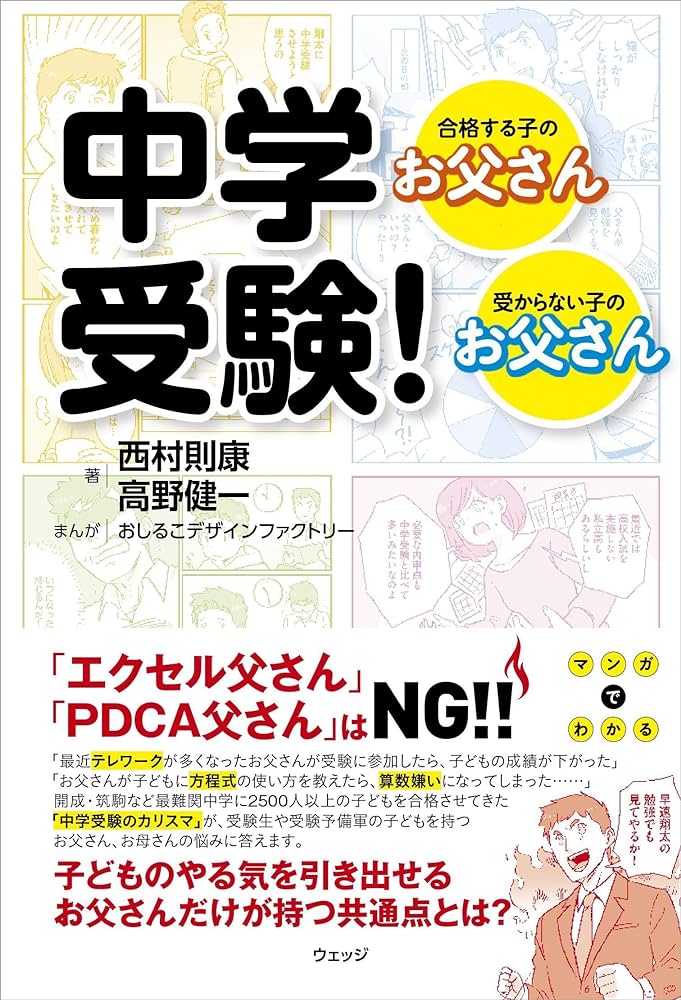
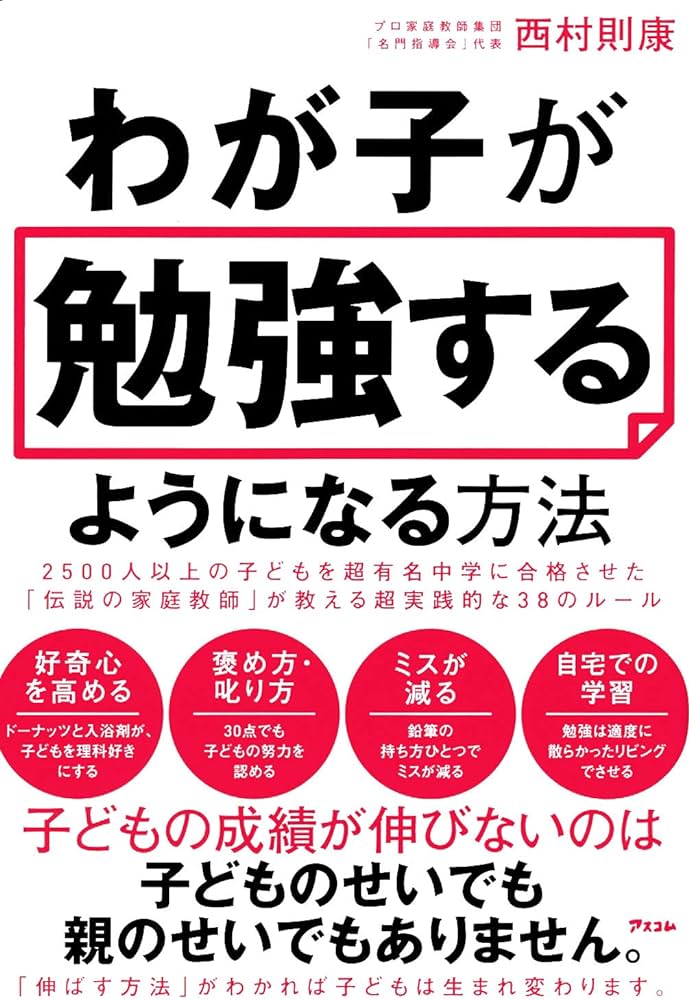
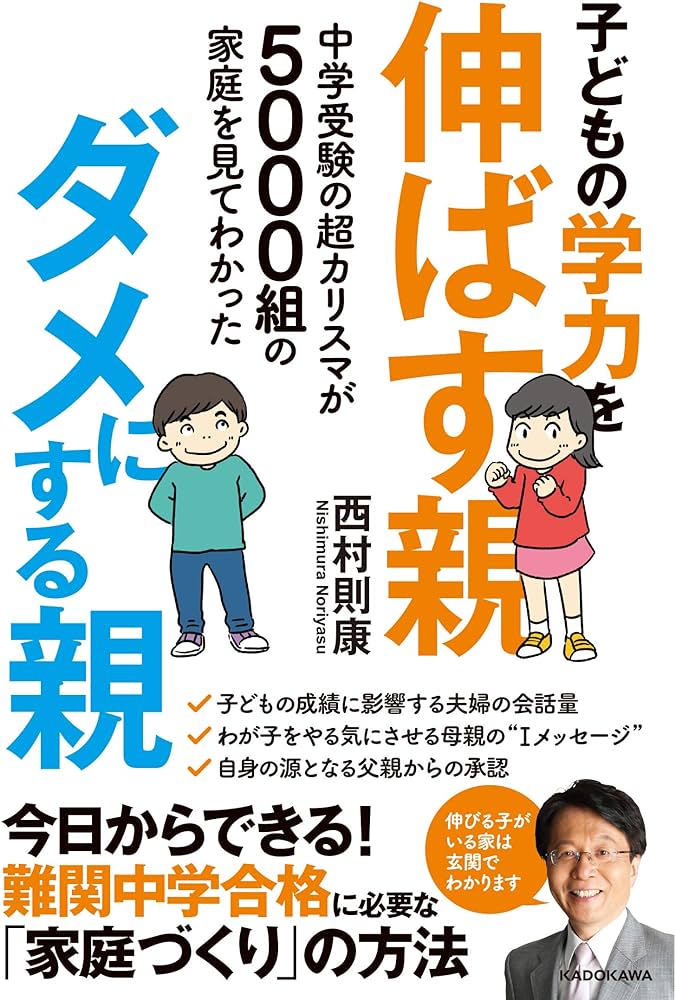
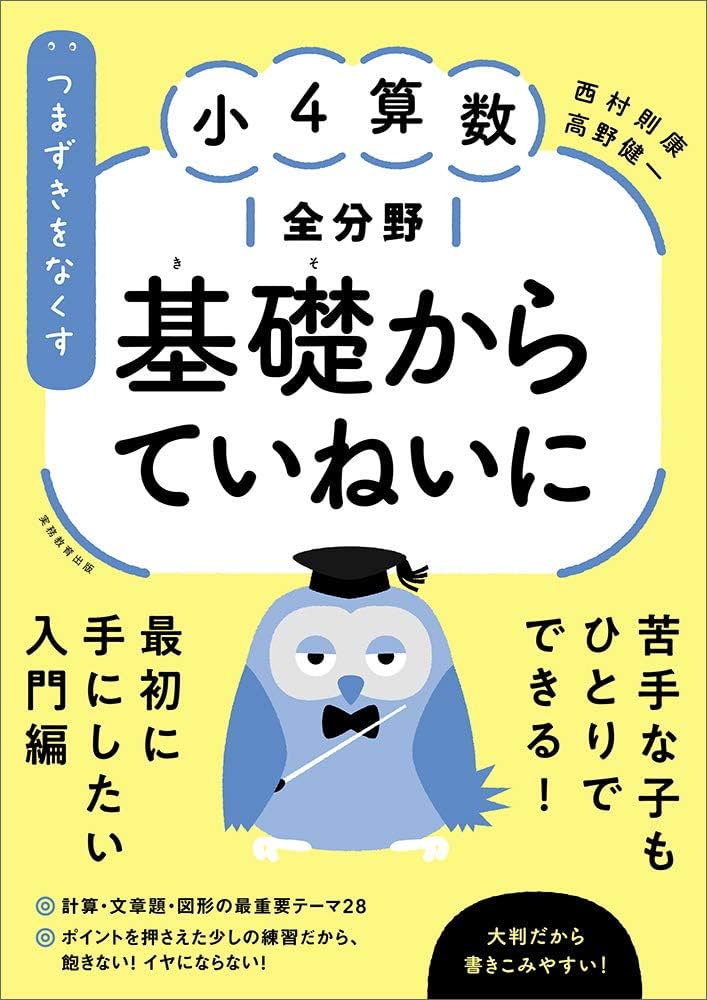
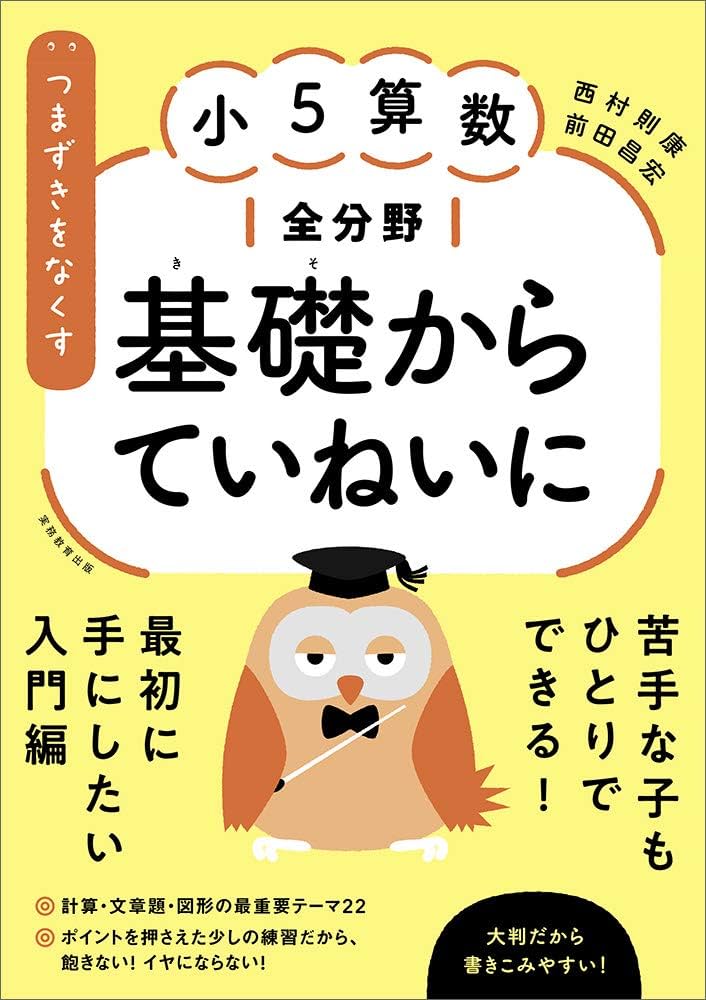
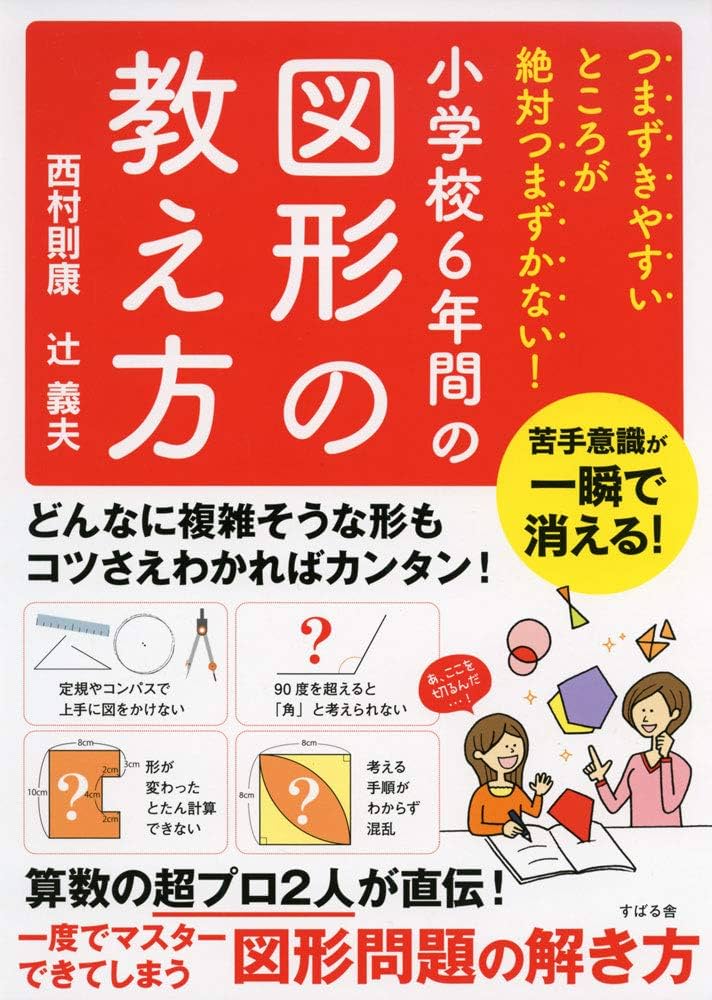
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[算数]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushsansu.jpg)
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[国語]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushkokugo.jpg)