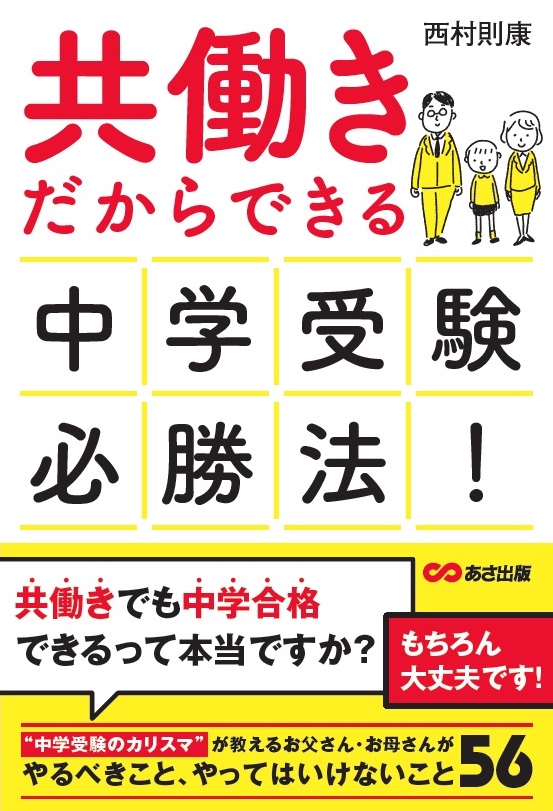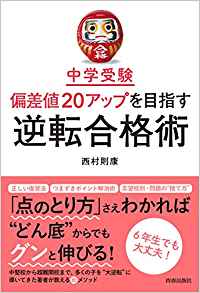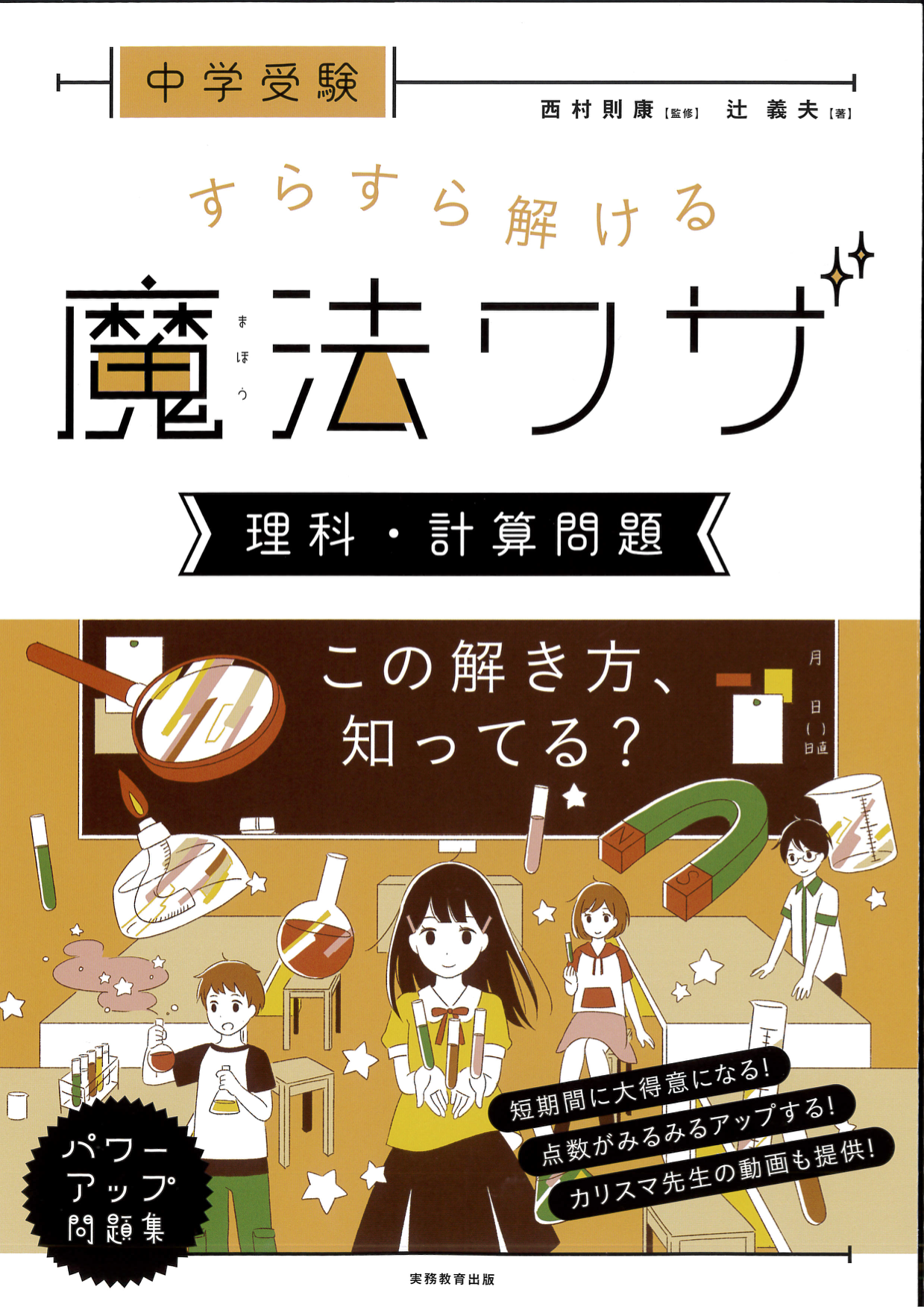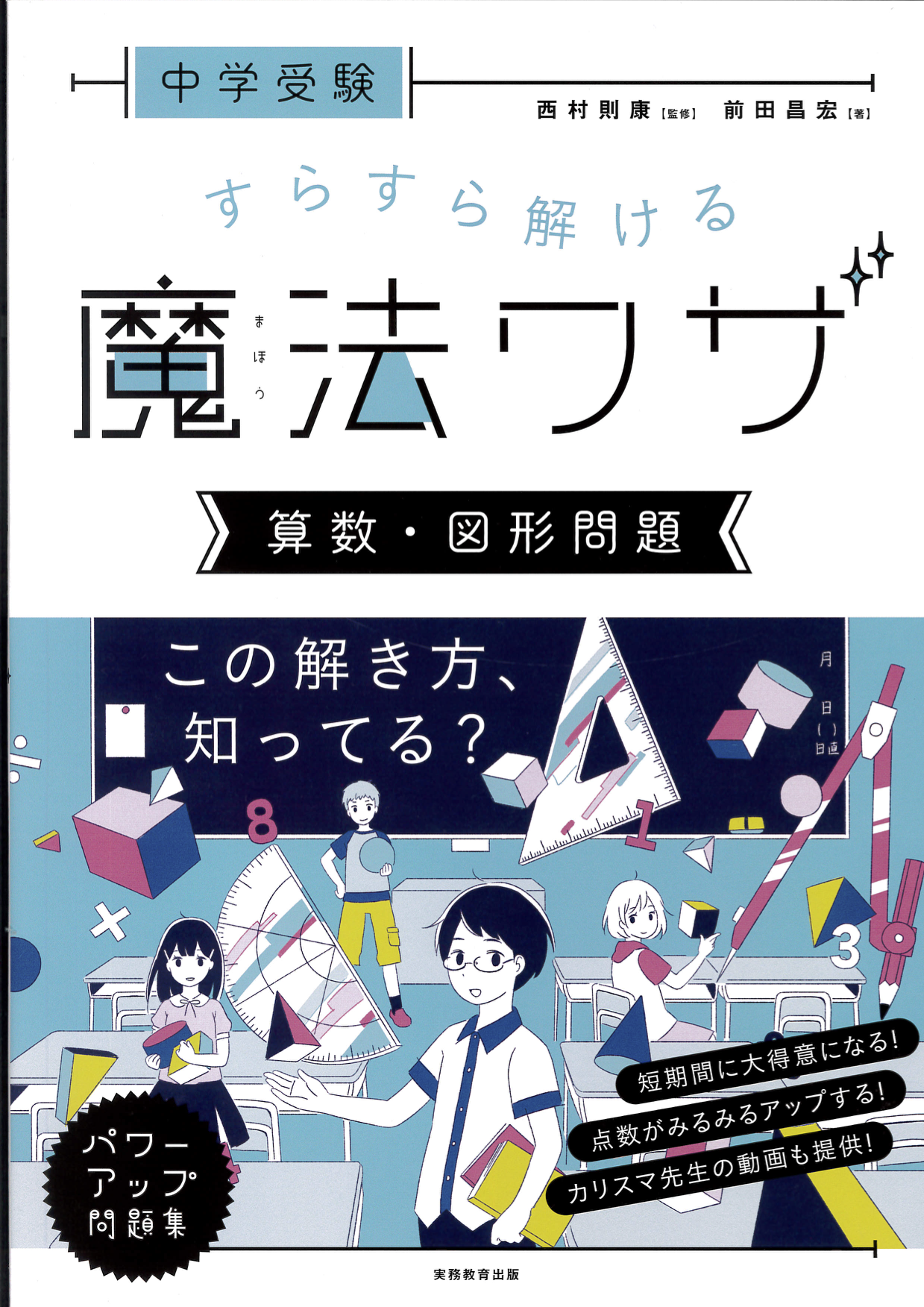目次
中学受験における3月の位置づけは
トライアンドエラーでペースをつかもう
前回のコラムでは、春休みが「自分の弱点をじっくり対策できる」大きなチャンスであること、そして、春休み攻略の決め手である「春期講習を受講する・しないの判断」についてお伝えしました。
春期講習は必ずしも受講する必要はなく、場合によっては「見送った方が成績が上がることがある」事実や、お伝えした「受講する・しない」の判断材料についてもぜひ参考にしていただき、皆さんそれぞれに最適な選択をしていただけたらと思います。
中学受験における3月の位置づけは
さて、今回はそのような春休みを含む今の時期が、中学受験全体においてどのような位置付けにあるのか、学年ごとにお話ししたいと思います。
3月/各学年の位置付け・学習に必要な力
進学塾での4年生の今頃は、受験勉強の慣らし運転にあたる時期です。
週に2回程度、学校の後に塾に通い、家でも毎日勉強する事を「ルーティン」にしていき、塾では、授業の聞き方を練習、体得していきます。
授業では先生が話をしている時はノートをとる手を止めて前を向き、顔を見ながら聞くこと。
塾通いのある生活習慣と、塾での授業の聞き方という基礎を身につけていくことが大切な時期です。
通学塾での5年生の今頃は、どの科目も基礎を土台にした応用問題や難問が増えてくるタイミングです。
授業時間や課題も増えますが、スケジュールの工夫と課題の取捨選択により上手くこなしていけるように調整していきます。
一般的な進学塾では、5年生の中盤までに、入試で必要な内容のほとんどを習ってしまいます。
つまり、6年生はもはやこれまで習ったことの総復習と入試対策・演習の時期であり、ほぼすべて(社会科の公民分野以外)はすでに習ったこととして授業が進んでいってしまうので、5年生の今頃までに、しっかり毎週の課題をうまくこなしていける学習方法やルーティンを体得しておきましょう。
ただし、課題をこなすことだけが目的になり、全てが「やっつけ」になってしまわないように気をつけてくださいね。
そのために大切なのが、意識的に「スピーディーな学習」と「スローな学習」の使い分けです。
「スピーディーな学習」は、ドリル的な計算練習や漢字練習など、短時間でスピーディーにこなしたい勉強を指します。
朝の隙間時間に入れ込むなど工夫して、短時間で集中して済ませることを習慣づけましょう。
「スローな学習」は、授業内容が「本当に分かっているか」を確認したり、「どうしてその解き方で解けるのか」を深く理解しながら、習ったことをしっかりと定着させたりする際の、じっくり考えながら行う学習方法です。
5年生で「スピーディーな学習」と「「スローな学習」」を上手に使い分けられるようになると、6年生の学習もうまく回っていきますよ。
進学塾での6年生の今頃は、志望校を具体的に検討するタイミングです。
科目によってはそれらの学校の過去問に取り掛かかったり、入試に向け本格的にアプローチをし始めたりする期間です。
(ただし、志望校の国語の過去問にはまだ手をつけないでください。お試しで10年前のものなどをやってみるのは構いませんが、国語は文章内容を覚えてしまうため、初見でないと実力が正しく確認できません。近い年度のものは力が十分につき、機が熟す夏以降に取っておきましょう。)
志望校については、まだまだ今の時期は「ここがいいかな」「この辺りのレベルかな」というようなぼんやりしたイメージで大丈夫ですよ。
最終的にきちんと決定するのは11月くらいでも遅くありませんから、あくまでも学習に向かうモチベーションアップのための作業と考えてくださいね。
6年生ともなると、授業の難度はさらに高く、勉強量も多くなります。
効率良く身になる学習をするためには「スケジュール作り」が鍵となるので、できることなら中学受験の指導経験が豊富な先生とお子さん、保護者の方がそろって(小学校のスケジュール等もよく確認しつつ)しっかり話し合いながらスケジュールを立てていきましょう。
トライアンドエラーでペースをつかもう
以上が、中学受験全体における3月の各学年の位置付けです。
学習スケジュールは、一度で完璧なものを作ることなど誰にもできません。
恐れずに、この時期にたくさんトライアンドエラーを繰り返し、だんだんとご家庭、ご本人にあったやり方、ペースを掴んでいきましょう。
一週間の中で「生活上、絶対に必要なもの」(睡眠や食事、お風呂など)を書き出し、残りの時間の中で「勉強に使える時間」を考えていくとやりやすいのですが、その時、ついつい張り切って詰め込みたくなる気持ちを抑えて、初めは「欲張りすぎない」ことがうまくいくポイントです。
3月はどの学年も、学習スケジュールのいわば「試用期間」です。
色々試して検証し、うまくいった部分は採用、行かない部分はまた相談して修正しながら、それぞれに無理なく前向きに取り組めるルーティンを見つけてくださいね。
皆さんの3月後半が、4月以降のより良い学習に向けた実り多き時間になるよう、心から願っています。

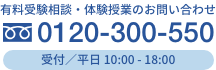


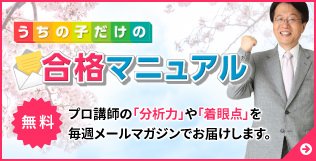



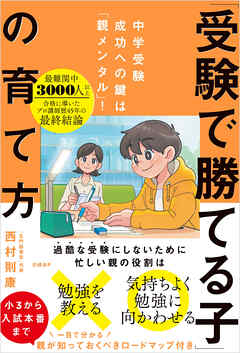
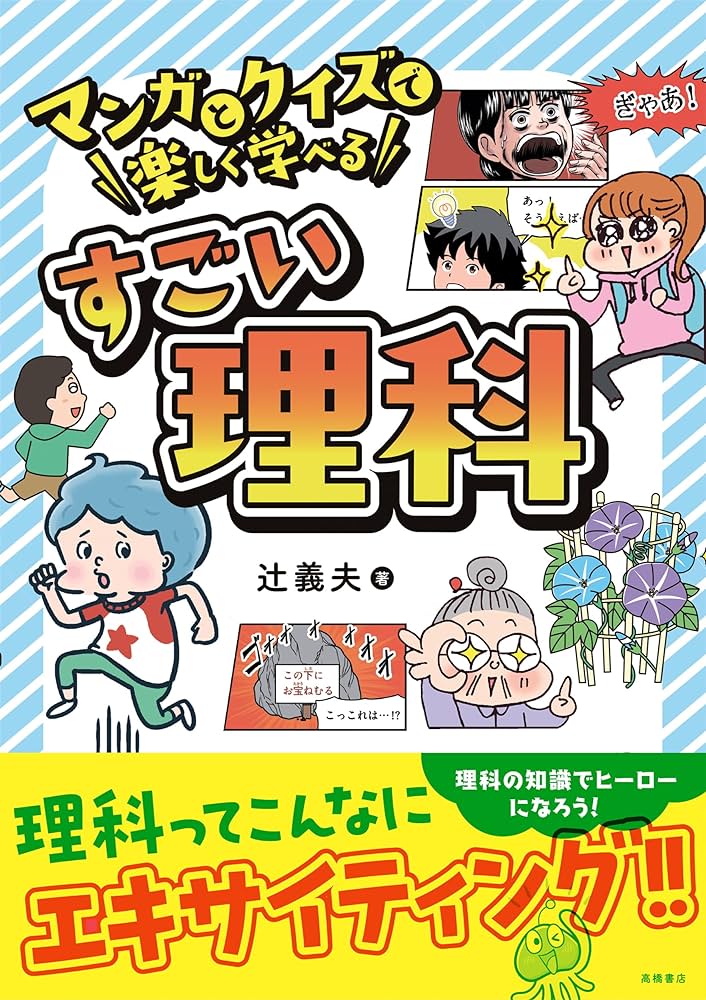
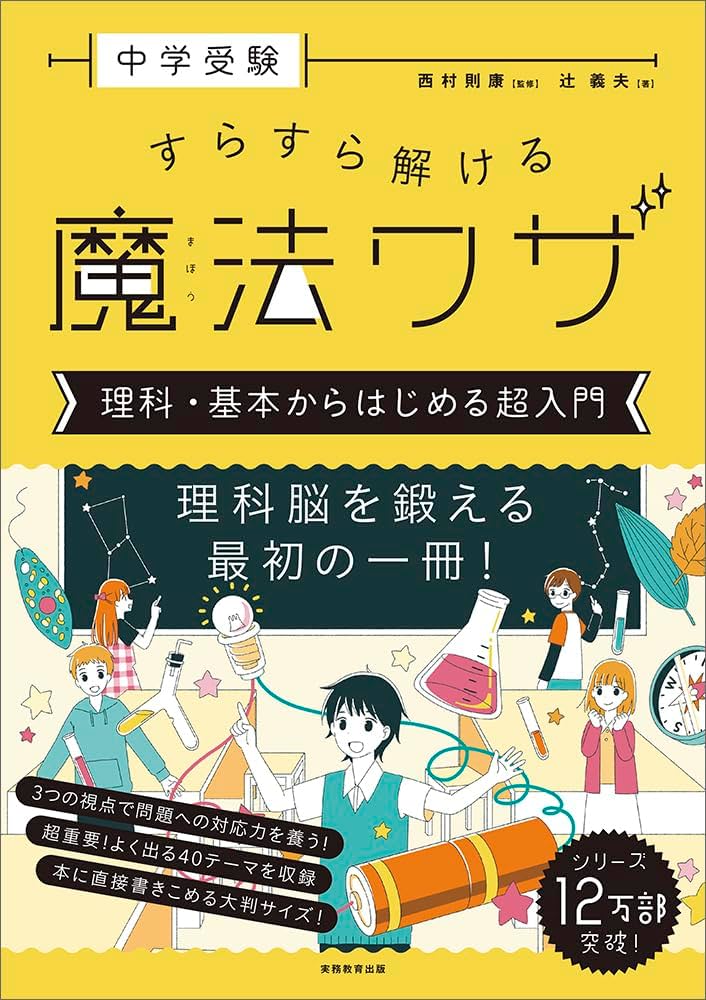
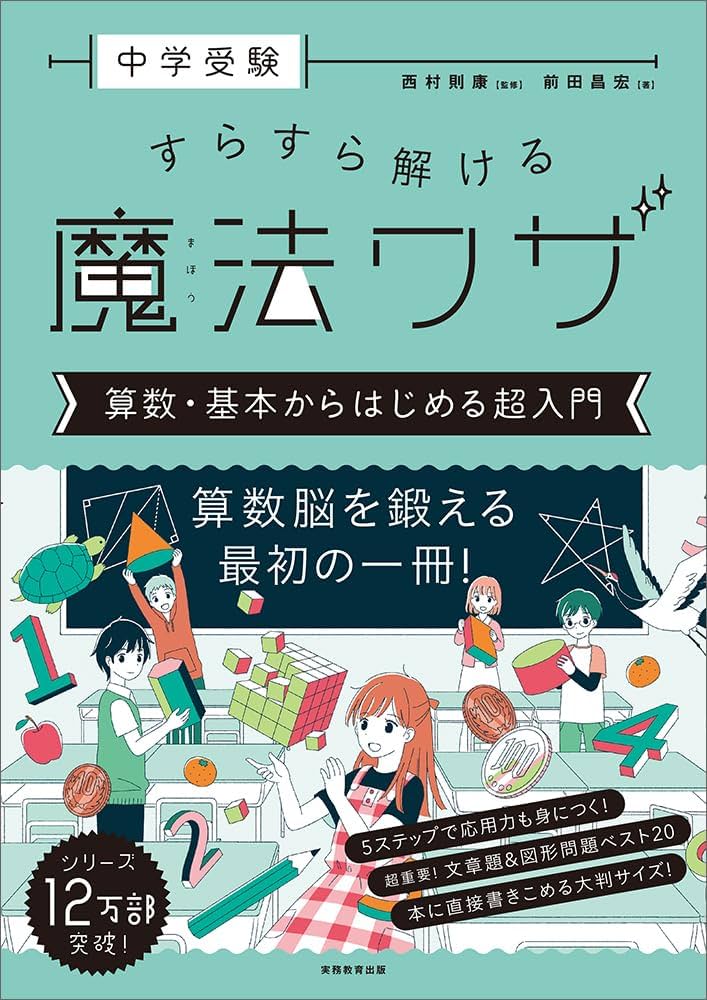
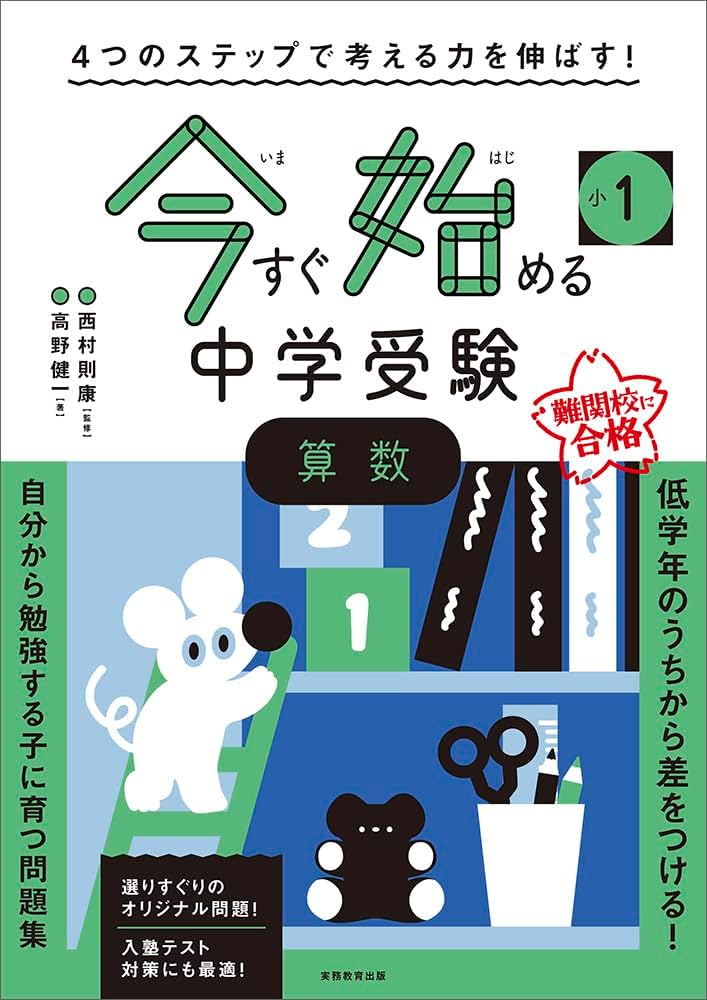
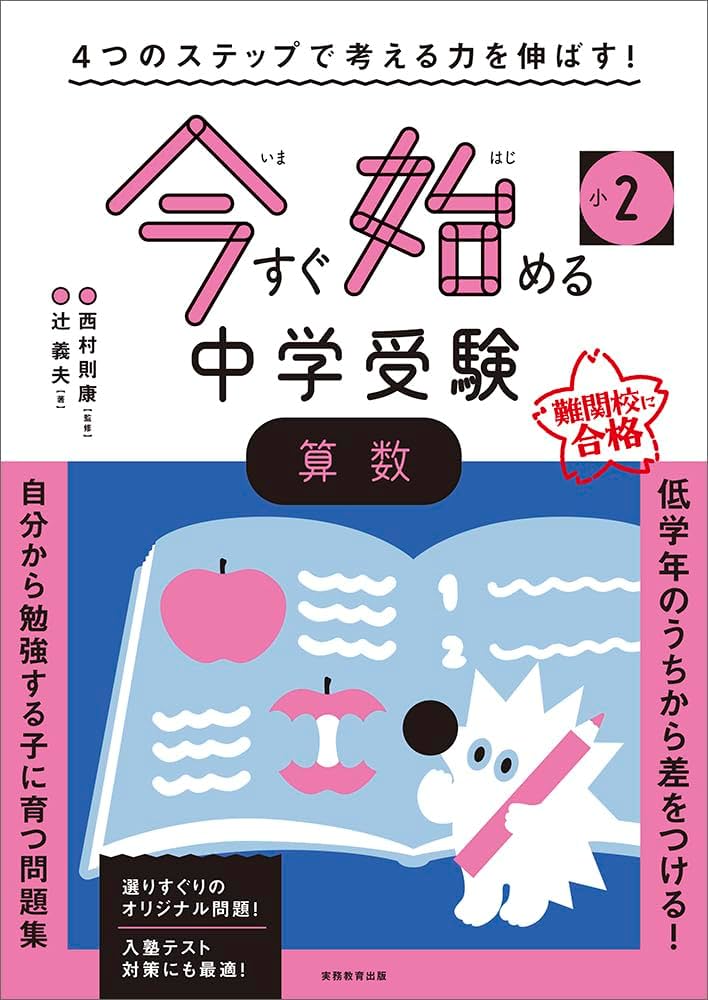
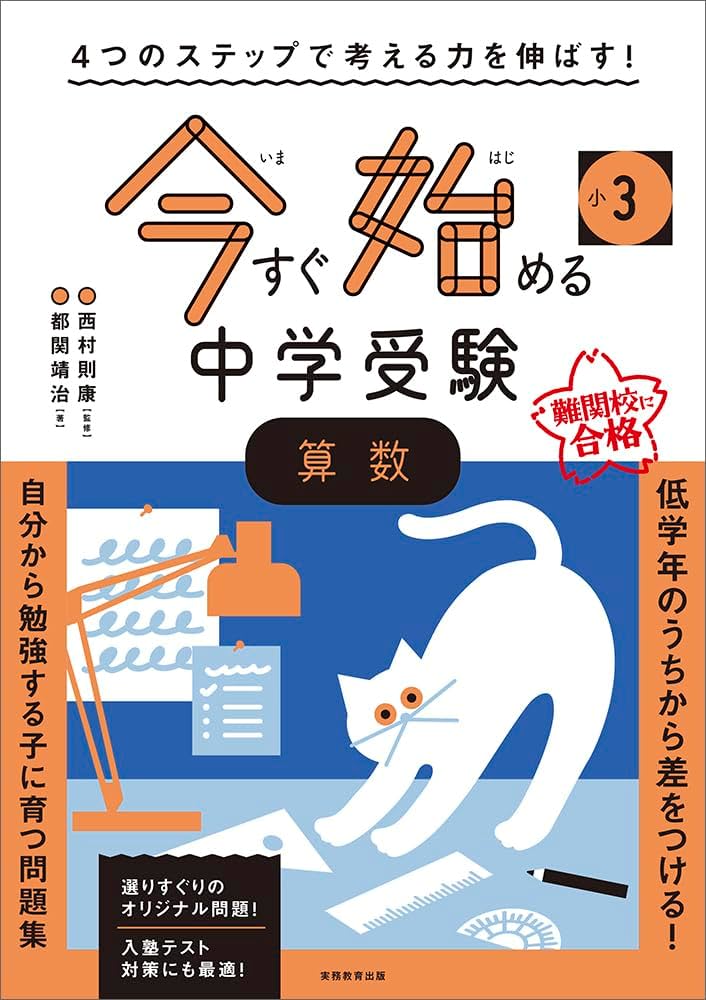
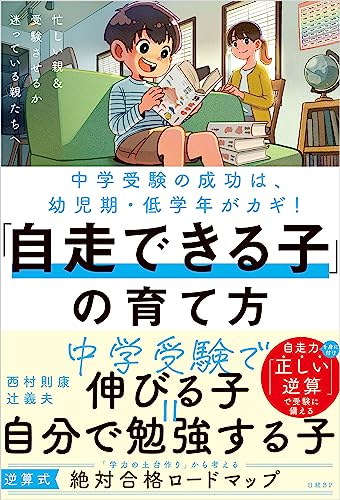
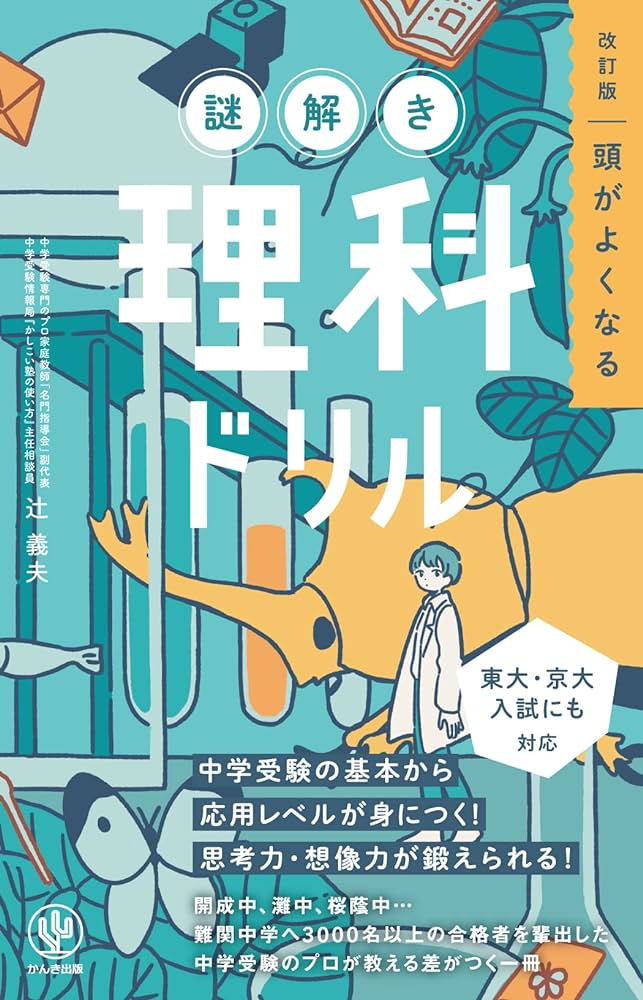
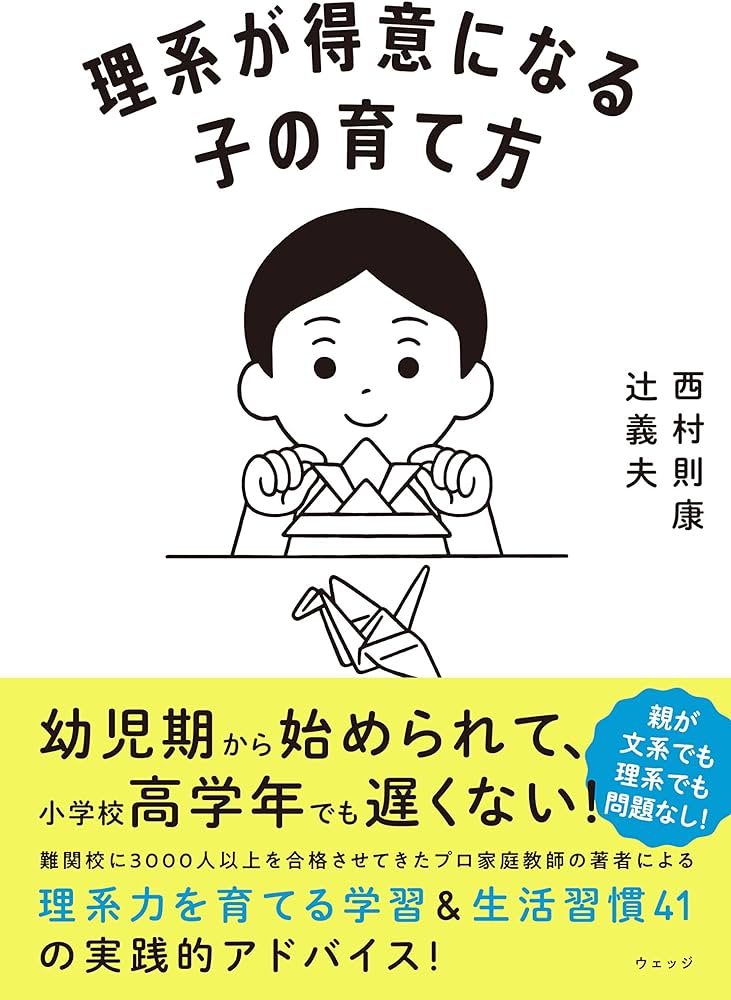

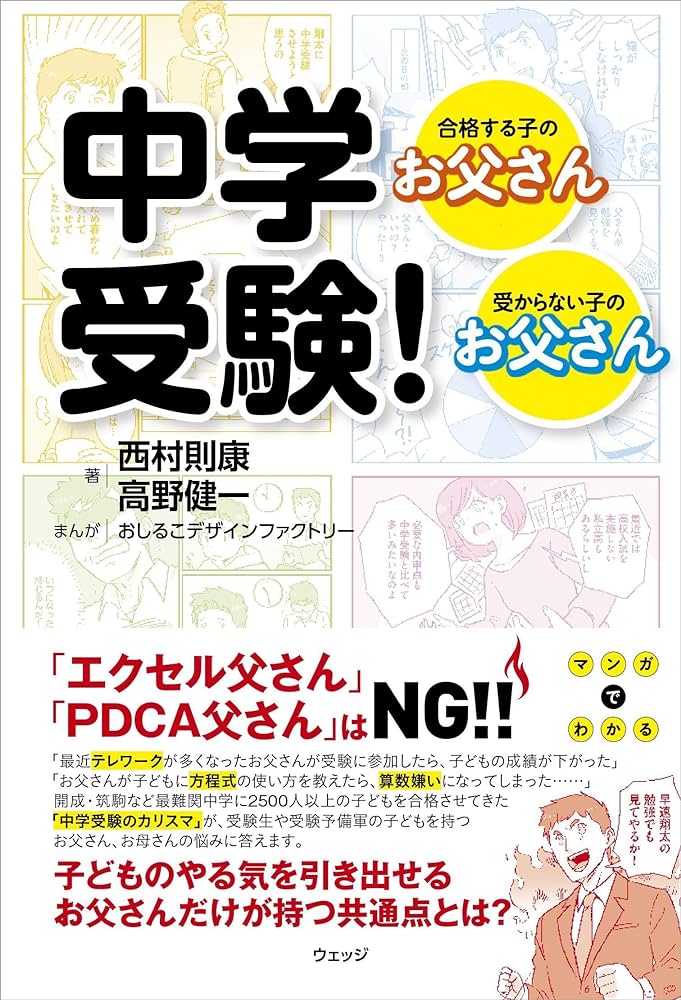
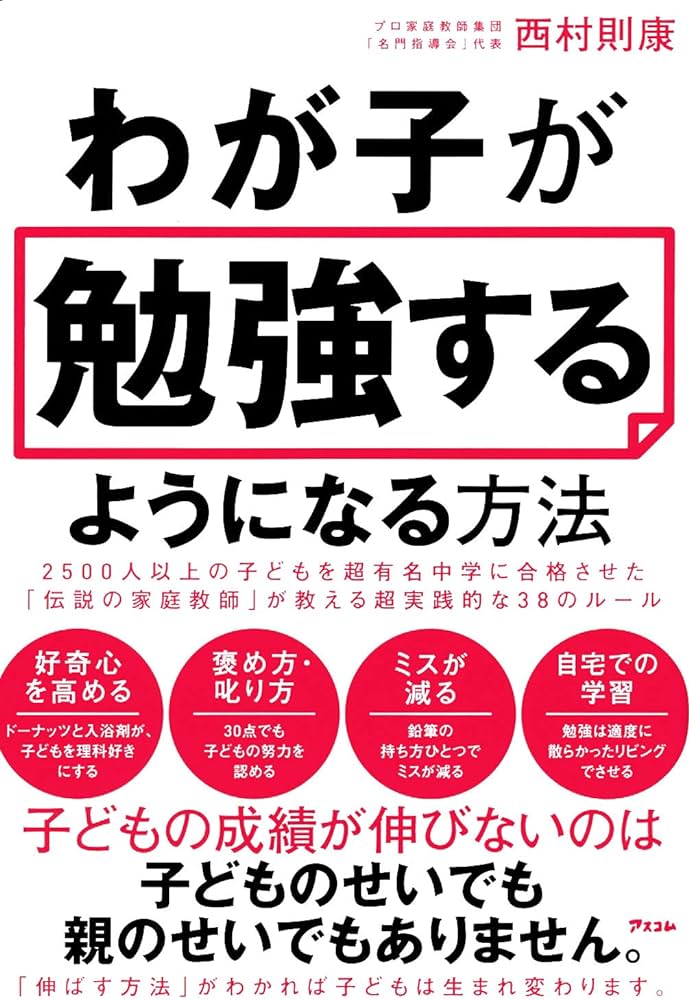
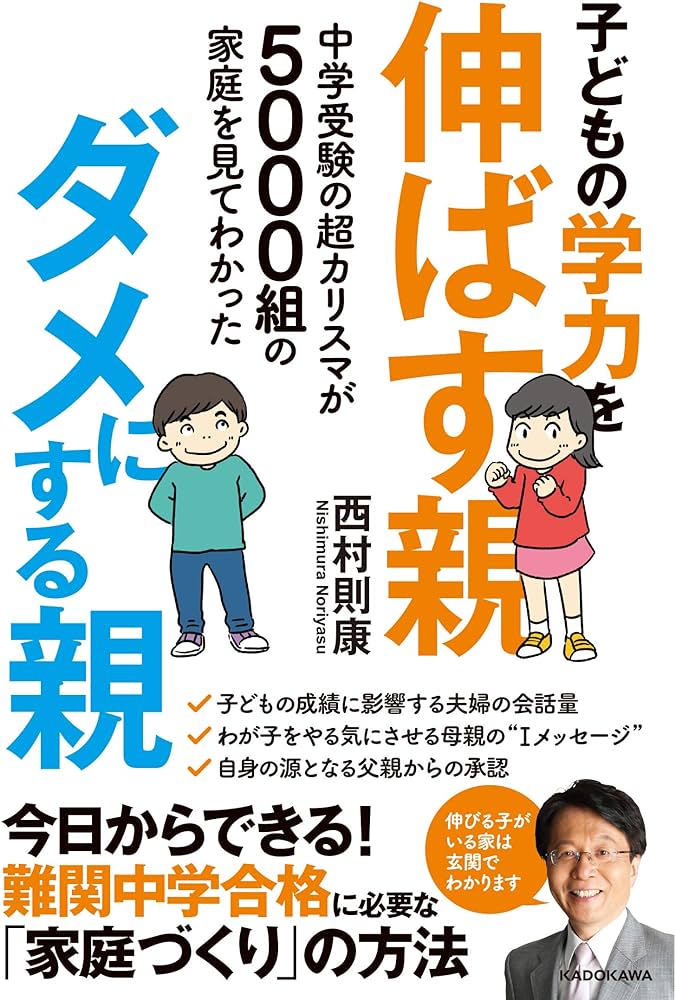
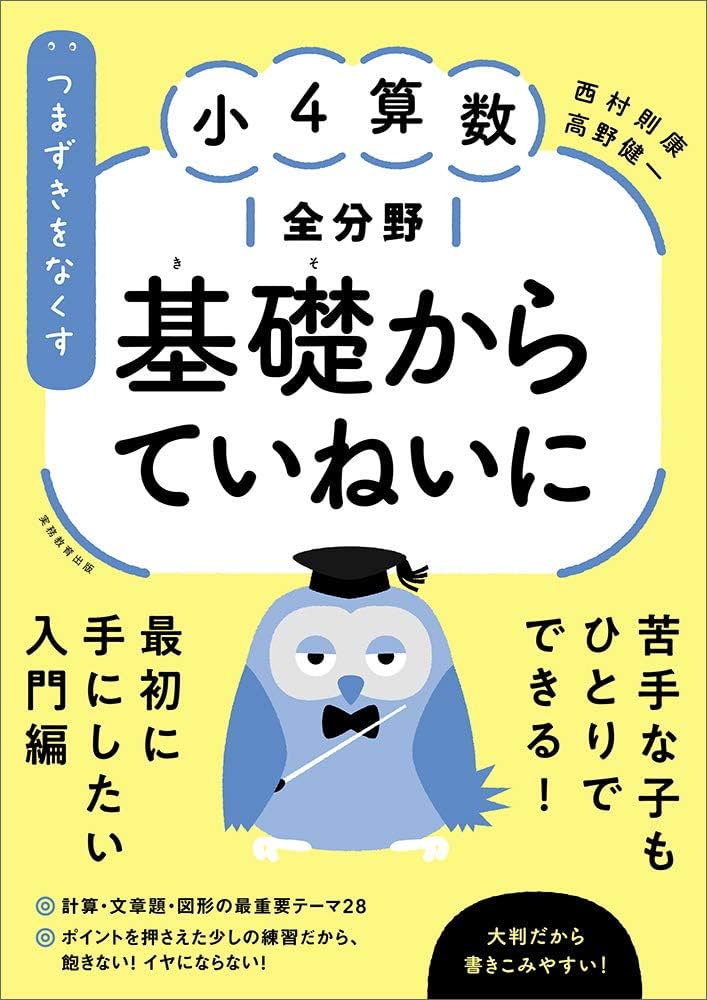
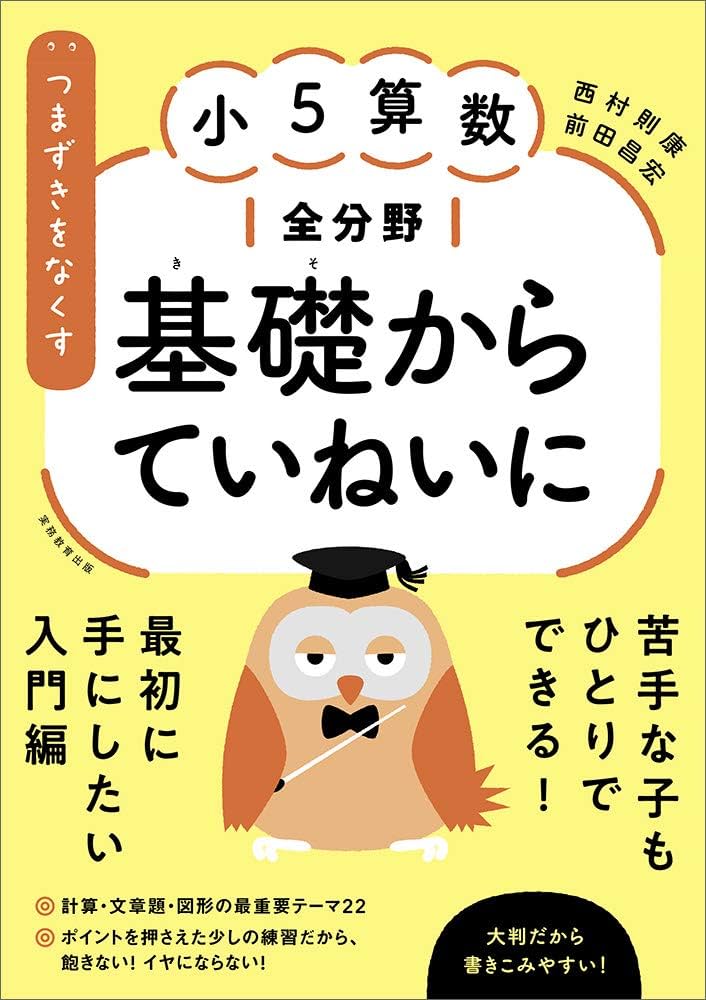
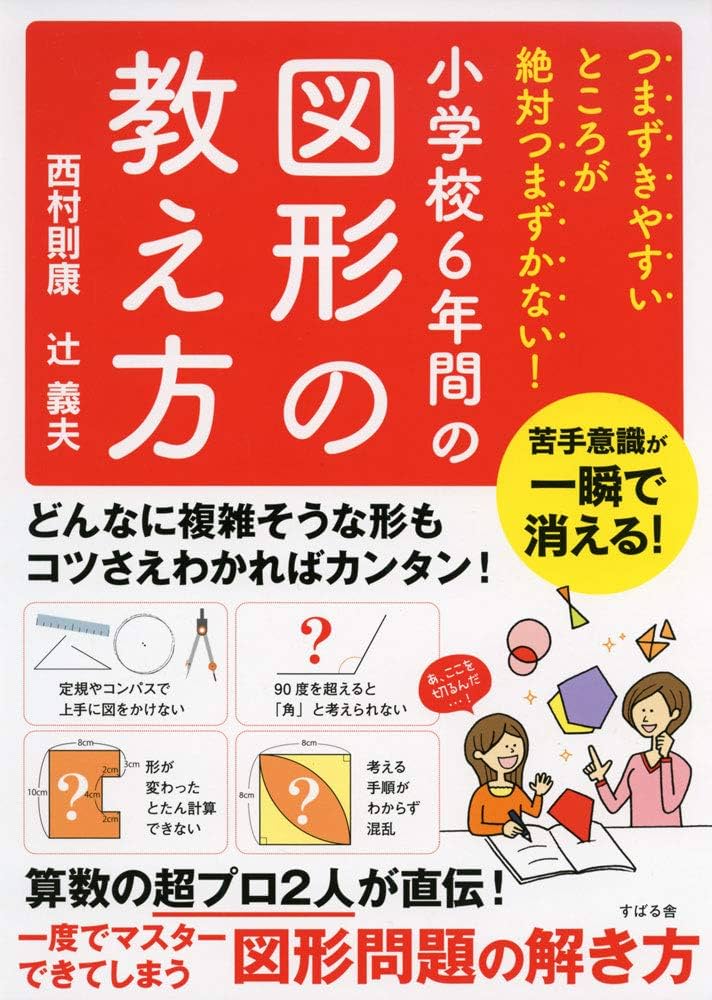
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[算数]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushsansu.jpg)
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[国語]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushkokugo.jpg)