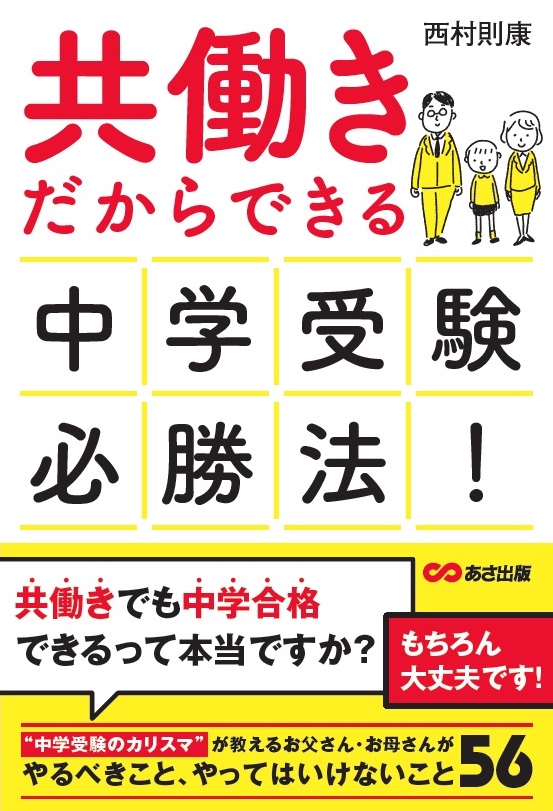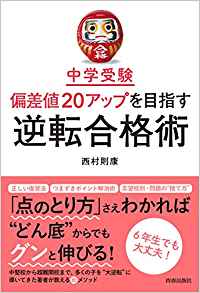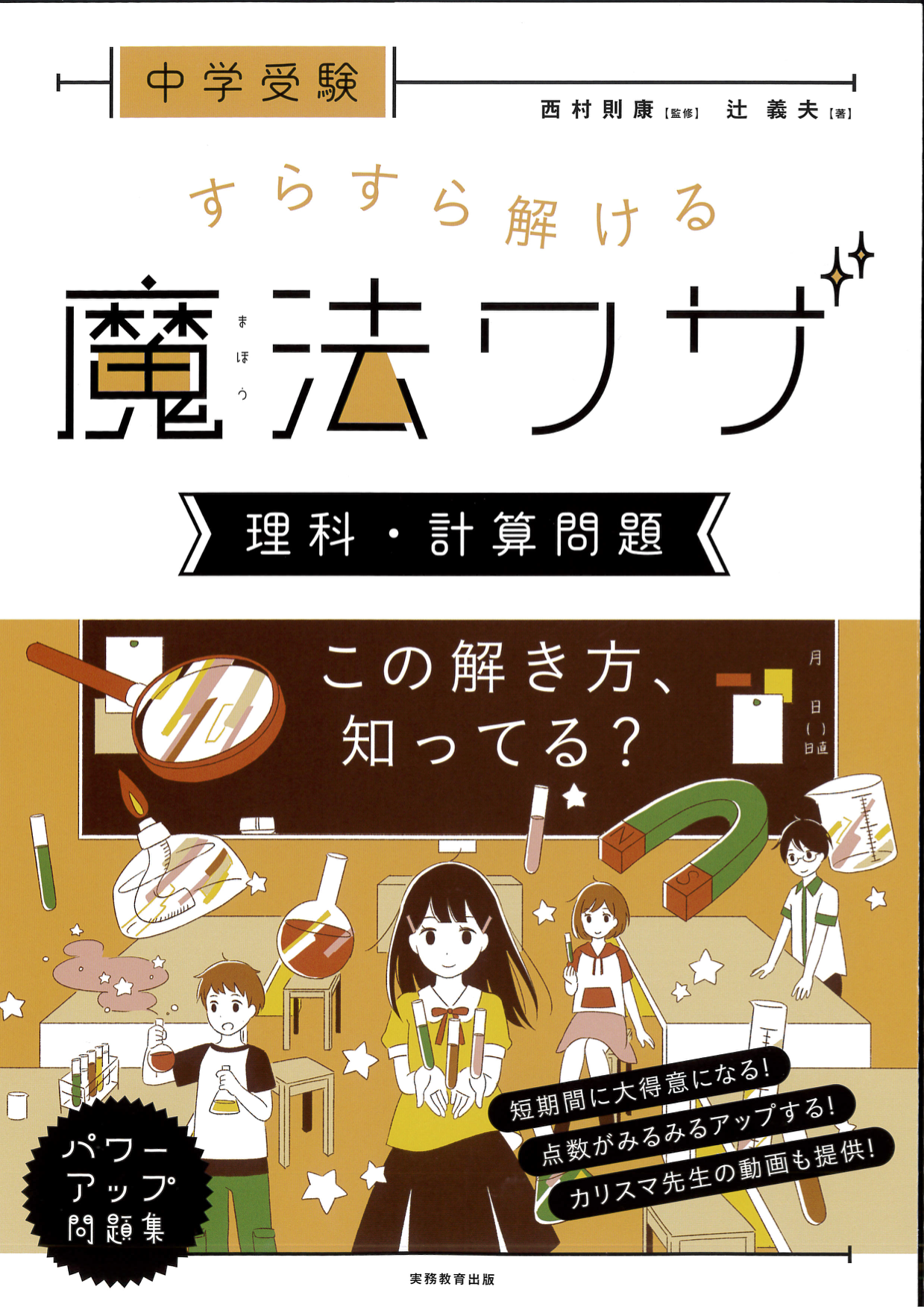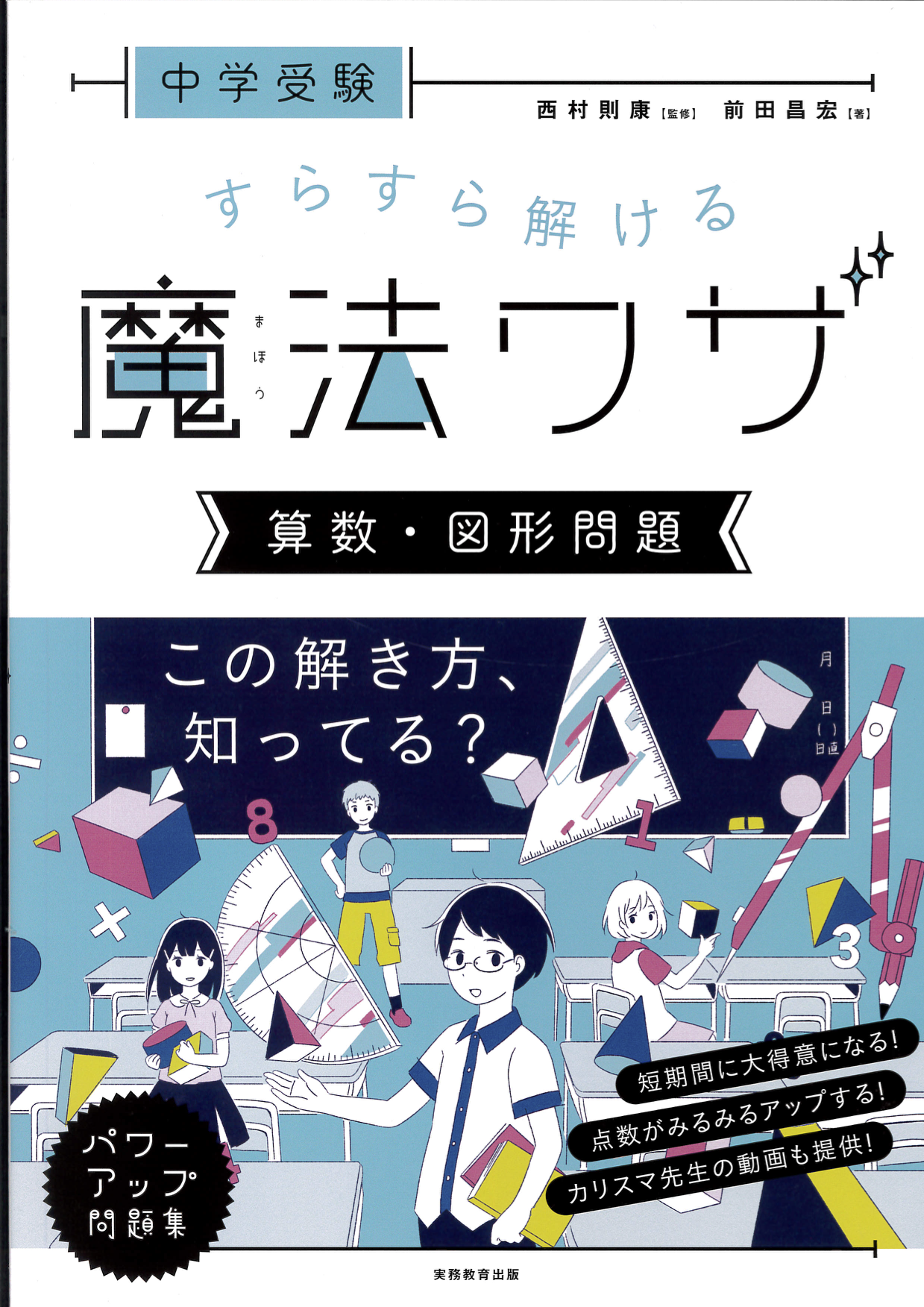目次
すべての整理は「その日のうちに」
具体的なテキストの整理方法
プリントの整理方法
続いていた雨模様も過ぎ去り、さわやかな陽気になりましたね。
週末は実力判定(日能研)や合不合判定テスト(四谷大塚)など、新年度最初の模試だった受験生の皆さんも多かったと思います。
手応えはいかがでしたか?
テストは受けることも大切ですが、それよりずっと大切なのは復習です。
結果は丁寧に分析し、きちんと弱点を克服しておくようにしてくださいね。
さて、大手中学受験塾では早くも新年度が始まり2ヶ月が経ちました。
小学校でも新学年がスタートし、ようやく新しい生活リズムが掴めてきた頃ではない可と思いますが、中にはまだ日々の課題に精一杯で、塾で配られるプリントやテキストが机の上に山積み……という人もたくさんいると思います。
せっかくの良い教材も、必要な時に取り出せなくては宝の持ち腐れですし、何より教材が山積みになった机では気持ちよく勉強ができませんよね。
そこで今日は、ドンドン増える塾のテキストやプリントを整理するおすすめの方法をお伝えします。
すべての整理は「その日のうちに」
まず、整理のペースですが、授業があった「その日のうちに」やるのがおすすめです。
忙しい皆さんが毎週末、整理整頓のための時間を取ることは難しいですよね。
特に高学年は配布物が多いため、たとえ1週間でもそれらを放ったらかしてしまうと、どれがいつのものだか分からなくなったり、答えと問題が揃わなくなったりと、整理に余計な手間と時間がかかってしまうことになるので気をつけましょう。
具体的なテキストの整理方法
それでは、教材ごとにおすすめの整理方法をお伝えします。
塾でもらってきたテキストは帰宅したらすぐに処理しましょう。
「処理」と言ったのは、それらをファイルなどに仕分けする前に、ある手順を踏んでほしいからです。
たとえばSAPIXのように授業毎に配布されるタイプの場合は、その都度プリンターでスキャンします。
3・4年生のうちは保護者の方にお願いしても良いですが、5・6年生になったら一緒に、もしくは一人でやれると良いですね。
この作業は慣れるまでちょっと面倒ではありますが、たとえ復習する時間や体力が残っていない日もスキャンだけは欠かさず行う習慣ができれば、少なくとも毎回、その日習ったことにざっとでも一通り目を通せることになります。
その日に習った内容を都度自覚すること、これは小さなことのようで、意外と効果的なことですよ。
また、前年度のテキストは基本的に見返すことはありませんが、ある単元において基礎からまるで判っていないことが発覚した(ゼロからやり直しが必要になった)場合はそれらを見返すこともあるかもしれません。
もちろん皆さんがそのような残念な事態に陥ることが無いように願っていますが、こうしてデータで残しておくことで、次の学年に上がった時になんの躊躇(ちゅうちょ)もなく原本をドサッと捨てられるメリットもあります。
過去1年分のテキストがごっそりなくなると、部屋が見違えるほど清々しますよ。
自宅にあるプリンターにデータ名の記録やファイリング機能も備わっている場合は、ぜひスキャンの際に単元名やテキストナンバーを入力して保存しておきましょう。
出来ればこのときデイリーチェックテストのみ、基礎問題のみなど、分類ごとに仕分けておくと、復習の際に必要な教材を簡単に探したり、過去問演習で発覚した苦手なジャンルの類題のみをチョイスして一気にプリントアウトできたりと、とても重宝します。
日能研のようにテキストが学年や学期などの初めに配布される場合は、科目ごとに裁断しておき、講習が終わったらスキャンしておけばよいでしょう。
このときカラーのデータが乏しいと感じる場合は、スキャンの際にネットや参考書からテーマごとに重要な写真やデータを選んで加えておくと、自分だけの充実した復習教材を作ることができてオススメですよ◎
プリントの整理方法
プリント類はテキスト内容と連動・重複していることがほとんどです。
科目・種類ごとにファイルやボックスを作り、授業の度にきちんと仕分け保存するとよいでしょう。
ボックスの背に科目や種類の名前を書き(もしくはシールなどを貼り)、復習しやすいように時系列にきちんと並べてしまっておくと、復習の際も便利です。
塾で配布されるテキストやプリント類は、各塾の講師陣による長年の入試研究結果が凝縮された、頼もしい受験勉強のパートナーです。
受験生の皆さんが志望校合格に向けて、これらの教材を最大限に活用でき、清々しい環境で充実した時間を過ごせるよう心から願っています。

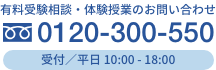


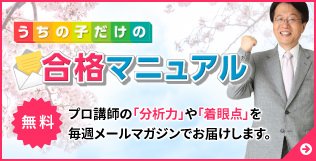



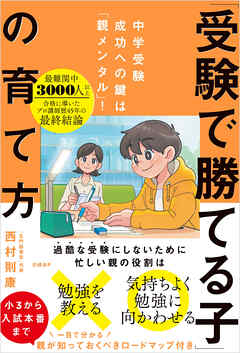
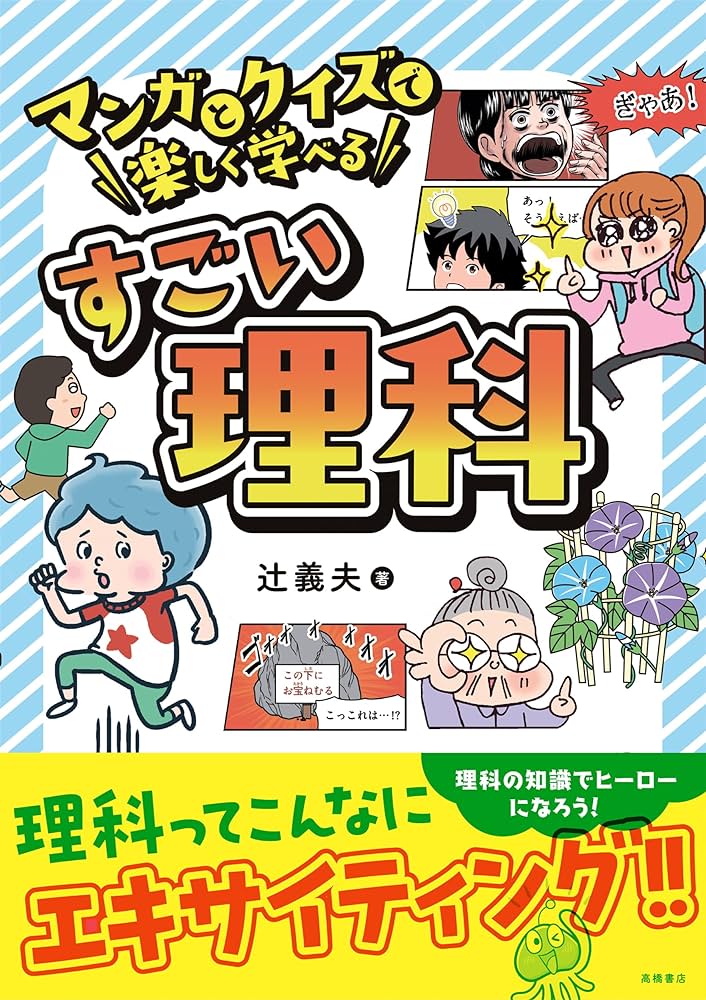
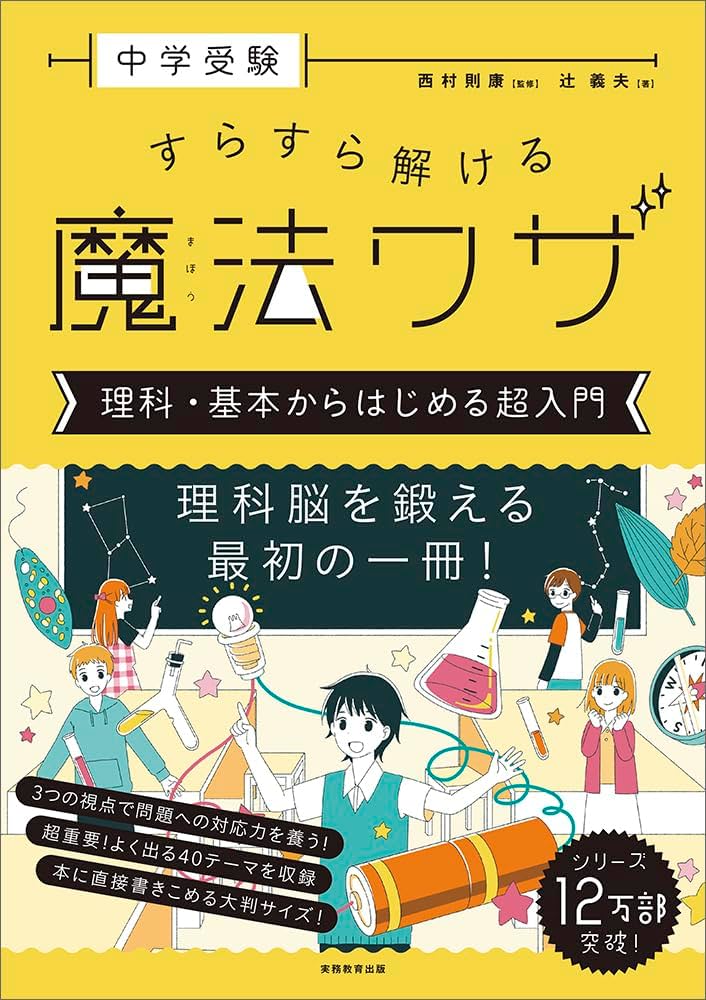
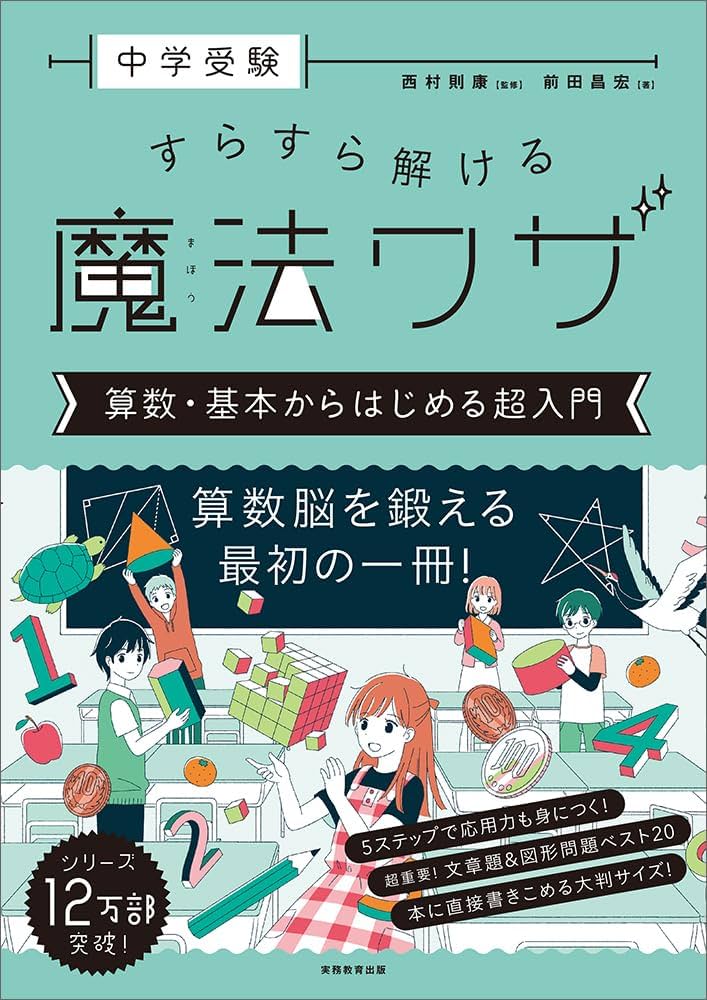
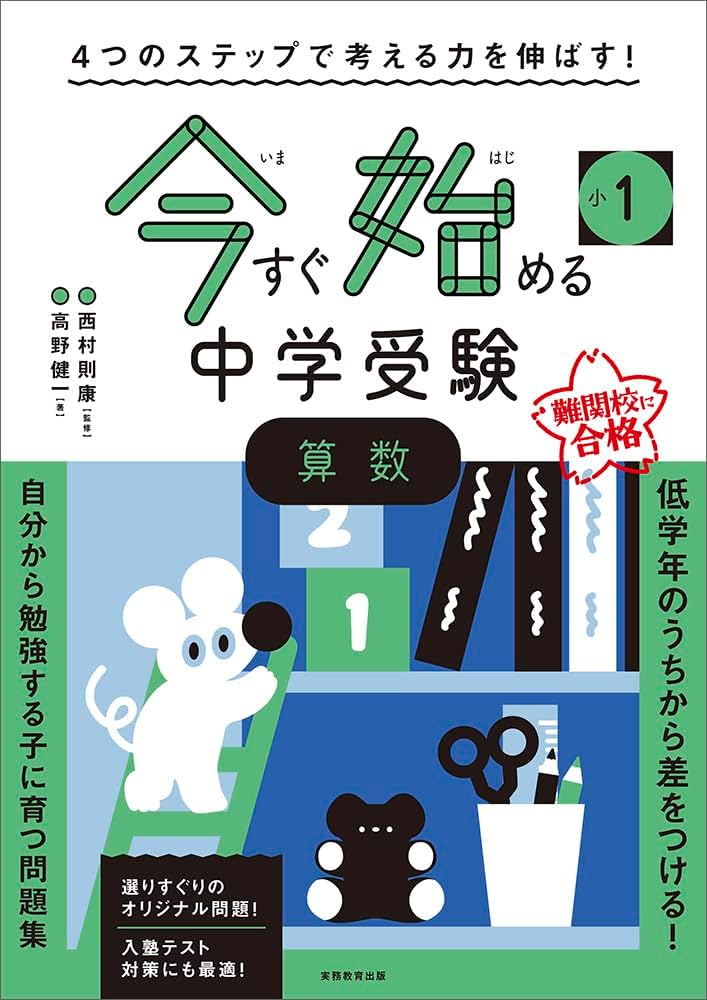
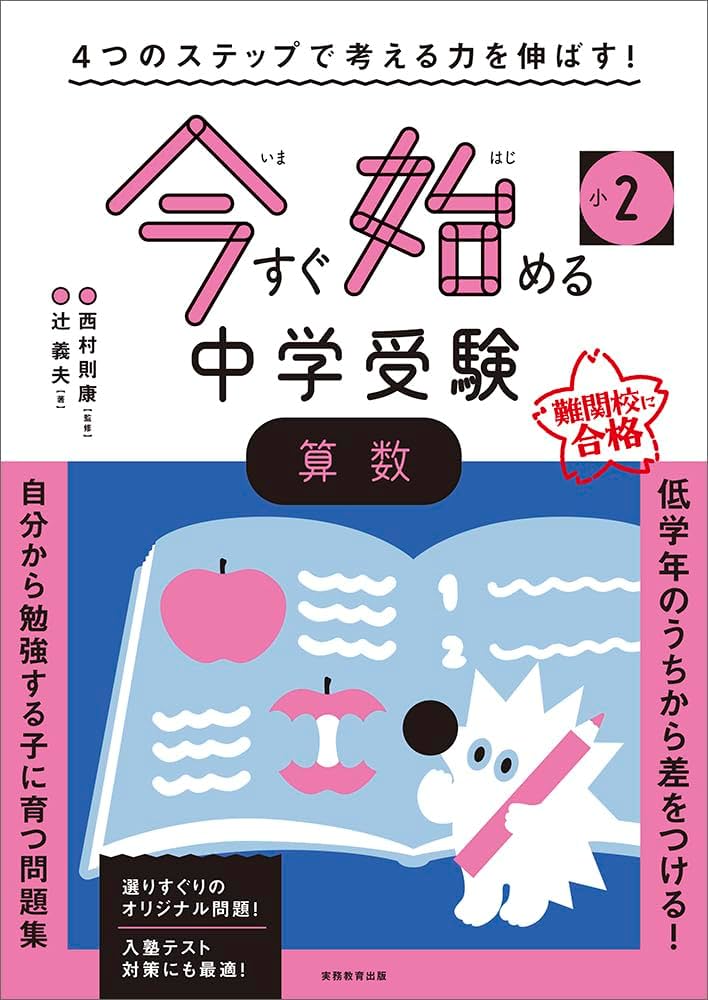
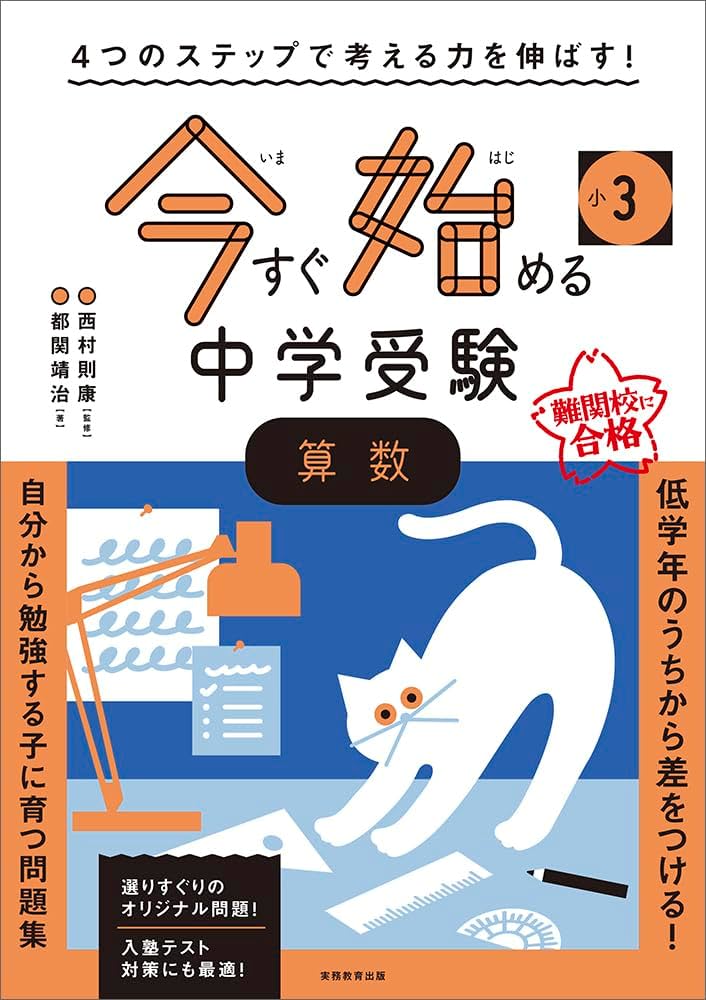
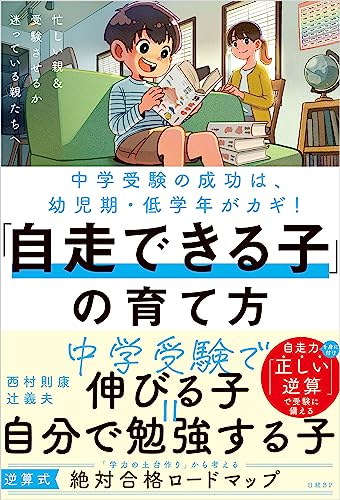
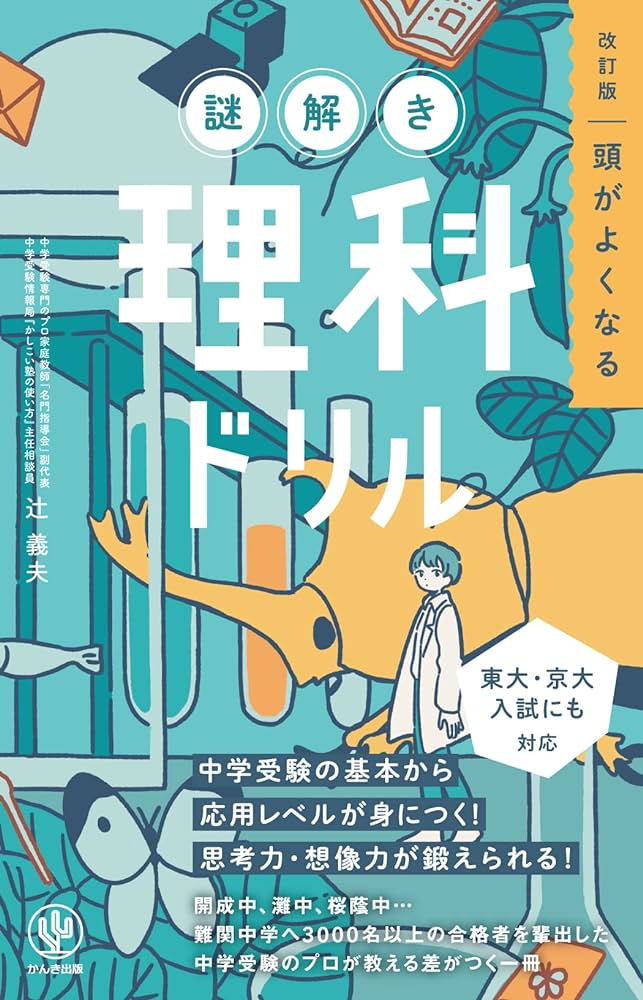
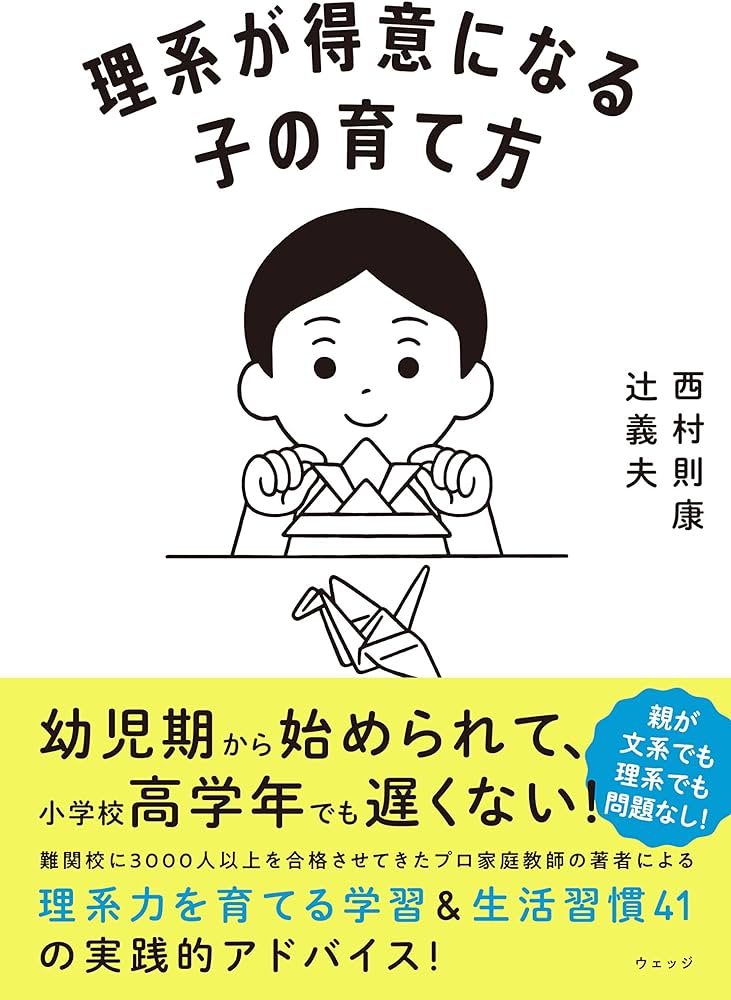

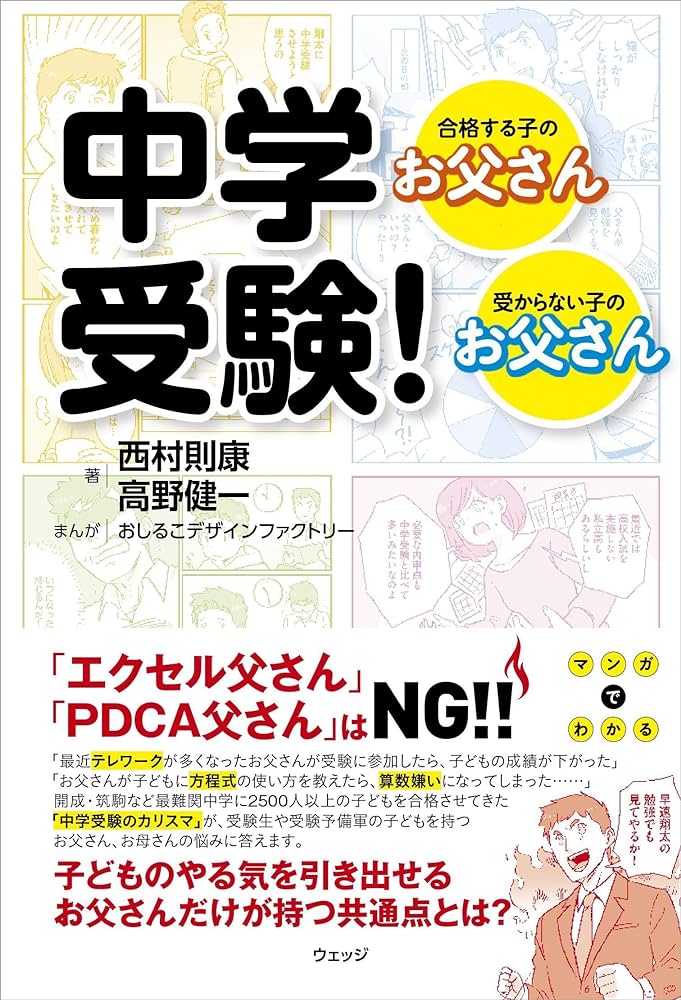
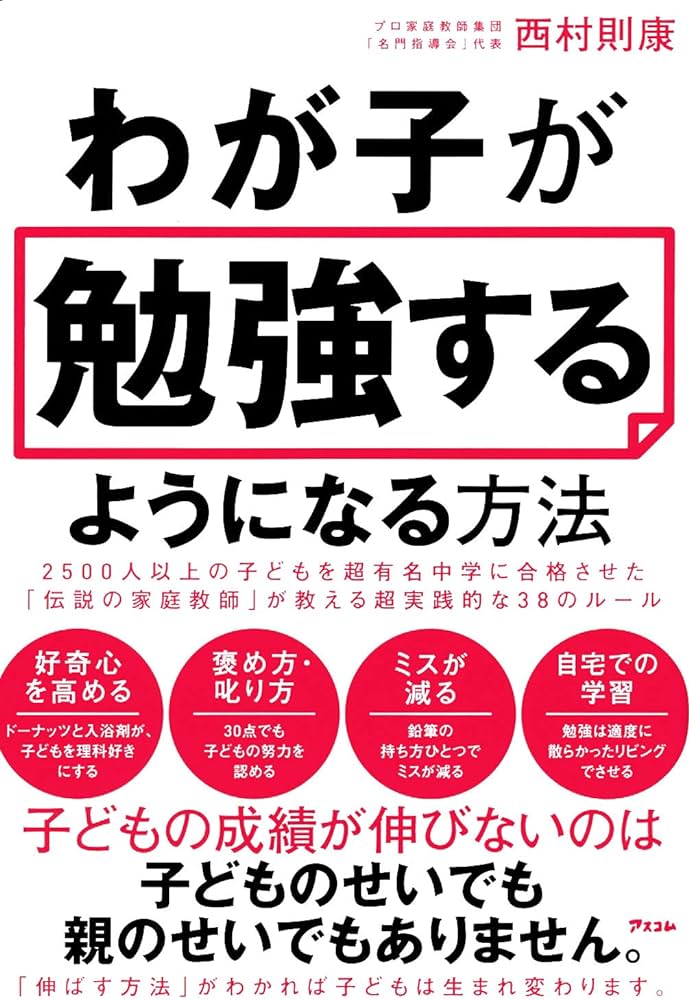
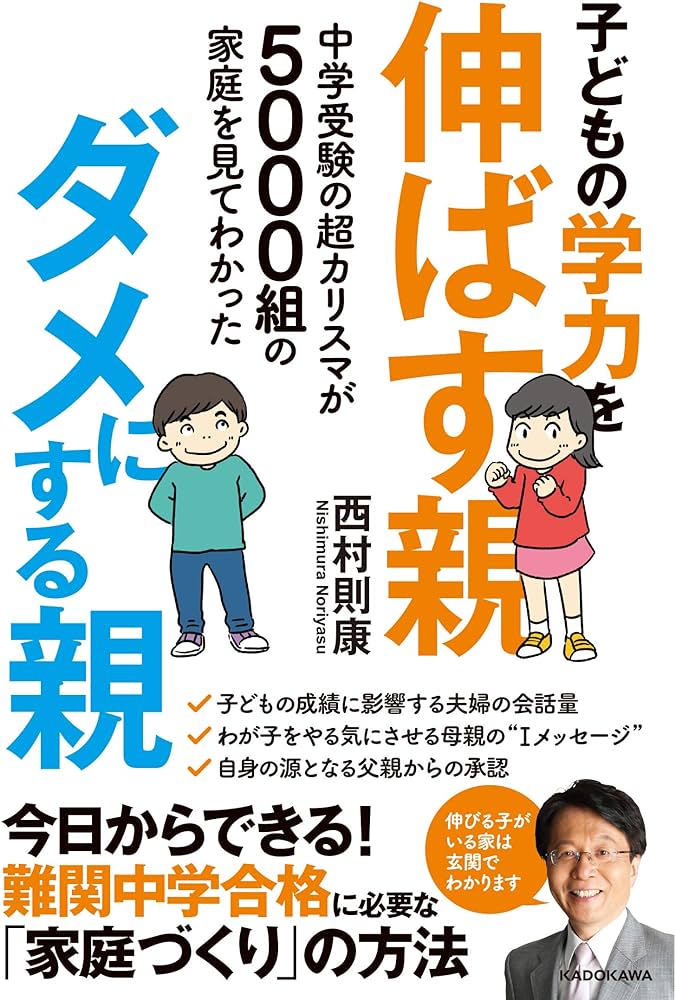
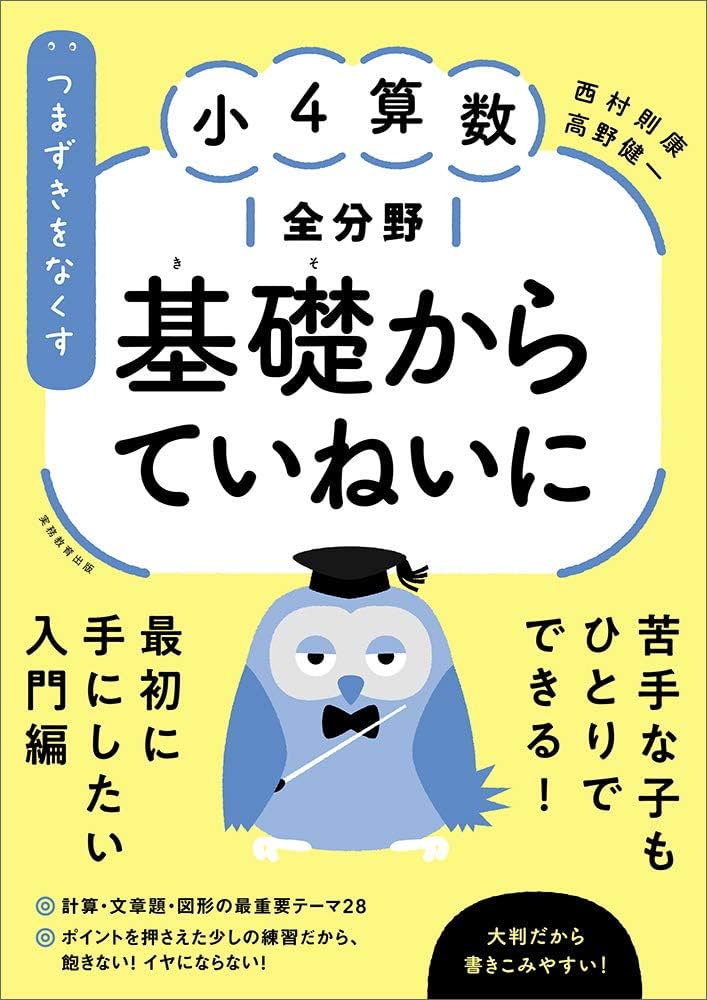
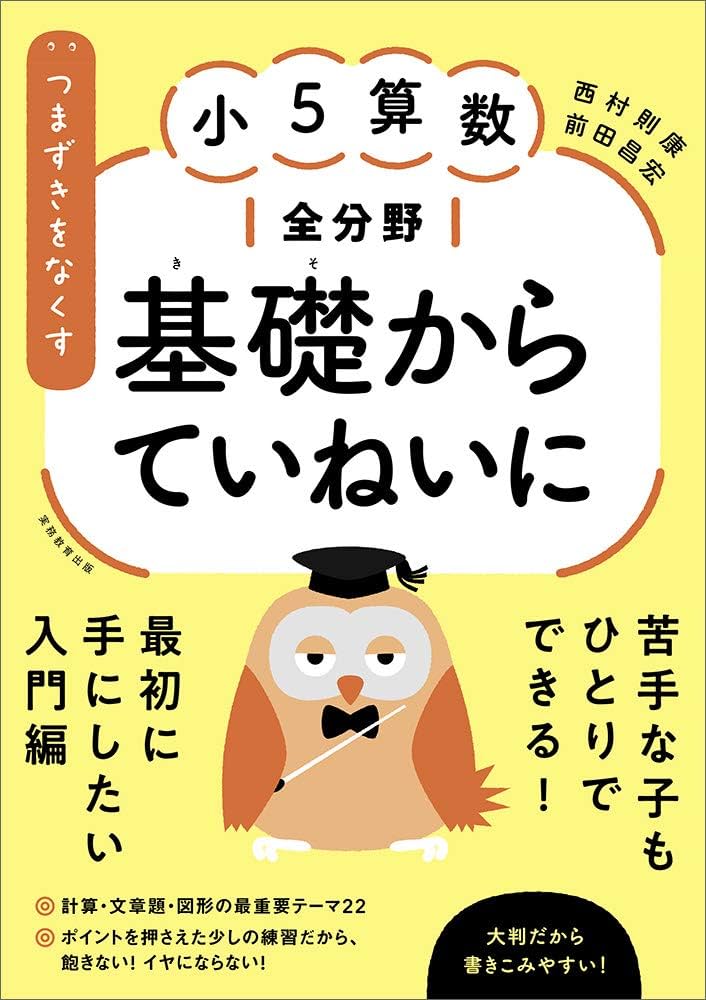
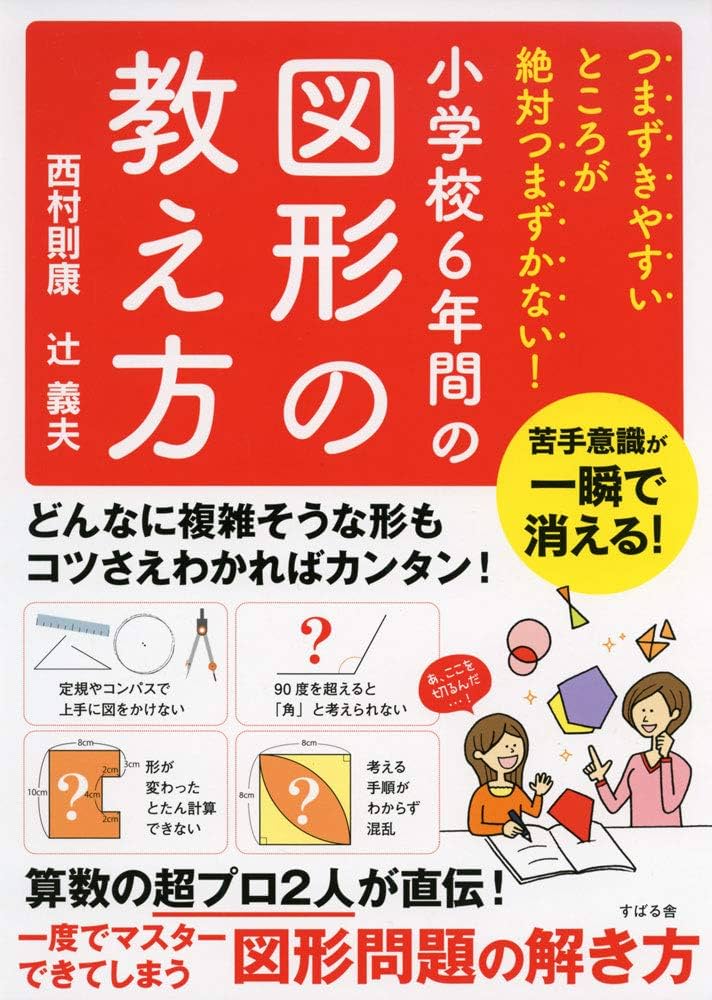
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[算数]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushsansu.jpg)
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[国語]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushkokugo.jpg)