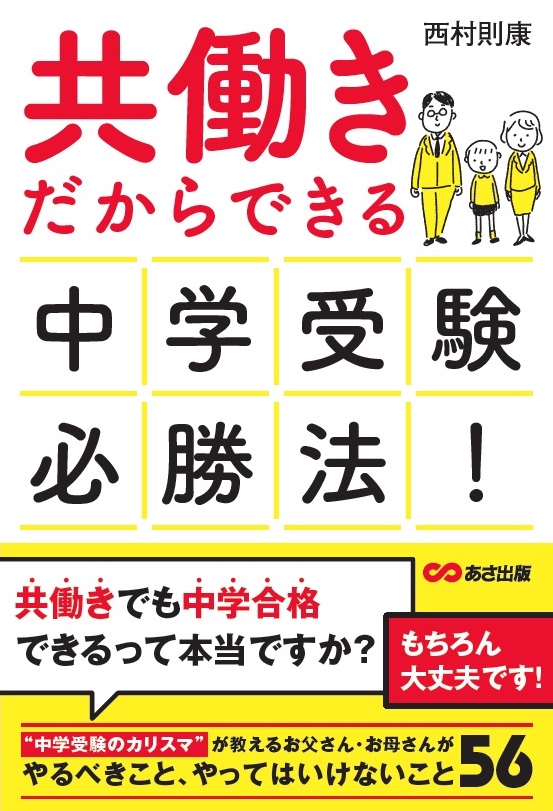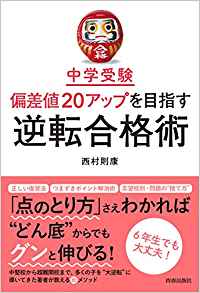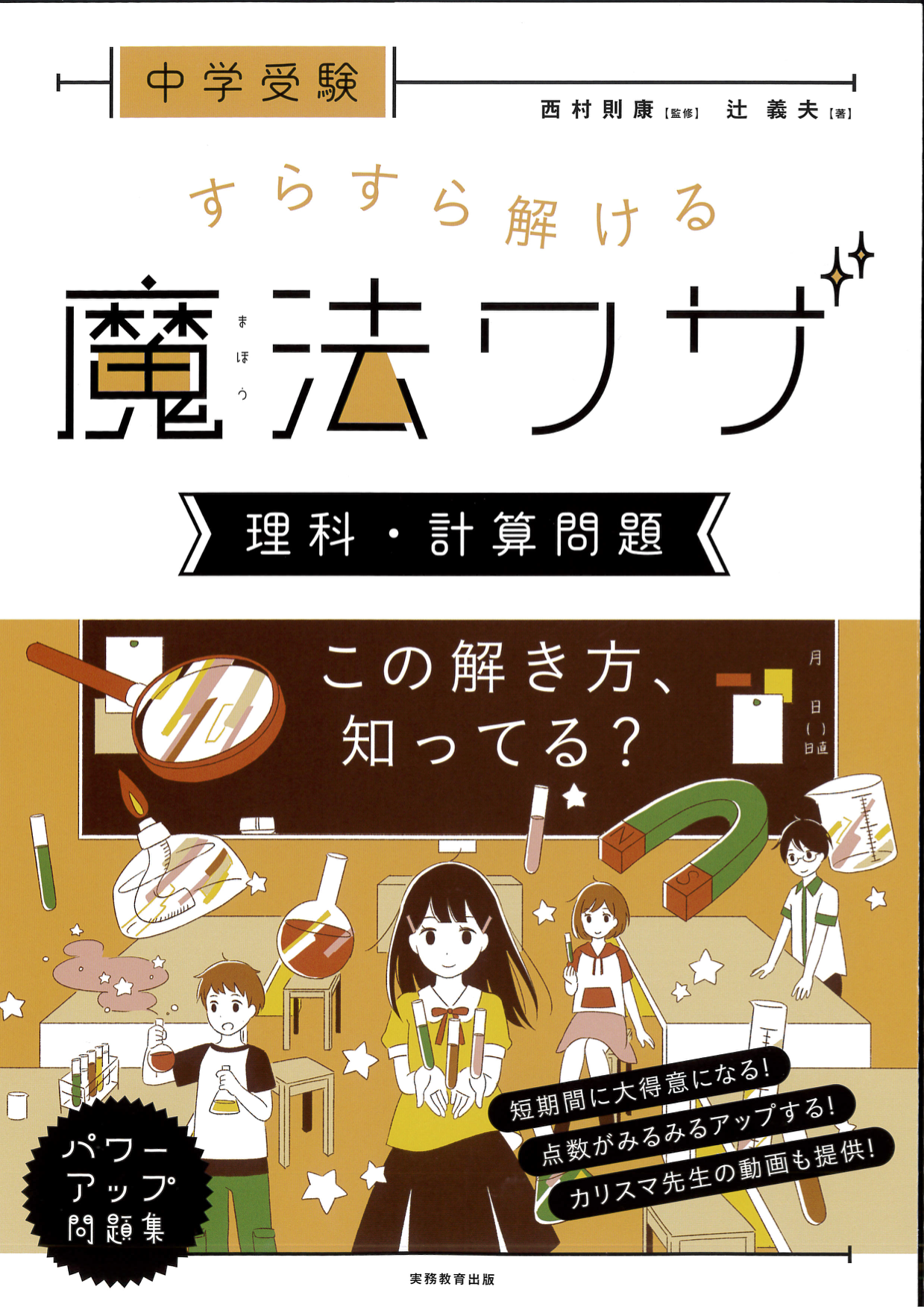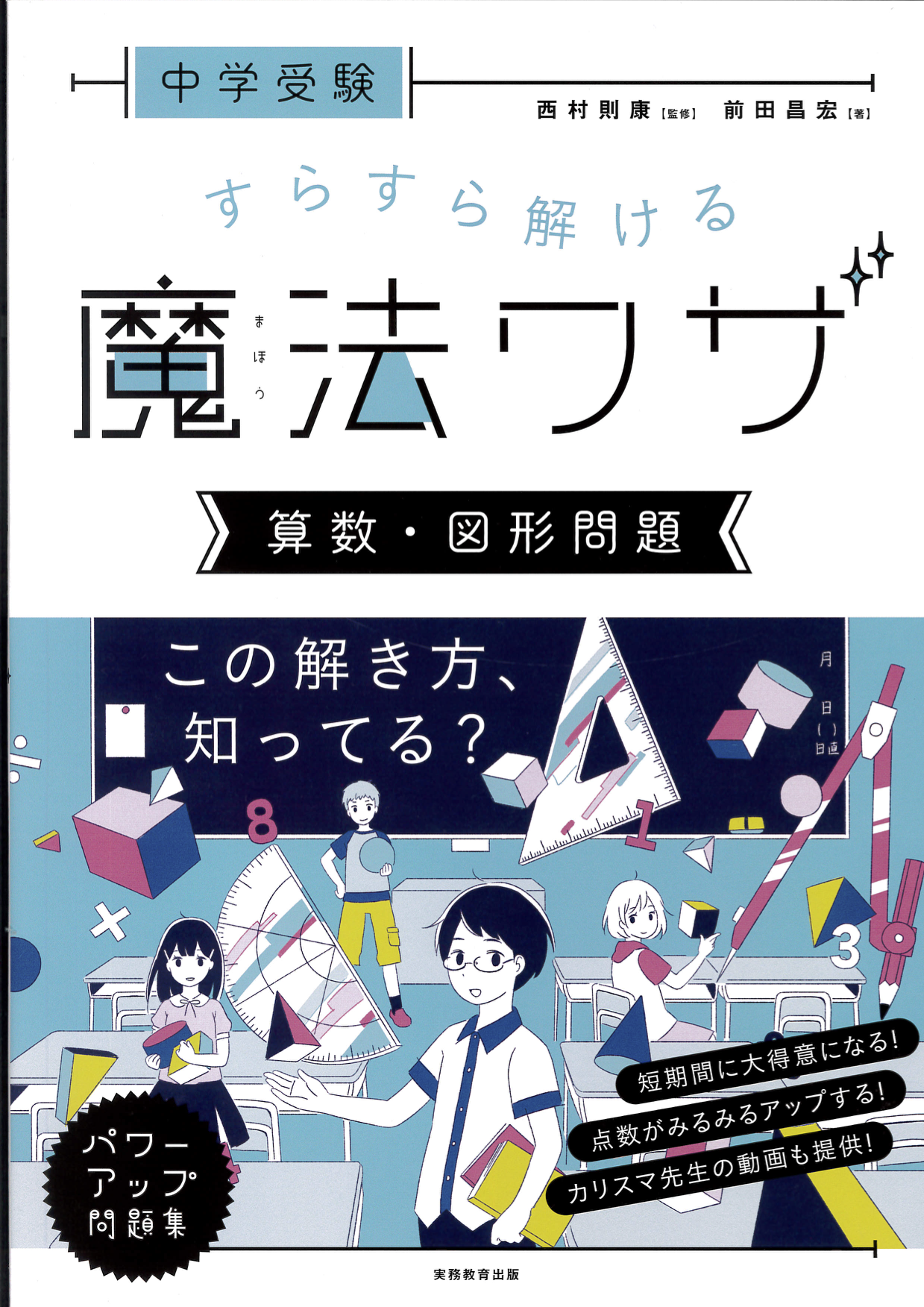目次
新学年 一週間の学習スケジュール
授業での「積み残し」にどう対応するか
特に新6年生は毎週のスピードに注意
2月になり、大手塾では新年度が始まりましたね。
新しい学年になり、過去に習ったことの〝積み残し〟が気になっている生徒さんも多いのではないでしょうか?
受験シーズンである1月末〜今月頭の休講期間にしっかり対処できた人は良いのですが、僅かな日数ですからなかなか難しかった人が殆どではないでしょうか。
そこで今日は、前の学年(もしくはもっと以前)から分からないままになってしまっている単元・苦手なままになってしまっている単元の〝積み残し〟にどう対処したら良いか考えてみましょう。
新学年 一週間の学習スケジュール
まず、新学年は新学年の塾の課題やスケジュールもありますから、家庭教師や個別指導の先生と相談ができる人は、そのような状況をなるべく早く伝えましょう。
過去の単元を復習するには、目の前の「今習っていること」をしっかり理解したうえで、「余裕の時間」で取り組む必要があります。
一人一人積み残しの分量や状況(どの程度からやり直す必要があるか)、塾・学校のスケジュールなどは異なりますから、自分の現状を良く知る先生と相談しながら、計画を立ててスタートできればそれが一番です。
難しい場合は、親御さんなどの力も借りながら自分で過去のテストなどを洗い出し、苦手な単元とその原因を明確にしたうえで、それらを書き出し、塾や学校のスケジュールと照らし合わせて、いつ、どのようにそれらの復習を行うか考えていく必要があります。
苦手な単元の洗い出しまでは一人で出来るかもしれませんが、それらの根本原因がどこにあるかの特定や、その復習をどんな順序で、何の教材を用いて、どのように学校や塾の忙しいスケジュールの合間に組み込んで行くかという具体的な部分の計画は、小学生一人ではなかなか難しいものがあります。
出来るだけ中学受験の豊富な経験を持つ先生などに助言をもらい、無理や抜けのない綿密な計画を立てるようにしましょう。
授業での「積み残し」にどう対応するか
今後の学習においても、時には授業の流れに乗れず、積み残しが発生してしまうこともあると思います。
そんな時は、後で対処しやすいように、「形で残しておく」ことがポイントです。
テストで出来なかった問題を解き直すのはもちろんですが、「結構難しかったな」「なんとなく不安だな」「一応解説は読んで理解したけれど、時間が経ってまた解いたら出来るかな」などと感じたときは、実際に後日きちんとできるか確かめられるようにしておきたいですよね。
そこで、そのような問題はコピーをとり、ノートに貼る、ファイルにスクラップする等して、形で残しておきましょう。
裏面に解説、解答を貼るとなお◎です。
それらを一つにまとめておくことで、自分が苦手なものをいつでも少しずつ復習することが出来ますし、ジャンルにとらわれない自分だけの効果的な復習ドリルにもなりますから、同様の(範囲のない実力)テスト対策としても使いやすいですよ。
特に新6年生は毎週のスピードに注意
過去の積み残しが怖いのは、今後習っていく新しいことの理解が進まなくなったり、学習がうまく積み重ならなくなったりしてしまうことです。
また、毎週・毎月の範囲のあるテストでは何とか点が取れても範囲のないテストではいつも点数が伸びない、という状況も出てきてしまうので、無駄も不安もドンドン増えていってしまいます。
新6年生の皆さんは、ここから夏まで、これまで学んだことの総復習と応用演習がものすごいスピードで進んで行くわけですから、特に注意が必要です。
土日も模試が入りますます忙しくなりますが、目の前の課題(今週の勉強)にばかりとらわれず、放置してきてしまった積み残しに今すぐ着手し、不安・ストレスの種を早めに取り除いておきましょう。
新年度を迎え、新たな希望に満ちた慌ただしい日々が始まっていることと思います。
ぜひ毎日の学習の中に〝積み残しの復習計画〟を上手に盛り込み、今後の学習をより楽しく、効果的なものにしてくださいね。
皆さんが心も身体も健やかに受験生活を送れることを願っています。

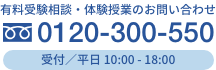


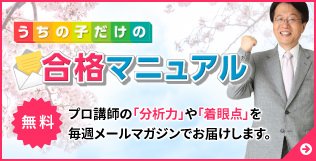



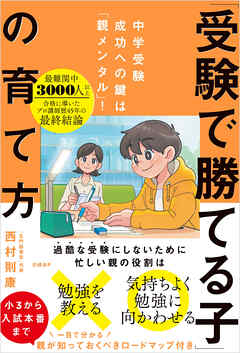
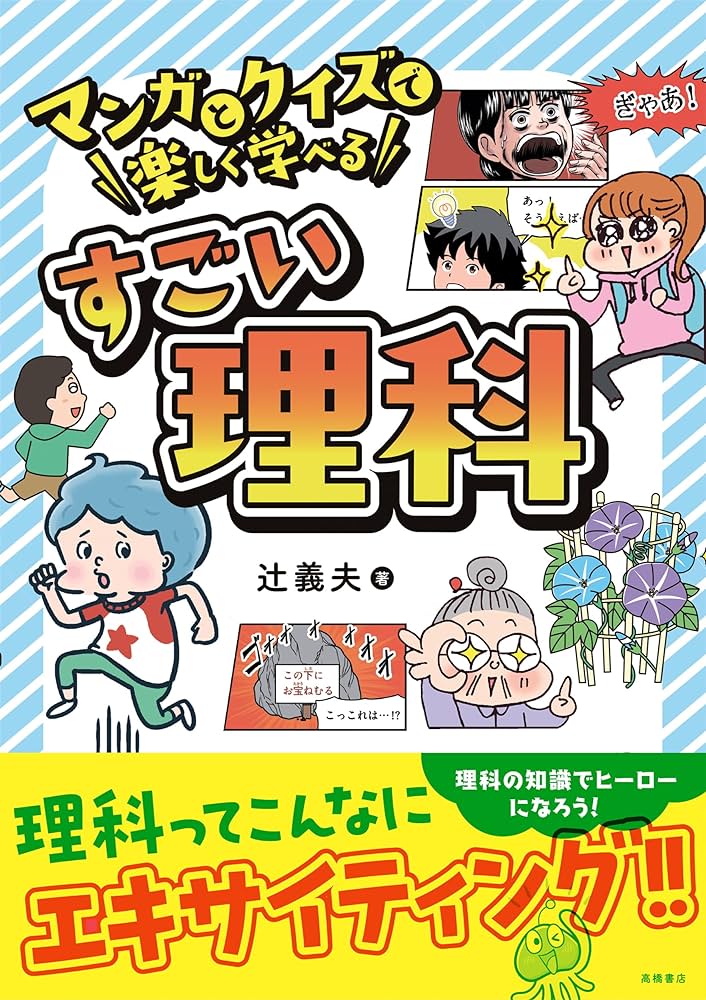
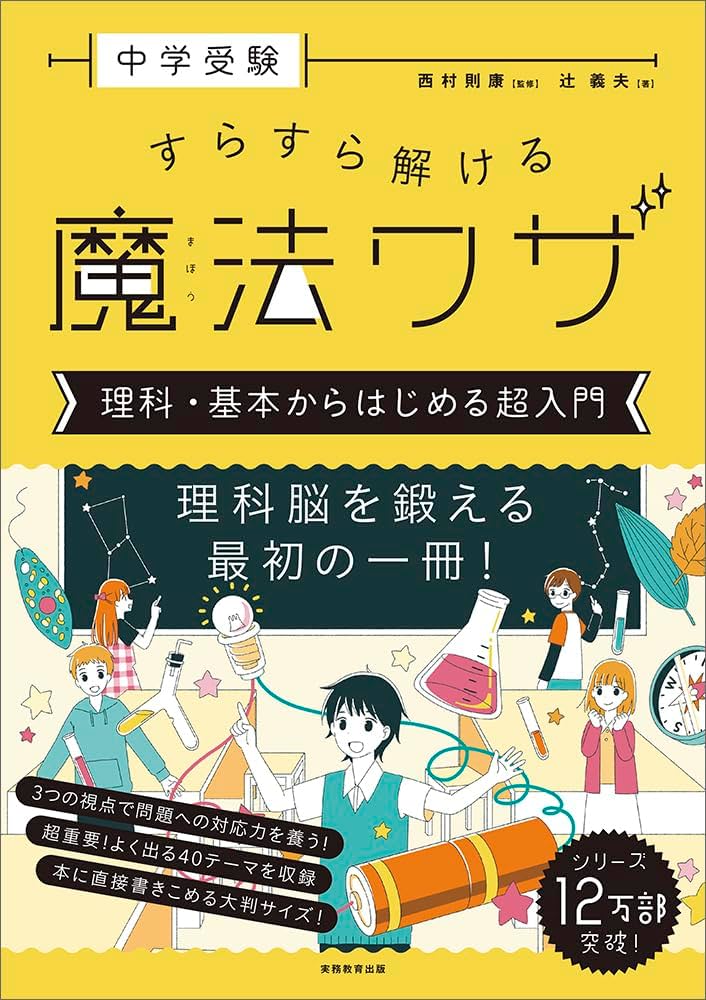
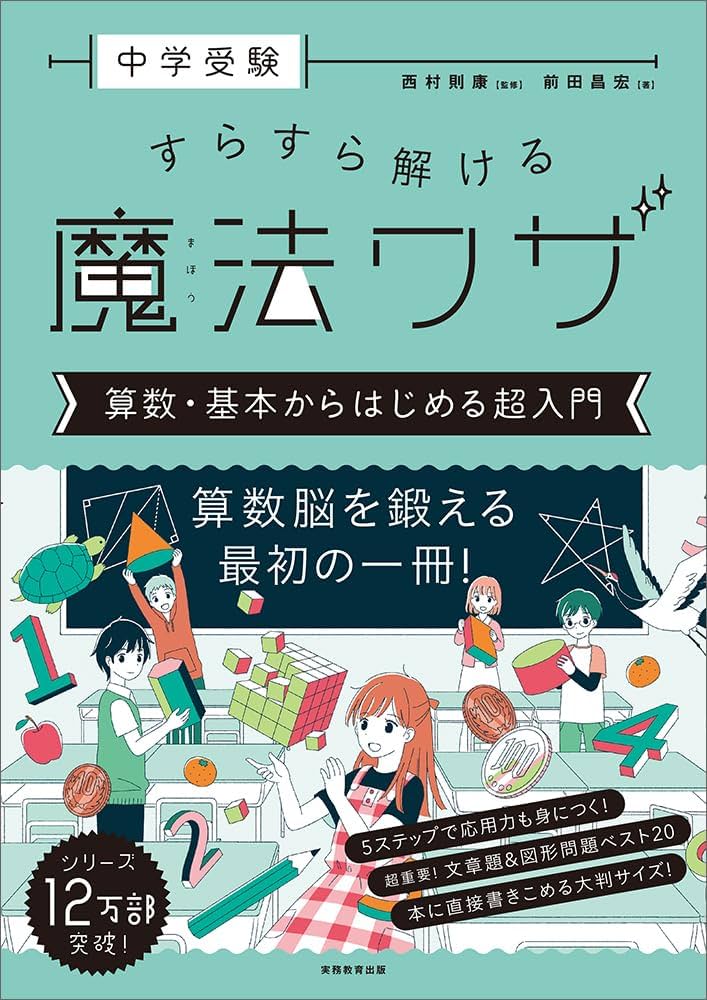
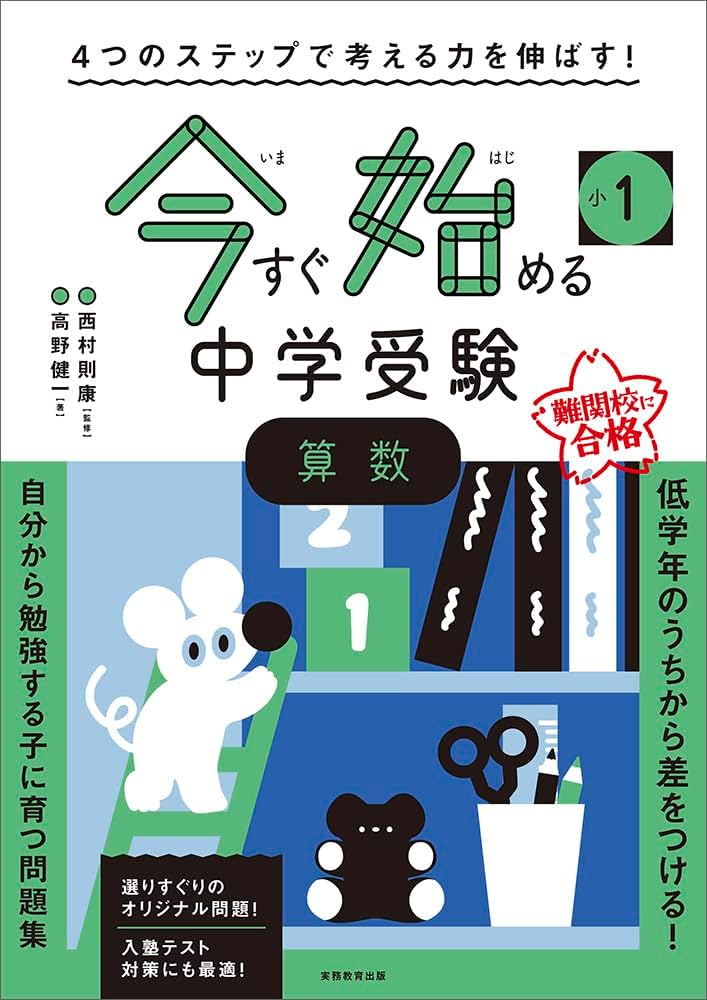
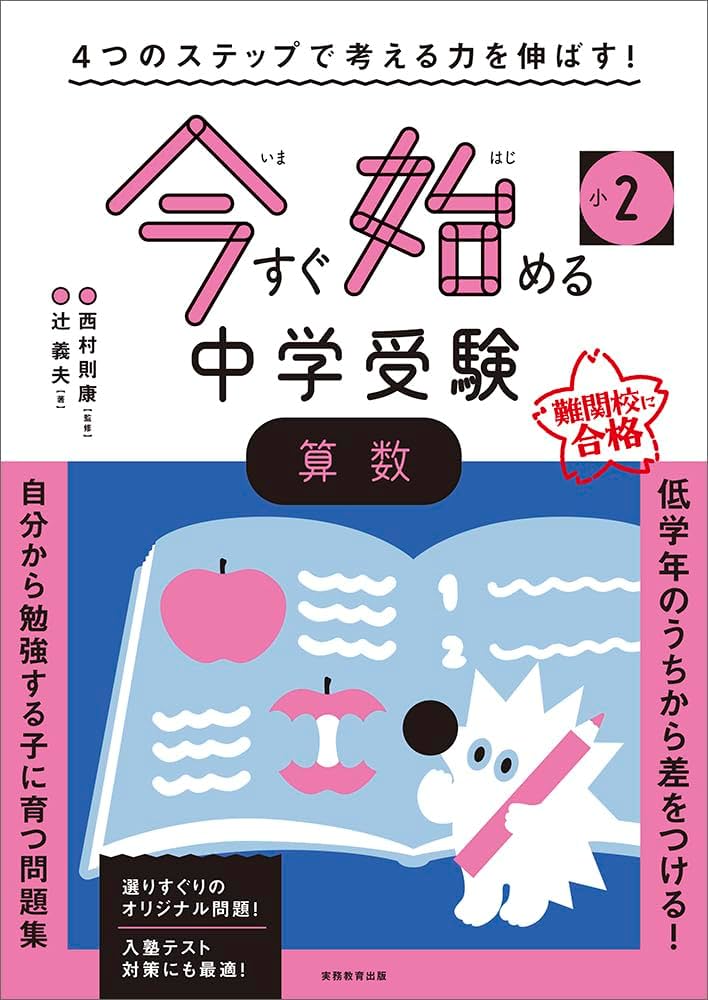
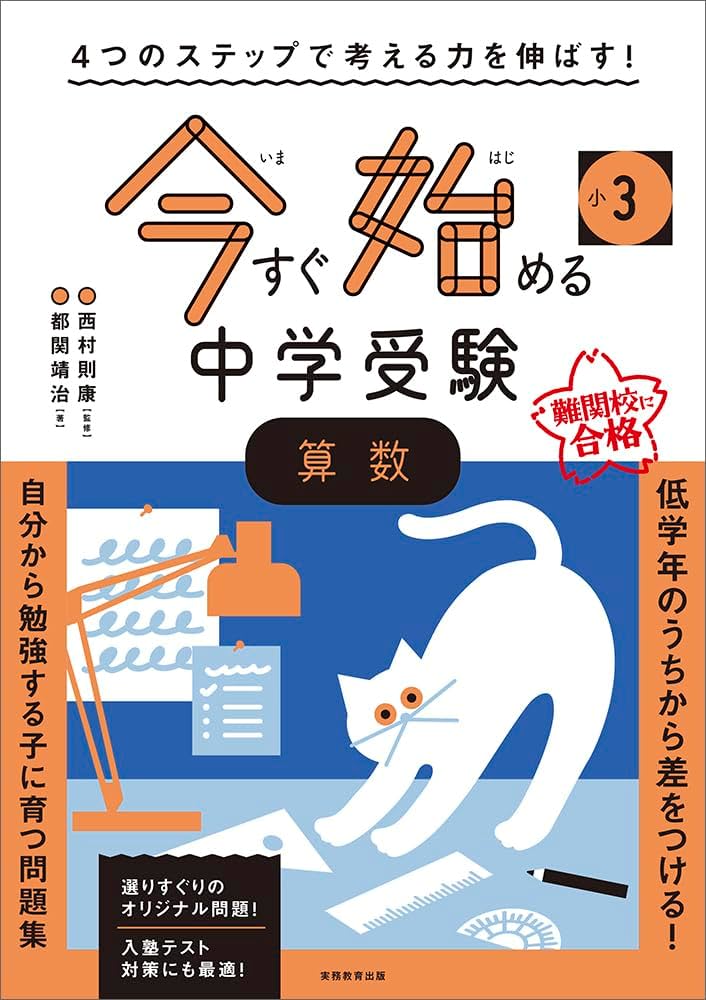
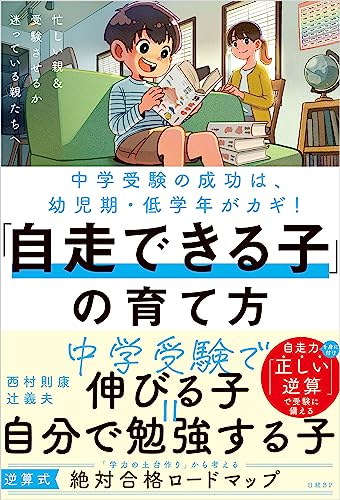
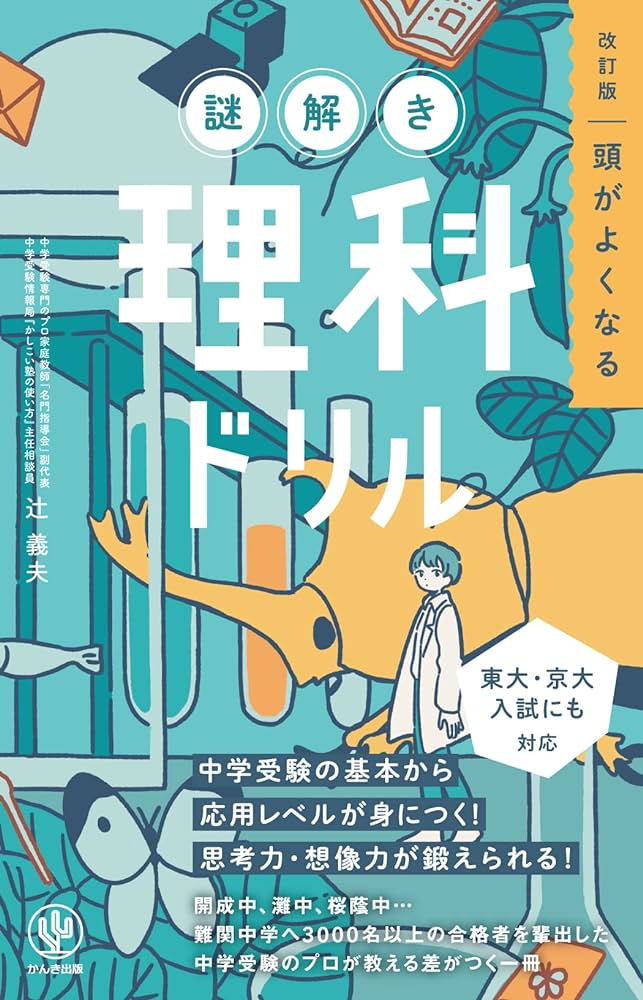
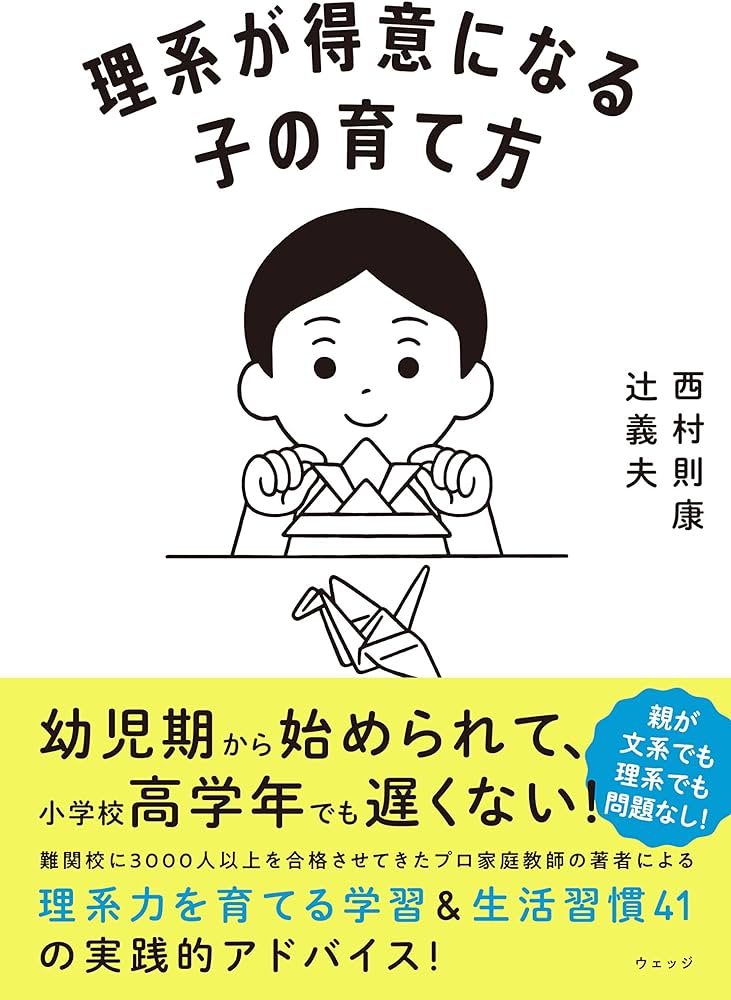

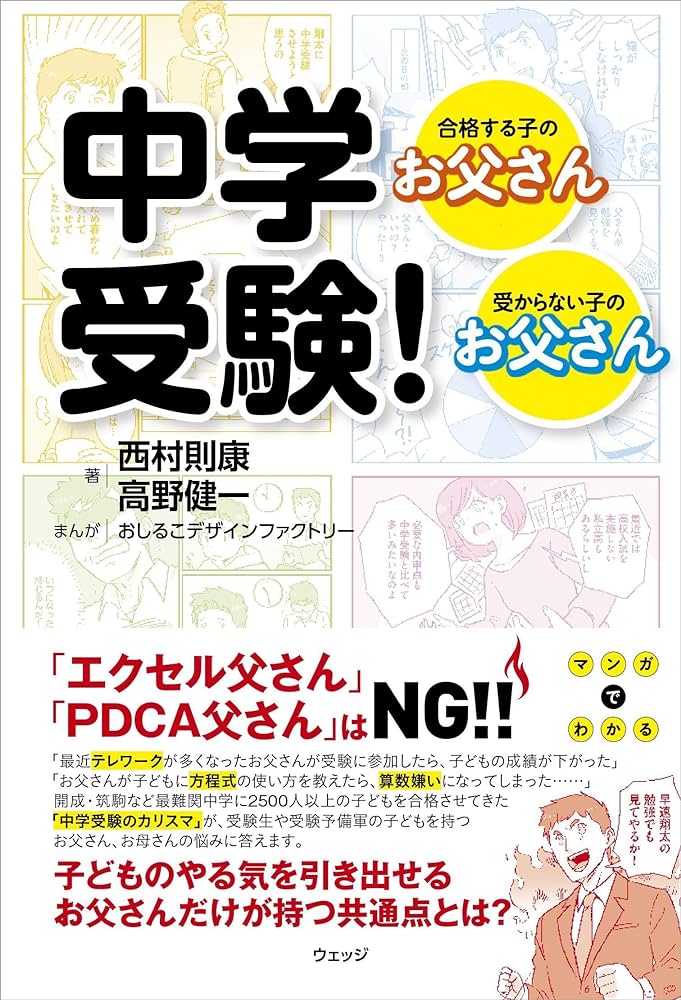
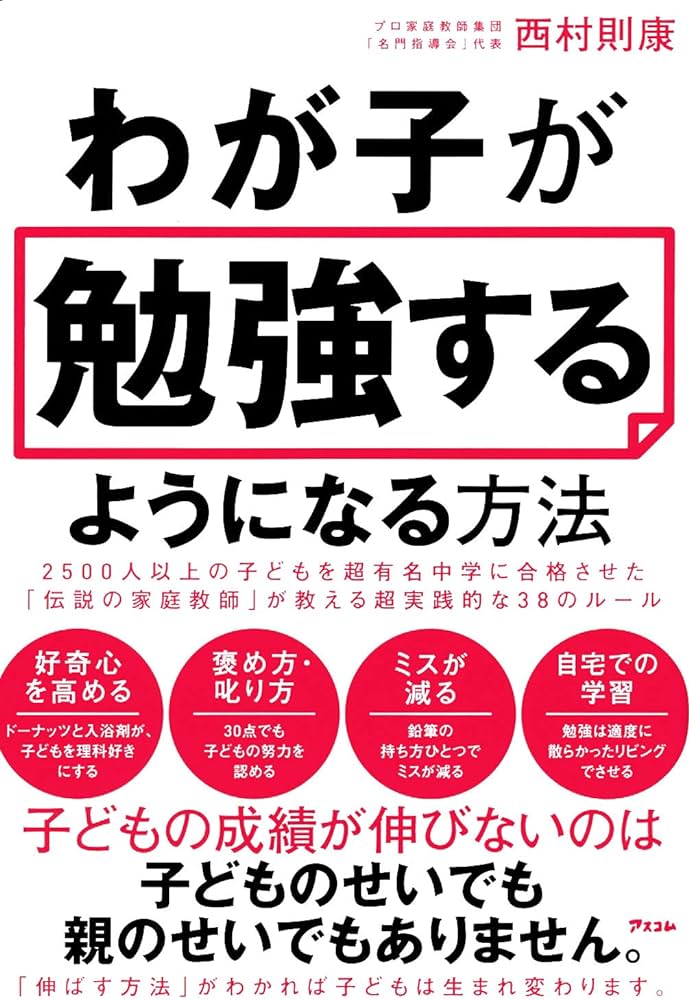
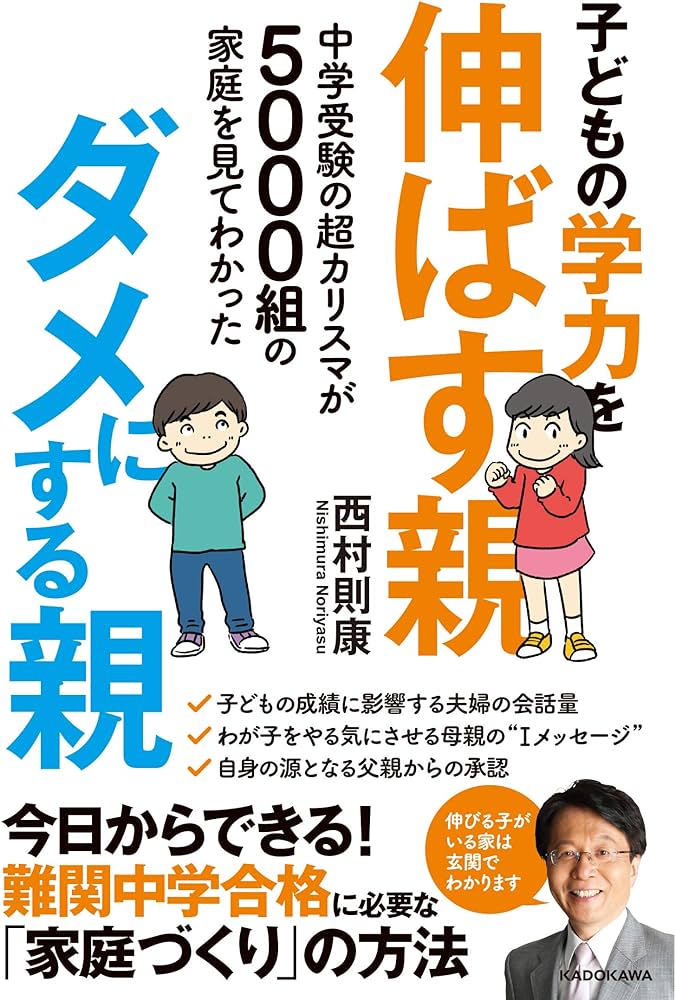
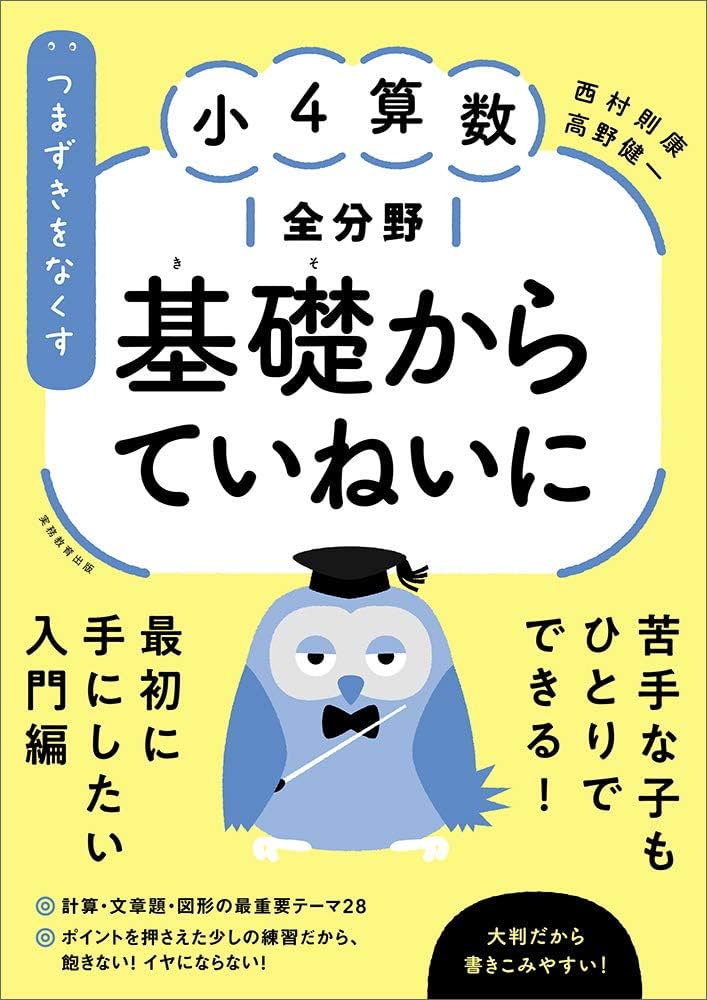
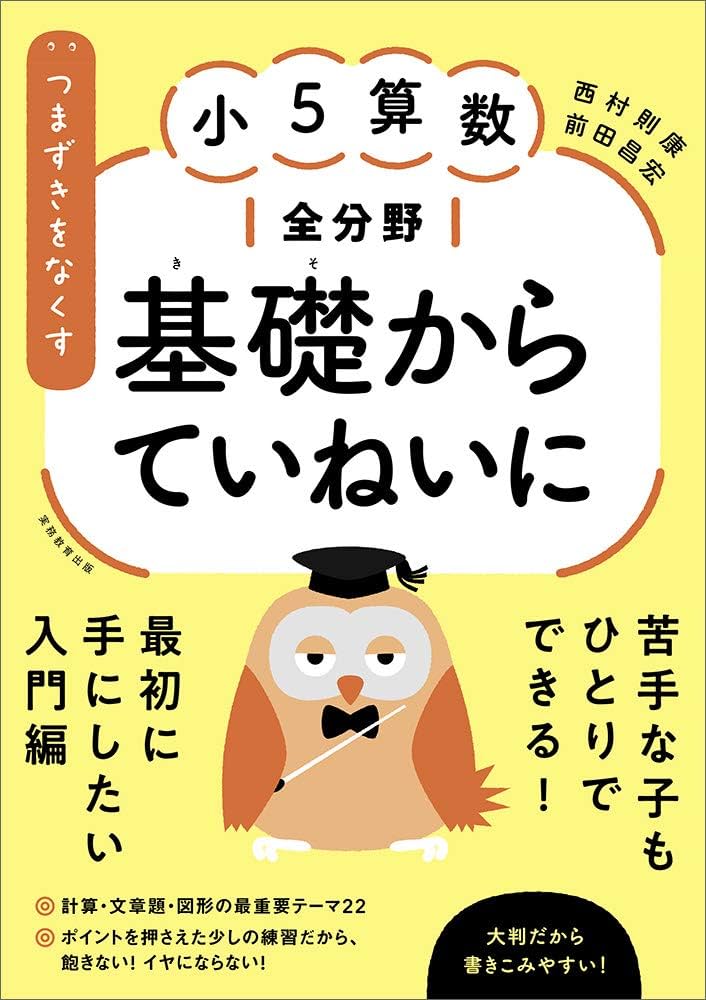
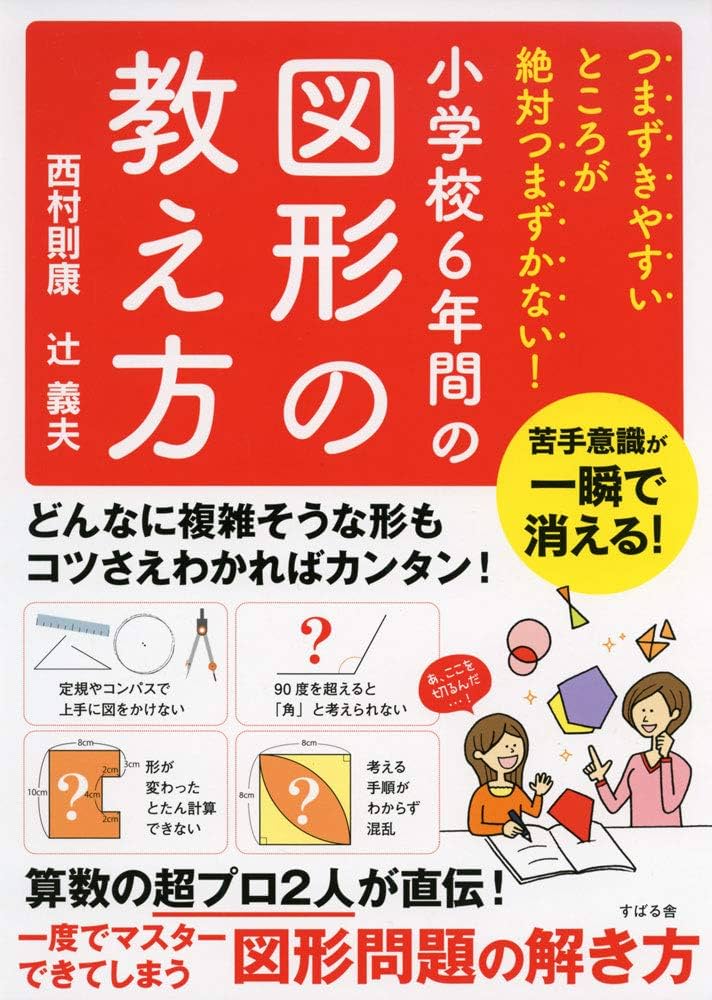
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[算数]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushsansu.jpg)
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[国語]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushkokugo.jpg)