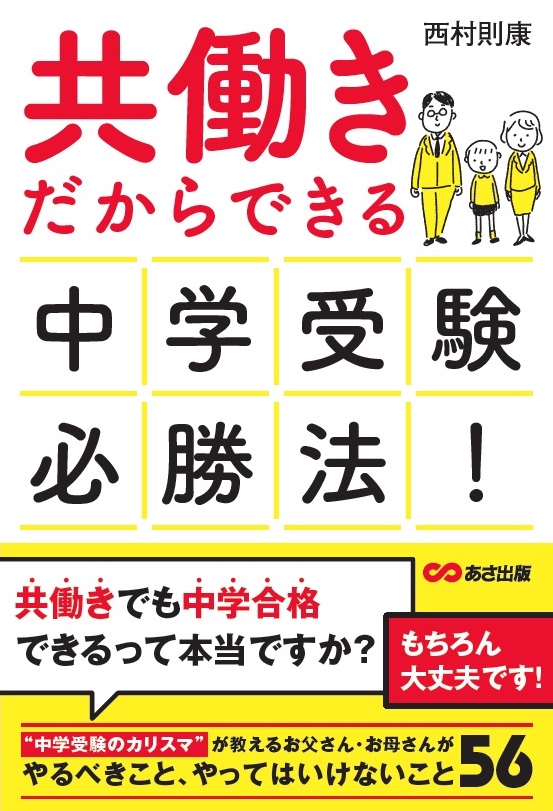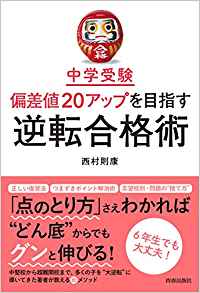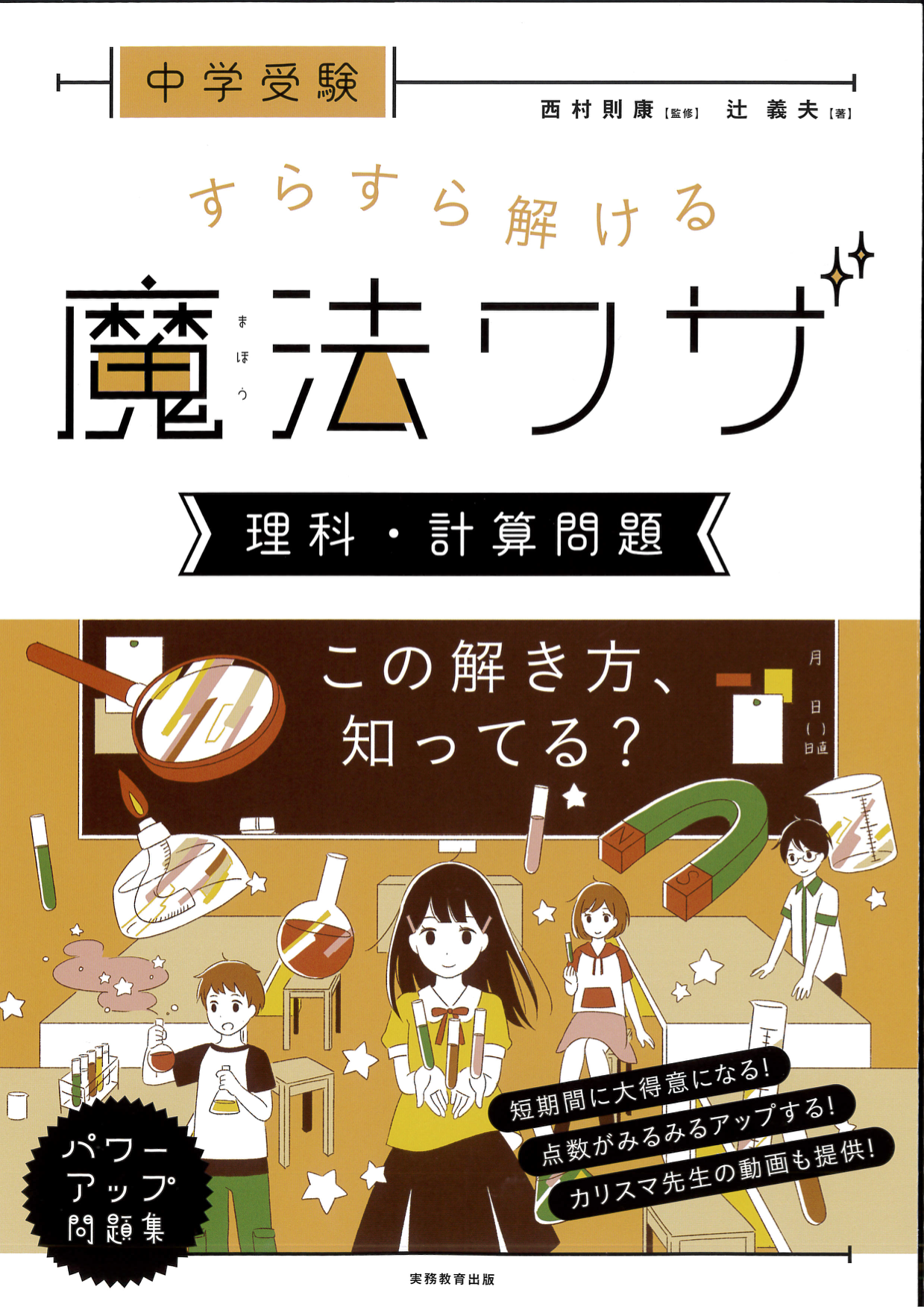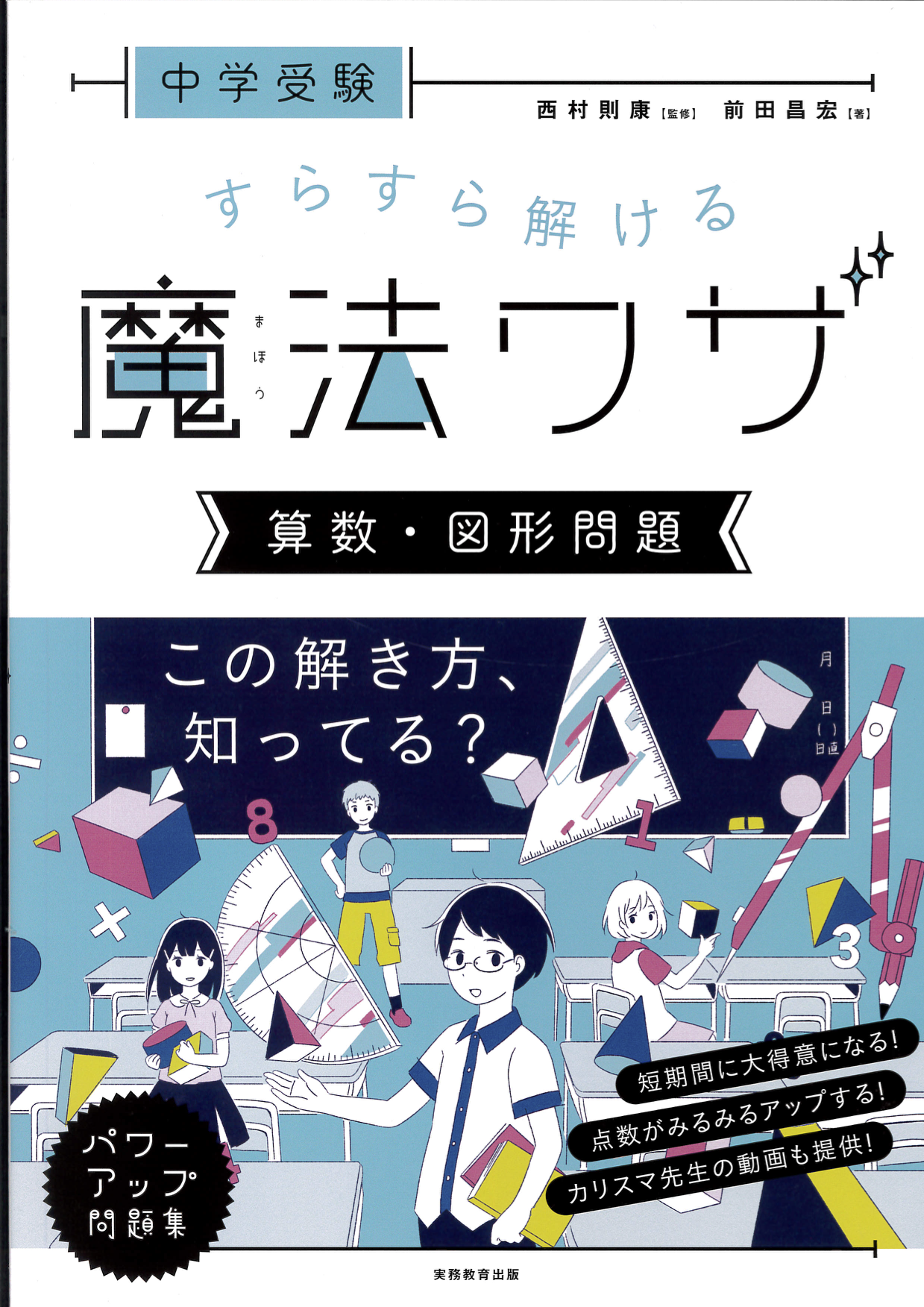目次
入試の国語には前年話題の本がよく出題される
「本屋大賞」に注目しよう
大賞〜第三位はどんな本?
澄んだ空と爽やかな風が心地好いですね。
入試の国語には前年話題の本がよく出題される
さて、中学入試の国語では、過去1年間で話題になった作品がよく扱われているのをご存知ですか?
もちろん宮沢賢治や太宰治、武者小路実篤など古い作家の作品も扱われますが、多くの学校で新作・新刊本が好まれる理由は、受験生がテキスト等で学習していない初見の文章の方が、その実力をしっかり測ることが出来るからです。
国語では出題された作品が既読であるかないかにより、読解のスピードや理解度がまるで変わりますし、塾では題材のテーマや会話の内容について授業内で深く掘り下げ、噛み砕いて解説してしまうため、入試では出来るだけ多くの生徒がテキストやテストで触れていない作品を選び、平等・正確に生徒を評価しようというわけです。
もちろん塾側もそれを踏まえて、名作と呼ばれる過去の作品をしっかり押さえつつも、毎年新作をテキストやテストで扱うようにしていますが、それらの作成にはある程度の時間を要するため、予想問題や対策がその年度の入試には間に合わないこともしばしばです。
ですので、生徒の皆さんはぜひ、G.W.や夏休みなどのまとまった時間が取れるタイミングには本屋へ自ら足を運び、話題の新刊をチェックしてみましょう。
特に、皆さんと同じ10代の少年少女が主人公の小説や、皆さん〜高校生くらいの世代に向けて書かれた論説文などは読みやすい上にテストにもよく出るのでおすすめですよ。
「本屋大賞」に注目しよう
「話題の新刊」と言いましたが、具体的な探し方としては、Amazonなどのネットでランキングをチェックしても良いですし、本屋で平積みの本を確認したり、各賞を受賞した作品を手に取ってみたりすると良いと思います。
ちなみに4月9日には書店員が売りたい本を選出する「本屋大賞」の発表がありました。
例年、本屋大賞の作品が確定するよりも中学受験で扱われるタイミングの方が早いので、これらの作品がそのまま入試に出ることは多くありません。
しかし、これらの作品により話題になった作家の別の作品が入試に出題されることは大変よくありますので、気になった方はぜひ、以下の作品でも、同じ作家の別の作品でも良いので読んでみてくださいね。
大賞〜第三位はどんな本?
参考までに、大賞〜第三位までのあらすじはこのようなものです。
◎2025年本屋大賞
☆第一位(大賞)『カフネ』(阿部暁子著/講談社)
*法務局に勤める野宮薫子は、溺愛していた弟が急死して悲嘆にくれていたが、弟の元恋人・小野寺せつなに会い、やがて彼女が勤める家事代行サービス会社「カフネ」の活動を手伝うことになった。弟を亡くした薫子と弟の元恋人せつなの二人の距離は、食べることを通じて次第に縮まっていく。
☆第二位 『アルプス席の母』(早見和真著/小学館)
*秋山菜々子は、神奈川で看護師をしながら一人息子の航太郎を育てていた。シニアリーグで活躍する航太郎には関東一円の学校からスカウトが来ていたが、選び取ったのはとある大阪の新興校。息子とともに、菜々子もまた大阪に拠点を移すことを決意するが……。
(※こちらの作品は2025年度の入試で複数採用されました。)
☆第三位 『小説』(野崎まど著/講談社)
*5歳で読んだ『走れメロス』をきっかけに、内海集司の人生は小説にささげられることになった。12歳になると、内海集司は小説の魅力を共有できる生涯の友・外崎真と出会い、二人は小説家が住んでいるというモジャ屋敷に潜り込む。そこでは好きなだけ本を読んでいても怒られることはなく、小説家・髭先生は二人の小説世界をさらに豊かにしていく。しかし、その屋敷にはある秘密があった。
各塾のG.W.講習は、この先に控えている夏期講習よりも授業や課題のボリューム・負担が比較的少ないです。
ぜひこの機会を利用して読書も大いに楽しみ、読む力をメキメキと育ててくださいね!
皆さんが心も身体も健やかに、充実したG.W.を過ごせるよう願っています。

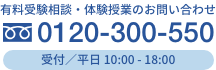










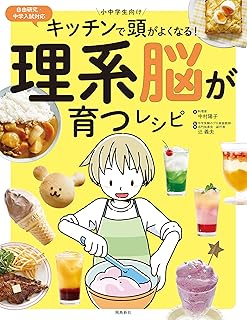
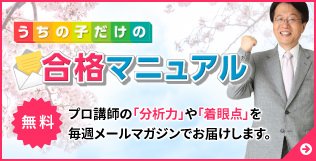



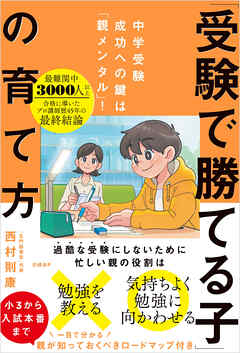
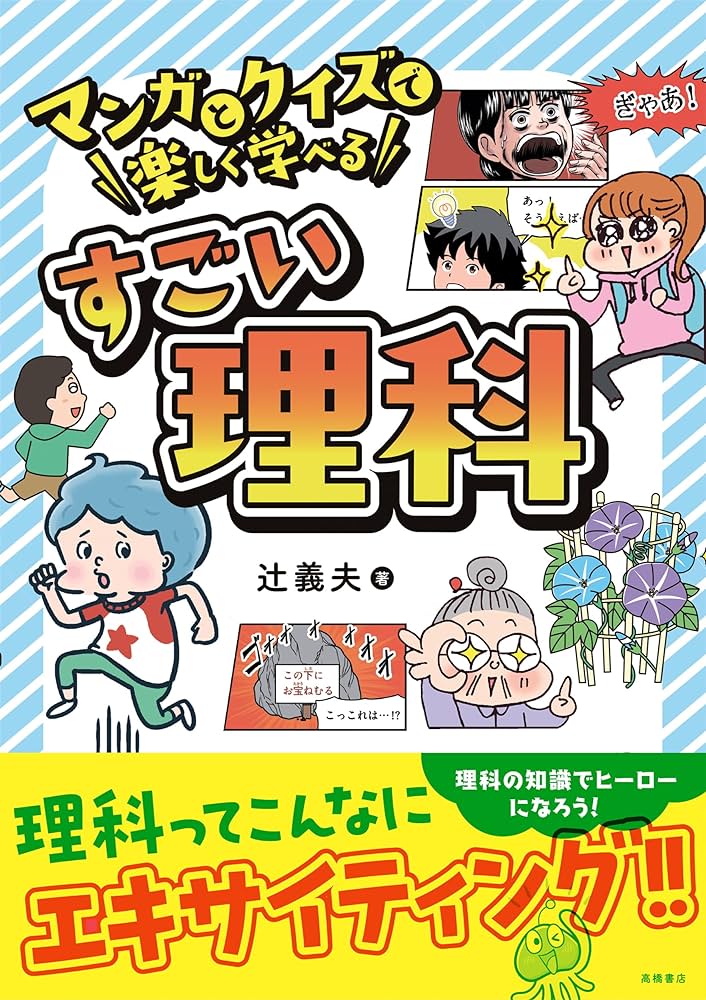
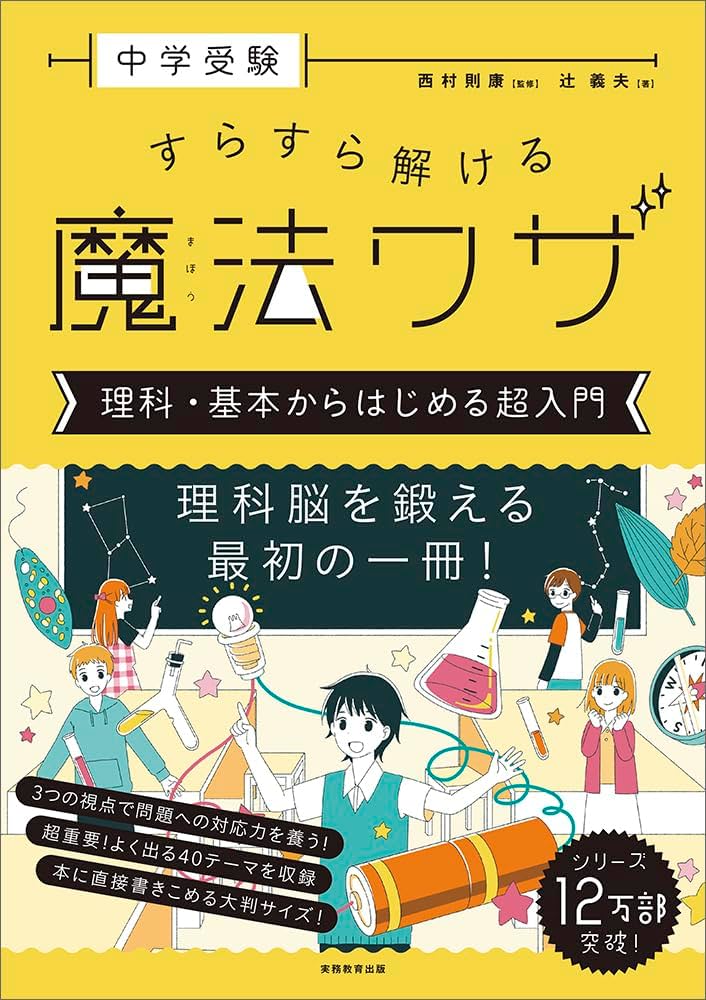
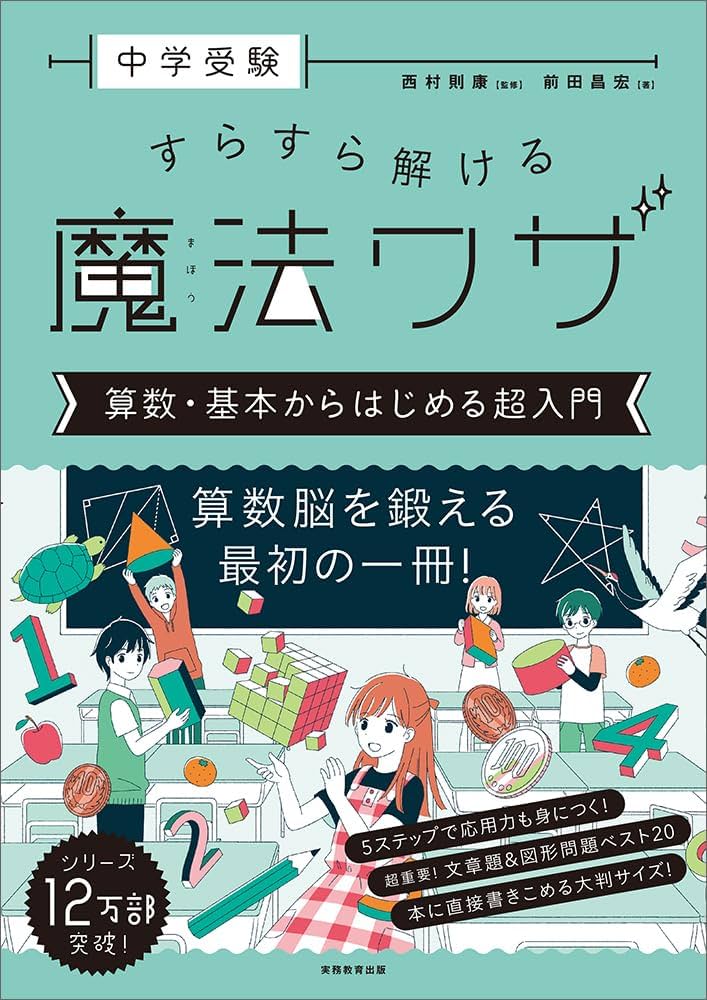
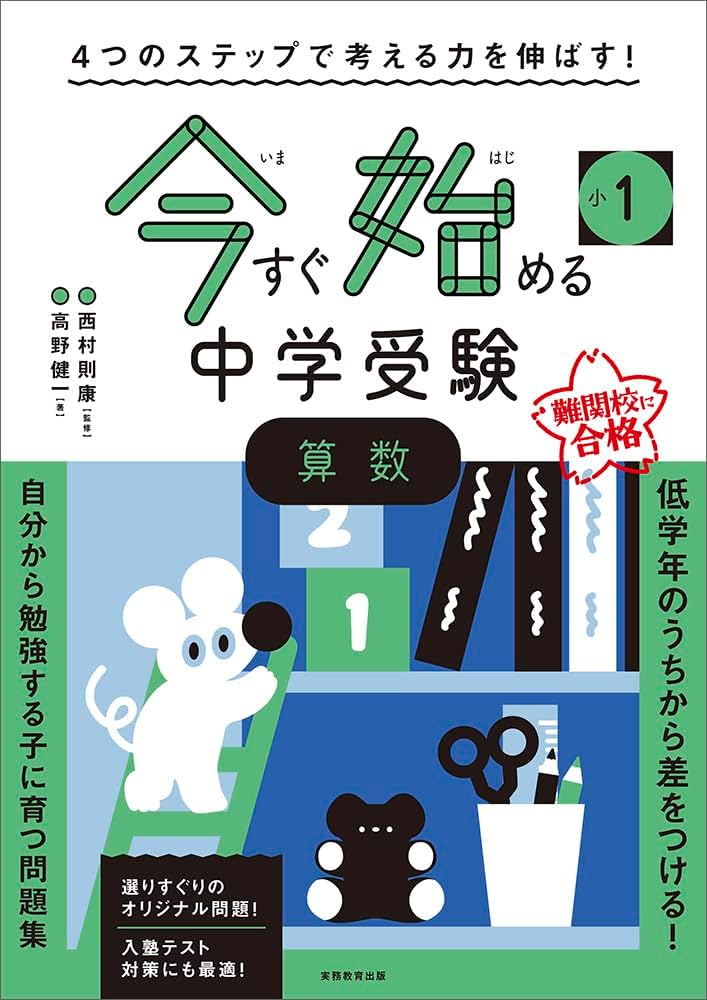
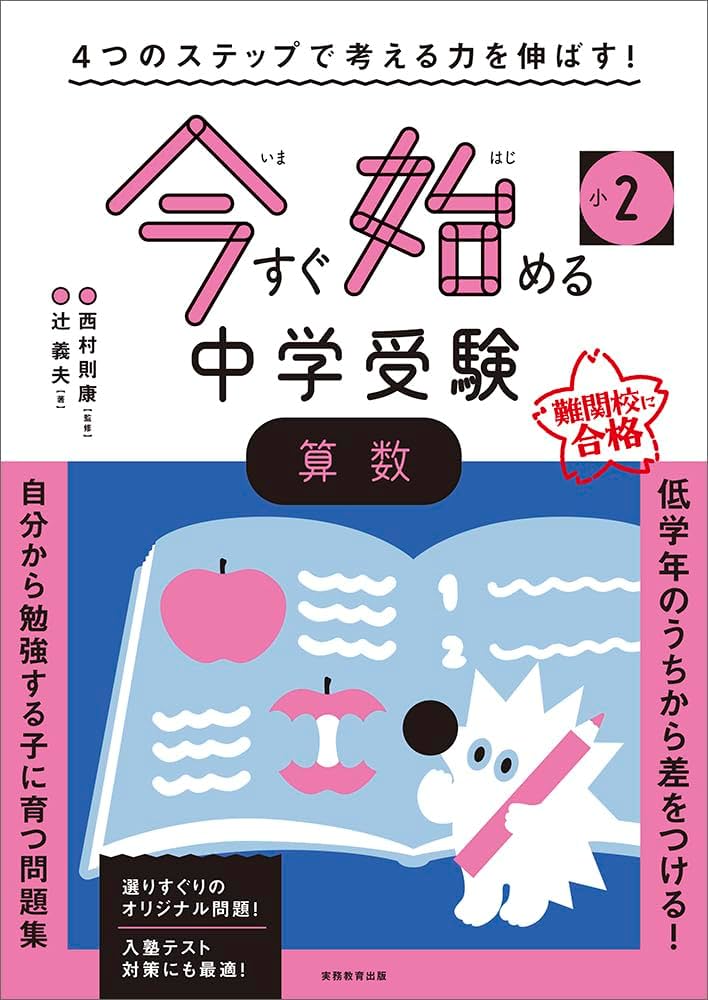
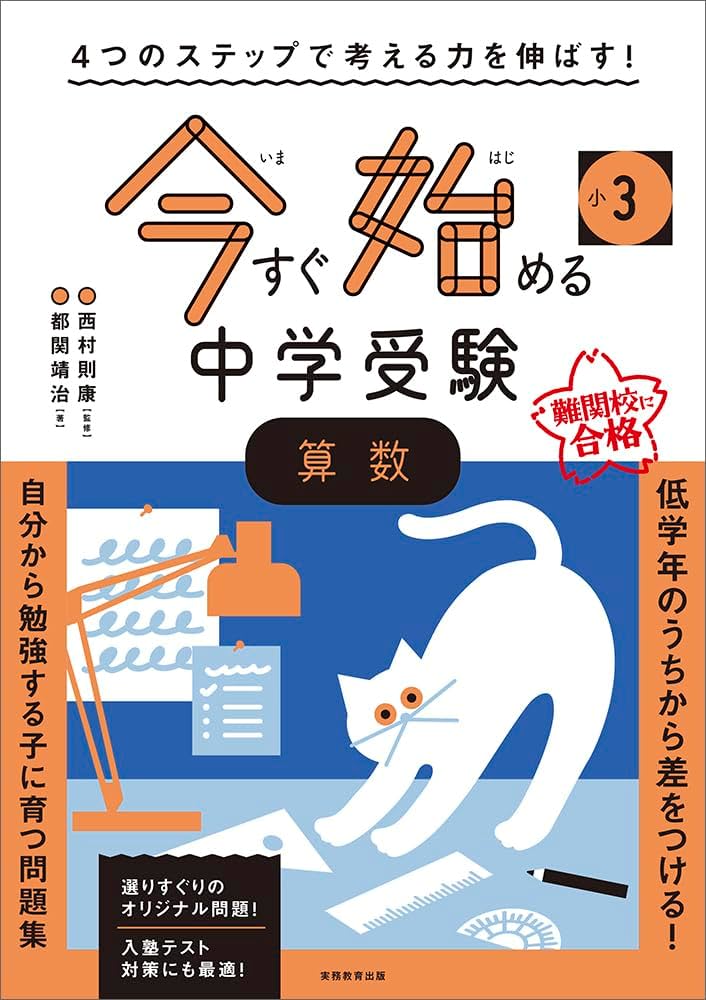
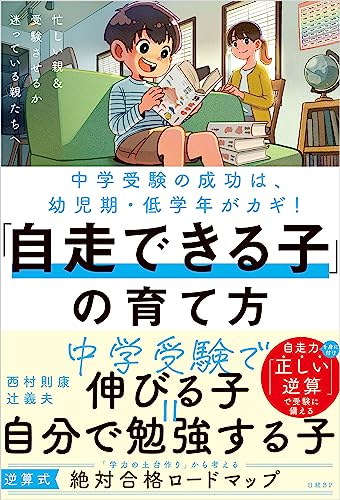
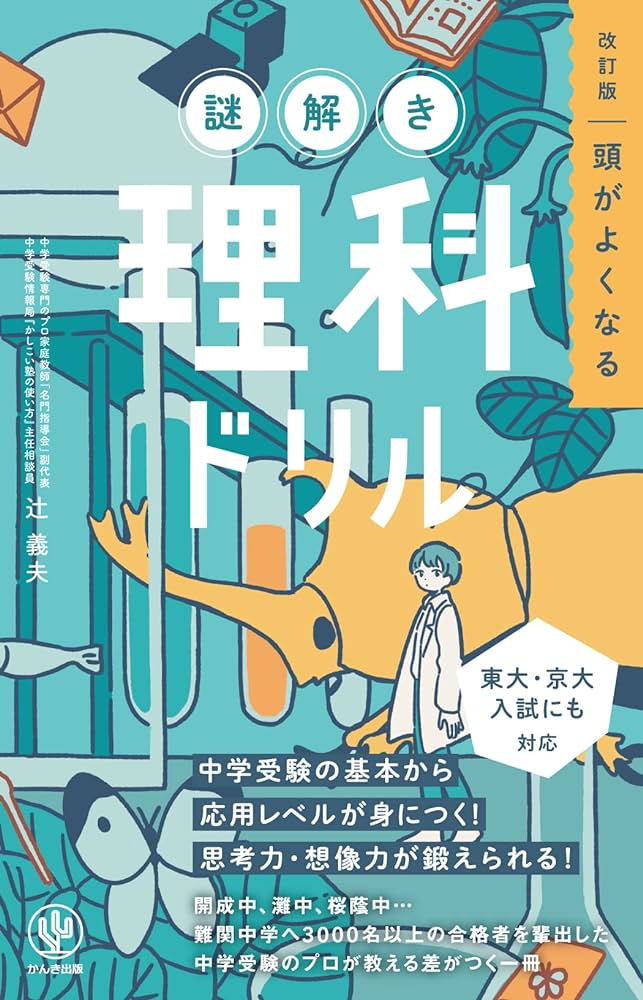
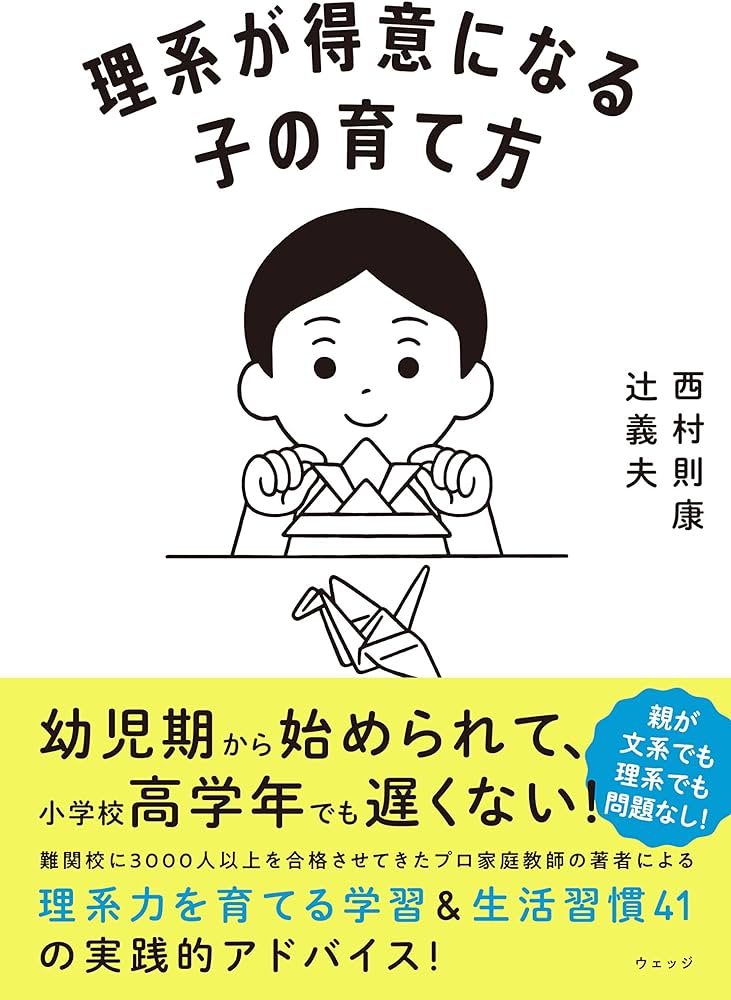

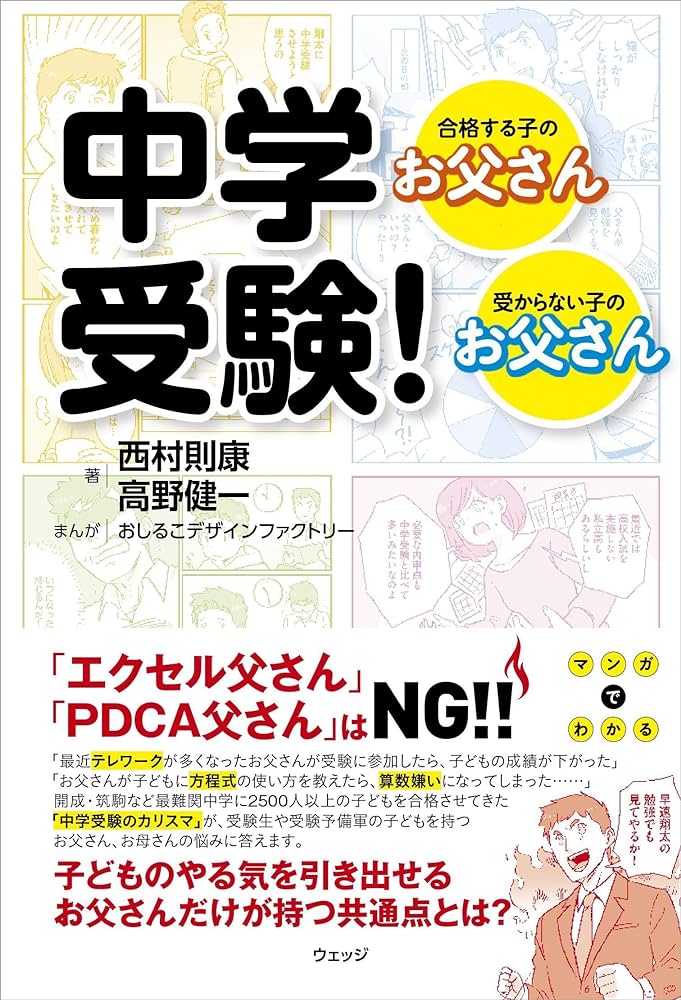
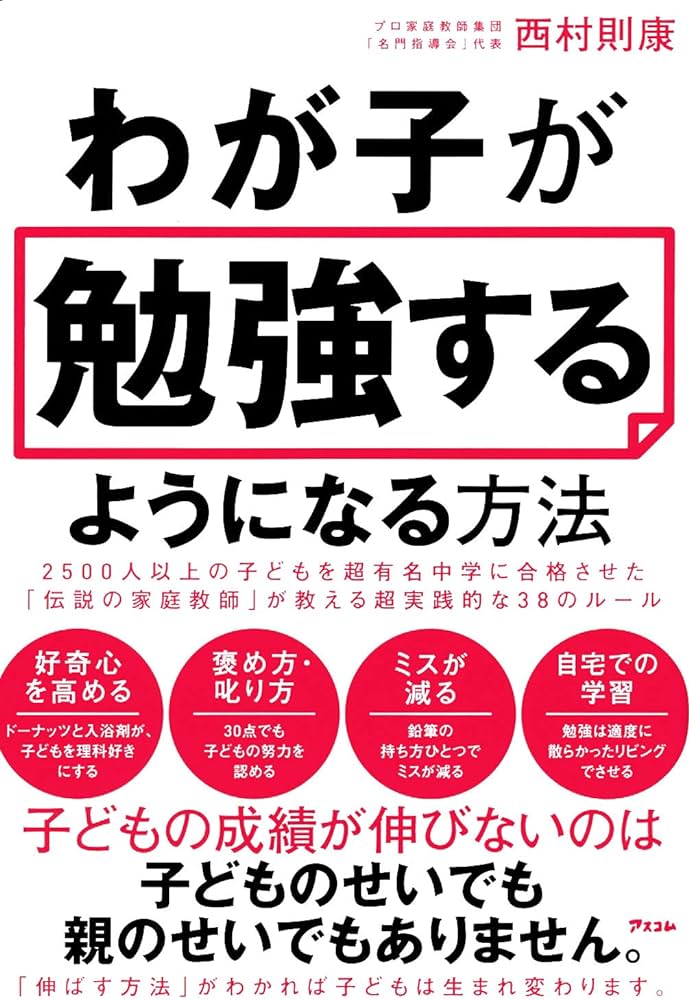
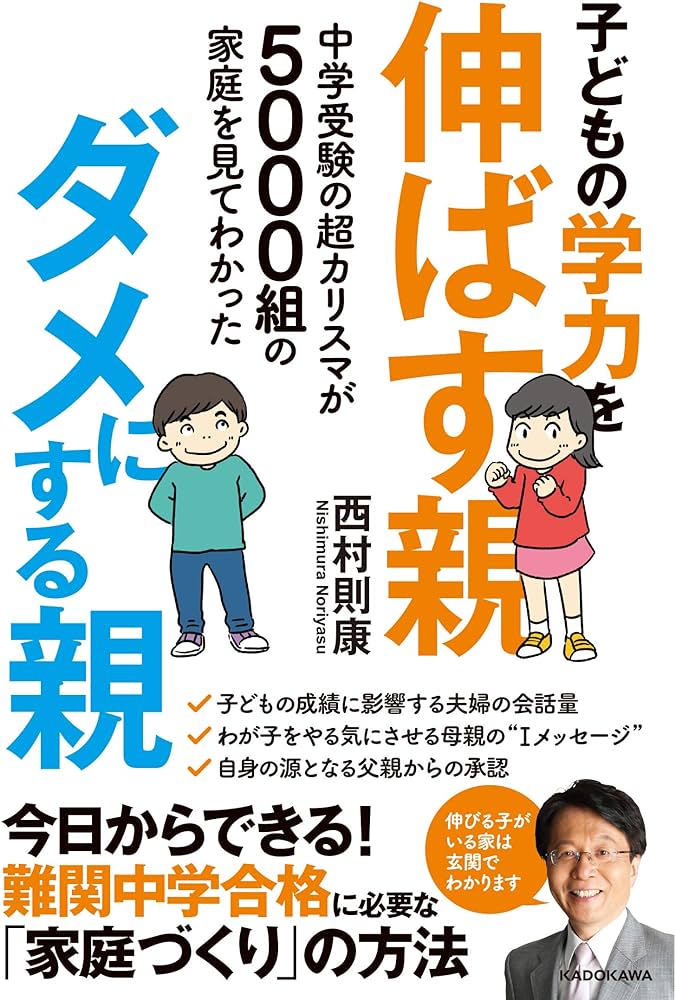
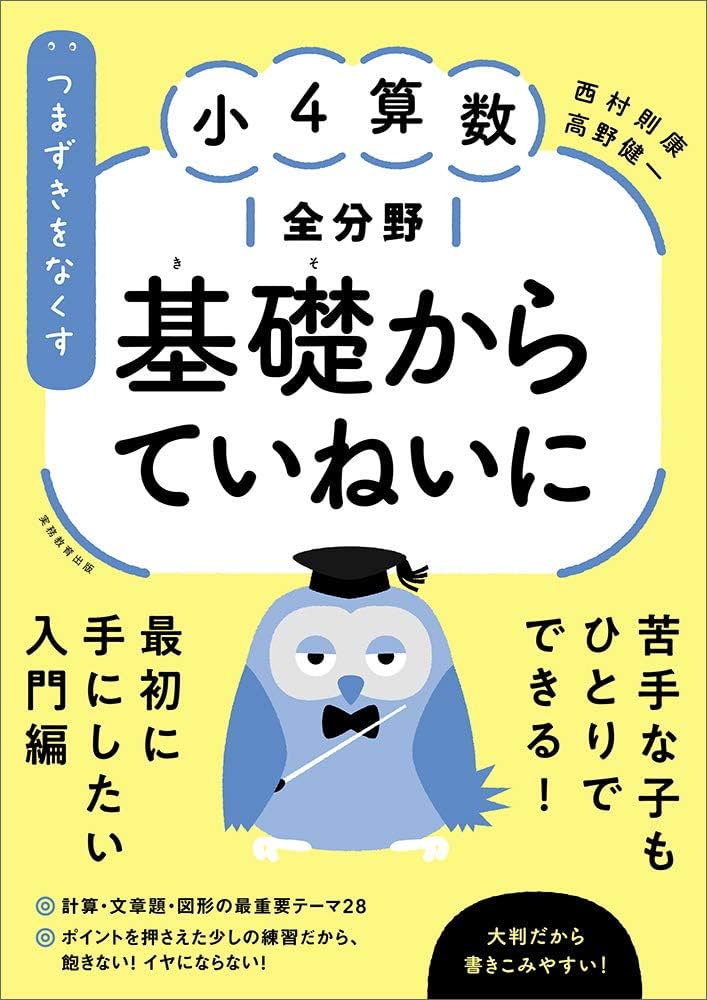
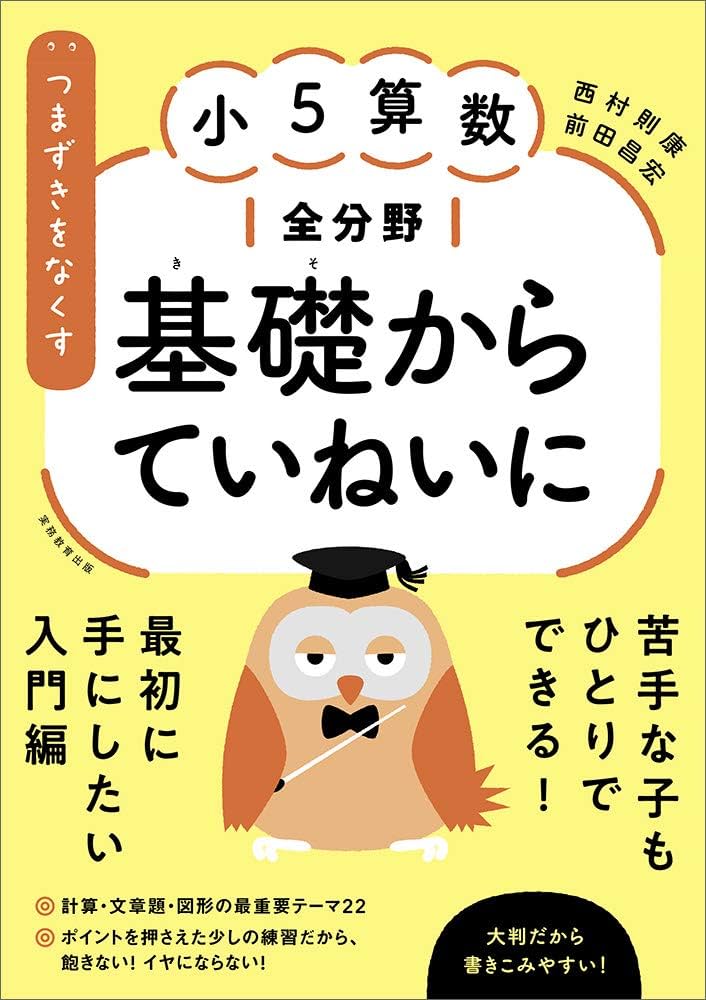
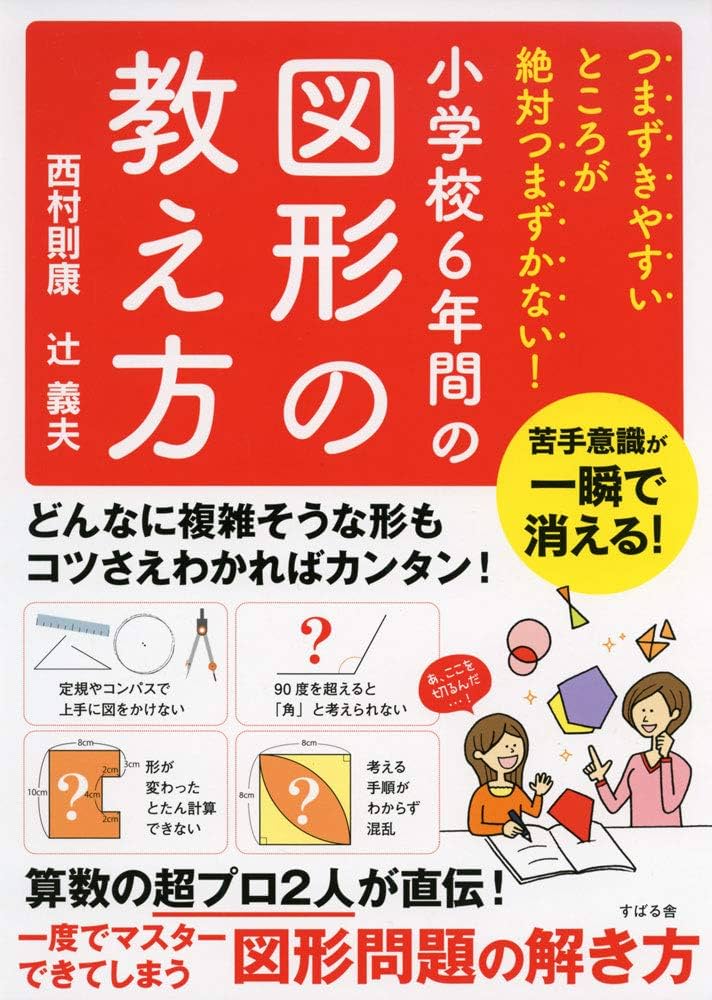
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[算数]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushsansu.jpg)
![中学受験 入塾テストで上位クラスに入るスタートダッシュ[国語]](/wp-content/themes/meimon/img/book_startdushkokugo.jpg)